様々な統計やデータ
過去の記事はこちらからどうぞ
ウィーンは世界で一番住みやすい街(2023年度)
ウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したかつての帝国の都です。
荘厳な建造物が多く建ち並び、豊かな緑に囲まれ、上品で高貴な一面もありながら、どこかいい意味での人間らしいいい加減さが感じられる街で、とても住みやすいと思います。
私はウィーン以外に住むことは考えられないほど、ウィーンの魅力に取りつかれてしまいました。(笑)
実際にウィーンの生活のクオリティーが高いことは世界的に知られています。
さて、コロナが終わって2023年の統計で、ウィーンは再度世界で一番住みやすい街に選ばれました。
(今頃になってしまいましたが)
2009年から11年連続で1位、そしてコロナ以降2023年の12回目の1位です!
| 1. | ウィーン(オーストリア) |
| 2. | チューリッヒ (スイス) |
| 3. | オークランド(ニュージーランド) |
| 3. | コペンハーゲン (デンマーク) |
| 3. | ジュネーブ(スイス) |
| 6. | フランクフルト (ドイツ) |
| 7. | ミュンヘン (ドイツ) |
| 8. | バンクーバー(カナダ) |
| 9. | シドニー(オーストラリア) |
| 10. | デュッセルドルフ(ドイツ) |
左のランキングを見て下さい。
これはMERCER (マーサー・・・世界最大の組織・人事マネージメント・コンサルティング会社)が毎年行う統計で(コロナ禍2020~2022は除く)、世界241都市を、政治、経済、社会福祉、教育、医療、文化、自然など39項目を様々な角度から調査しランク付けを行っています。「世界生活環境調査・都市ランキング」です。
ウィーンが再度1位です!!
ウィーンは特に文化、教育、住居、医療面などで高得点で、オーストリアは昔から芸術・文化の水準が高かったことがうかがえます。
治安面も重要です。
ウィーンの治安はよく、パリなどとは比べ物になりません。
オーストリアは永世中立国、その首都ウィーンには国連都市があることもその理由のひとつです。
ベスト10にランクされた街は、ヨーロッパの街が7つと大半です。
私はここにランクされたヨーロッパ全ての街を見てますが納得できます。
ちなみに日本の街は横浜47位、東京50位、大阪58位、名古屋63位です。
アジアでのトップはシンガポールの29位です。
最下位241位はスーダンのハルツームでした。
私はウィーン大好きですから、この結果はプライベート、仕事領域を含めて大変嬉しいですね。
実際に生活をしていると、もちろん全てがいいことだけではありませんが、しかしそれを含めてもウィーンは住みやすい街であることを実感しています。
御興味があれば以下マーサーのサイトを御覧下さい。
オーストリアで一番安い車のランキング
車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。
ウィーンの街にも多くの車が走っています。
日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。
街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。
後から誕生した人間がこの地球に共存させてもらっていることと同じです。
コロナ禍の2021年にオーストリアでの自動車メーカー順位を掲載しました。
今日はオーストリアで一番安い車の順位を見てみましょう。
どのメーカーの車がどれだけ安く買えるのでしょうか?
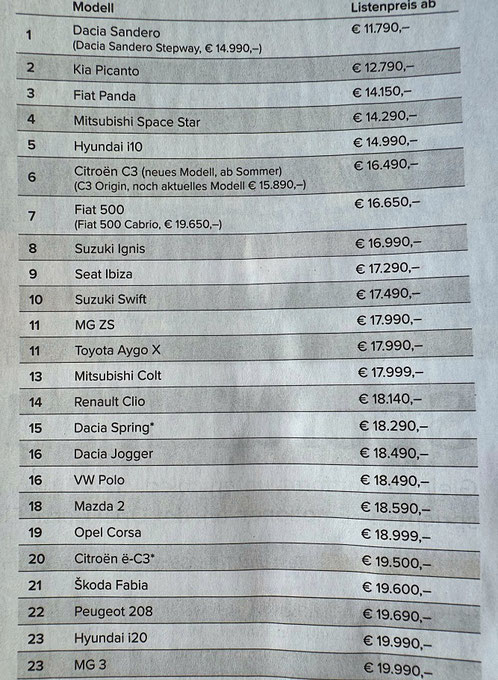
こちらはÖAMTC(Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club)
が発行している"auto touring" 2024年5月号に掲載されていたもので、オーストリアでの一番安い車種とそのメーカーが1位から順に並んでいます。
オーストリアで一番安い車は
Dacia SanderoでEUR11.790.-となっています。
Daciaは日本ではあまり知られていないのではないでしょうか。
ルーマニアのメーカーで、1966年創業、現在はルノーの傘下になっていて、従業員12.000人を超える企業となっています。
こちらではコロナ以前からかなり普及してきて、当初はあまりパッとしないいかにも安さが目立つデザインでしたが、最近では垢抜けした感がありますね。
当初からとにかく安いので話題になっていて、徐々に普及してきてる感じがありますね。
2位は韓国KIA Picantoです。
KIAもこちらでは安いイメージが定着していますね。
Suzuki、Toyota、Mitsubishi、Mazdaもランクインです。
特にSuzukiはベスト10に2台入っていますね。
値段が安い車は小さいサイズがほとんどだと思いますが、ちょい乗りする人や、走ればいいのでとにかく車があれば便利と考える人にとってはわざわざ高い車を持つ必要はないでしょう。
保険や燃料だってかかるわけですからね。
それにしてもDaicaは安いですね。
数字で見るウィーン市あれこれ(2023年度版)3
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
前回の数字で見るウィーン市あれこれ2 が好評を頂きましたので今日はその3です。
| 面積 |
415km² |
| 宅地面積 | 36% |
| 緑の比率 | 49% |
| 公共交通機関の面積 | 15% |
| 一番小さい区と一番大きい区 |
Josefstadt (8区 1.1km²)、Donaustadt (22区 102,3km²) |
| 緑の比率が最も少ない区と最も多い区 | Josefstadt (8区 1.9%)、Hietzing (13区 70.7%) |
| 一番高い住居建物、一番高い建築 |
DC Tower (250m)、 Donauturm (252m) |
| 一番標高が高い場所と低い場所 | Hermannskogel (543m)、Lobau (151m) |
| 一番低い地下鉄の駅 | U1 Altes Landgut (地下30m) |
| 墓地の比率 |
ウィーン全体の1.3% |
| ぶどう畑 | 1.9% |
| 飲料水の噴水の数 | 1.300 |
今回はウィーンの面積、緑の比率や標高が一番高い場所などを取り上げました。
ウィーンは森の都と言われている通り、街の面積の半分が緑であることがわかります。
皆さんがよく聞くウィーンの森は、その豊かなウィーンの緑をもっと外側から囲んでいる大きな森です。
ウィーンは23区で分けられたかなり広い街ですね。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその4をまとめてみたいと思います。
国立オペラ座舞踏会(2024年)
1月6日のHeilige Drei Königeが過ぎるとウィーンの街は舞踏会が至る所で開かれ、それに伴うカレンダーもあるぐらいです。
舞踏会の中で最も頂点であるのは国立オペラ座の舞踏会(Opernball・・・オペルンバル)です。
この舞踏会は復活祭がいつ来るかによって開催される日が毎年変動し ます。
謝肉祭のクライマックスである火曜日(Faschingsdienstag)の前の週の木曜日と決め られていますので、今年は2月8日の木曜日・・・つまり昨日ということになりますね。

こちらは昨日の午前中に撮影した国立オペラ座です。
舞踏会の最終準備をまだしています。
相当大掛かりな作業で、どこから見ても目立ちます。
正面入り口だけではなく、後ろの搬入口や横の部分でも作業が行われています。
<国立オペラ座舞踏会の歴史>
国立オペラ座舞踏会は、有名なウィーン会議(1814-1815) の時からだとされていますが、場所は宮廷関係の劇場ではなかったようです。
そもそも国立オペラ座自体、1868年に完成していますからウィーン会議の50年以上後ということになります。
その1820~30年代、この帝国の都ウィーンでは数々の大小の舞踏会が開かれるようになっていました。
ヨーゼフランナー、ヨハン・シュトラウス(父)が活躍する時代ですね。
それから王宮のレドゥーテンザールで開かれるようになっていきますが、1848年の革命時からはしばらく静かになります。
1862年Theater an der Wienが舞踏会開催を許されました。
1869年にリンク道路の現在の国立オペラ座を宮廷が使い始めますが、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世がここでの舞踏会を拒んでいたため、1870年に完成したニューイヤーコンサートで有名な楽友協会ホールで "Ball in der Hofoper"として開かれました。
1877年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が賛同し、初めて現在の国立オペラ座の一角で祭典が行われました。
ハプスブルグ帝国崩壊後、オーストリアが共和国となり、すぐに帝国時代の懐かしさから1921年にはすでに舞踏会が開かれました。
1935年には「Wiener Opernball」という名で開かれ、1939年第2次世界大戦前日の夜、最後のオペラ座舞踏会が開かれます。
戦後壊された国立オペラ座が1955年に修復され、1956年2月9日に現在のオーストリア共和国の初めての国立オペラ座舞踏会が開かれ、現在に至っています。
つまり今年は現在のオーストリアになって63回目ということですね。
国立オペラ座舞踏会は世界各国の著名人、貴賓が集まり、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスと決められています。
<国立オペラ座舞踏会についての色々な数字>
ゲストの数は5.150人、250万人が国立オペラ座舞踏会のテレビ中継を見ている、160組の社交界デビュー、
会場構築時間は350人の専門作業員、150人のアルバイトで30時間、解体時間は21時間、50の業者、
総費用150万ユーロ、52.600のグラス、9.200のナイフとフォーク、1.300のSekt、ワイン900本、
150人の音楽家・・・。
国立オペラ座の普段の運営もすごいものがありますが、たった1回のこの舞踏会でも物凄いものを感じます。
さて、気になる今年の料金はというと・・・
| 入場料 | EUR 385,- |
| ボックス席(ロジェ)最大8人&立ち席4人 | EUR 24.500,- |
| 舞台側ボックス席 (ダブル) 最大10人&立ち席4人 | EUR 24.500,- |
|
舞台側ボックス席 (シングル) 最大6人 |
EUR 14.000,- |
| Premium舞台側ロジェ |
EUR 18.000,- & EUR 14.000,- |
|
舞台袖テーブル、舞台裏テーブル |
EUR 220,- |
| 歌の部屋テーブル、ゲルストナーロビーテーブル | EUR 220,- |
|
Parterreロジェロビー、Opernロビー テーブル |
EUR 220,- |
| マーラーの間、シュヴィントのロジア テーブル | EUR 220,- |
| 大理石の間 テーブル | EUR 220,- |
| ギャラリー テーブル | EUR 110,- |
今年は66回目の国立オペラ座舞踏会です。
厳密に言えば、入場料は350ユーロで、35ユーロは寄付になり、税金申告で経費として認められます。
それぞれの料金は入場料とは別で、飲食も別です。
入場料だけでも385ユーロですから国立オペラ座の最高額の座席よりも高いです。
この他に65ユーロ~135ユーロのオープニングだけを見るチケットも販売されています。
年間を通して数え切れないぐらい国立オペラ座の内部案内をしていますが、毎年思いますが舞踏会だけは別世界です。
国立オペラ座舞踏会の様子のビデオが見られますので、興味ある方は御覧下さい。
https://www.wiener-staatsoper.at/opernball/
※国立オペラ座オフィシャルサイトより
数字で見るウィーン市あれこれ (2023年度版) 2
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
前回の数字で見るウィーン市あれこれ 2023年最新版が好評を頂きましたので今日はその続編です。
| 2011年~2021年の人口増加率 | 12.8% (ローマ5.8%、ベルリン11.8%、ワルシャワ4.9%) |
| 初婚の平均年齢 | 男性32歳 女性31歳 |
| 最初の子供が生まれる平均年齢 | 31歳 (1991年は26歳) |
| 双子以上が生まれる割合 | 3.2% |
| 人気ある名前 |
男性 Mateo,Luka,Theodor 女性 Sophia,Emilia,Sara |
| 人口密度 | 1km² 4778人 |
| 人口密度が一番多い区と一番少ない区 |
5区(27.350人/1km²)、 13区(1.473人/1km²) |
| 住居に利用されている土地面積の割合 | ウィーン全体 24% (個人賃貸など55%、持ち家21%) |
| 1人当たりの平均居住空間面積 | 36m² |
| 1世帯の平均居住者数 | 2.0人 |
人口密度が一番多いのはウィーン5区、少ないのは13区ですね。
持ち家よりも圧倒的に賃貸の方が多いです。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその3をまとめてみたいと思います。
数字で見るウィーン市あれこれ 最新2023年度版
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
今日は数字で見るウィーン市あれこれの最新データを更新をかねてお届けします。
| 人口 (2023年1月1日現在) | 1.982.097人 |
| 男女の割合 | 男性48.9% 女性51.1% |
| ここ10年の人口増加率 | 240.851人の増加 (+13.8%) |
| 出生と死亡 (2021年) | 出生19.142人 死亡18.041人 |
| 平均寿命 | 男性77.7歳 女性82.6歳 |
| 国籍 | オーストリア国籍65.8% |
| 外国人 | EU 国籍14.5% EU以外19.8% 180ヵ国の国籍数 |
| ウィーンに移民した数 | 134.839人 |
| ウィーンから出て行った数 | 85.192人 |
| 移民国籍ベスト3 | シリア+39.980人 ウクライナ+31.231人 ドイツ+19.470人 |
この統計はウィーン市2023年1月1日時点での統計ですが、去年9月からウィーンの人口は200万人を超えています。
全人口1.897.491人のうちでオーストリア国籍が65.8%と去年の68%よりも少なくなっています。
約34%が外国人ということになります。
国籍数も180と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいて、特にウクライナ戦争のおかげでウクライナ人が急増しました。
1位のシリア人もかなり増えています。
3位がお隣のドイツですね。
ウィーンは国連都市があることも大きいですが、ハプスブルグ帝国時代からもともと多民族国家でしたので、その流れが受け継がれていると言えるでしょう。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いものがあります。
強制送還された数(2023年上半期)
ウィーンはヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の居城があり、かつての"帝国の都"を今でも偲ぶことができます。
ハプスブルグ帝国時代は多民族国家であり、日本では考えることができない10以上の言語を持った民族から成り立っていました。
そのため帝国が解体し、オーストリア共和国となってもその首都ウィーンには今でも多くの外国人が住んでいます。
それ以外にも難民の申請もあり、審査の結果が出るまではオーストリアのどこかに滞在することになります。
難民として認められなければ強制送還ですが、難民以外でも滞在許可等の問題などで強制送還される人も多くいるようです。
今日は今年2023年度上半期にどこの国へどのくらい強制送還をされているかのデータを紹介します。
右の表を御覧下さい。
こちらはオーストリア内務大臣が先日発表した2023年度上半期のAbschiebestatistik(国外追放の統計)です。
合計で5.872人がオーストリア国外に追放されていますが、その内右の表に見られる2.178人が強制送還されています。
どこの国へどのくらい強制送還されているかということなのですが、ランクされた国を見ると意外なことに難民が多く来る国ではなく、かつての共産圏・・・旧東欧諸国が多いことがわかります。
スロヴァキアがトップで605人も強制送還されています。
| 1. スロヴァキア | 605 |
|
2. ルーマニア |
263 |
| 3. ハンガリー | 238 |
|
4. ポーランド |
175 |
|
5. セルビア |
164 |
|
6. チェコ |
101 |
|
7. ブルガリア |
75 |
|
8. インド |
63 |
|
9. ナイジェリア |
54 |
|
10. ジョージア |
52 |
| 11.その他 | 388 |
| 合計 | 2.178 |
スロヴァキアの首都ブラティスラヴァはウィーンからたったの65kmですし、旧共産圏と言えども今はEUにも入っていて、通貨もユーロが導入されていますね。
日本からの団体ツアーでもかなり頻繁にブラティスラヴァに寄って行きますね。
2位がルーマニア、3位がハンガリーです。
ウィーンを歩くとルーマニア人が増えていることは実感出来ます。
オーストリア政府のBMI (Bundesministerium für Inneres)によると、強制送還される45%はヨーロッパ諸国ということです。
これは滞在許可などが下りなかったり、こちらで事業が認められなかったりなど色々な要因があると思います。
旧東欧圏はEUに入っている国が多くなっても、オーストリアと比べればまだまだ物価的には安いので、収入も違います。
iPhone15が登場したことで、旧モデルがいくらで売られている?
昨日9月15日からiPhone15が正式に予約できるようになりましたね。
全世界共通の予約開始時間だと思いますのでオーストリアでは14:00、日本では21:00でした。
私も今回iPhone15を予約しました。
Appleにはまっているわけではありませんが、私なりの理由があるんです。
個人的にスマフォは好きではなく、docomoのガラケーを長年愛用していて、iPadAirを家で使い、iPad miniを持ち歩いているというスタイルなんですね。
オーストリアでは5Gの普及に伴って、ウィーンから3Gが徐々に廃止され、2024年の終わりまでには全国的に3Gが終わることになりました。
今までdocomoのガラケーを何不自由なく快適に使っていましたが(もちろんオーストリアのSIMを利用してます)今年7月ぐらいからウィーンの街中でも多くの場所が圏外になってきました。
最初はSIMか携帯電話の問題かと思っていたのですが、SIMを新しくして、ストックしてある新品のガラケーを使っても同じ現象が起きています。
iPadは4G/LTEなのでdocomoのガラケーが圏外でも、iPadは旗が全部立っていることから原因が分かりました。
自分のキャリア会社から7月13日にそのことについてのインフォが来ていましたが、最初は結び付きませんでした。
こちらのガラケースタイルも数機種販売されているのですが、とても使う気にならず、不本意にもいよいよスマフォデビューということになりました。
そんなタイミングでiPhone15が発表され、スマフォならiPhoneだろうなと思っていましたし、私はコンピューターなどは最新バージョンを買う主義なので、iPhone14などの旧モデルは視野に入れず、そこで今回14:00過ぎに速攻で最上位モデルのiPhone 15 Pro Maxを予約したというわけです。
なんだかんだ言いながらも楽しみですね。(笑)
さて、長くなりましたが、iPhone15が出たことによって、旧モデルはどのくらいの値段になるのでしょうか。

右の表を御覧下さい。
これは一昨日9月14日付の新聞に掲載されていた統計で、情報元はWillhabenです。
Willhabenは日本だとメルカリに相当するサイトで、様々な物が売られています。
iPhone14 Pro Max,iPhone14 Proが1.000ユーロを超えていますね。
中古とは言え、綺麗に使っていればいい値段で売れるんですね。
やっぱりiPhoneは元々高いこともあり、他と比べると売る時も高く売れます。
日本では半数以上の61%がiPhone愛用者という統計を見ましたが、こちらではそこまでiPhoneは普及してないように思えます。
高いですしね。
Samsungは強いですね。
値段もiPhoneと比べてかなりお得ですし、性能も悪くないようです。
電話が出来ればいい・・・車だって走ればいい・・・でもこれはそれぞれの価値観の問題なので、何を重要視するかは人によって違いますよね。
iPhone15の発売は9月22日です。
Appleからは今の所9月22日にピックアップできるようになっていますが、日本では納期がかなり遅れているようですね。
無事に9月22日に手にすることができるでしょうか。
オーストリアの所得税の税率 2023年現在
オーストリアは小国でもありながらそれなりの経済大国です。
一見、観光立国的なイメージがあると思いますが、実は色々な産業があります。
物価もヨーロッパでは高い方で、税金の天引き率はヨーロッパでは6番目、食料品はデンマークの次の2番目、人件費はベルギーの次に高いという国の統計があります。(コロナからは変わっているかもしれません)
また、私のように事業主だとUmsatzsteuer(売上税)とEinkommensteuer(所得税)の2つが課せられています。
Umsatzsteuerは20%と決められています。
例えば私に観光を申し込まれた場合は料金には20%の売り上げ税が含まれています。
Einkommensteuerは売り上げから必要経費を引いて実際の収入がどのくらいか(こちらではGewinnとよく言われますがどのくらいプラスになったか)によって課せられます。
そのEinkommensteuerの税率を見てみましょう。
右の表は売上全体から全ての経費を引いて実際にプラスとして残った収入(前述したようにGewinnと言います)に対して、どのくらいの所得税率が定められているかを示しています。
オーストリアでは年間Gewinnが11.693ユーロ以下であれば所得税はかかりません。
|
所得 (Gewinn) |
割合 |
| 11.693ユーロまで | 0% |
| 11.693~19.134ユーロまで | 20% |
|
19.134~32.075ユーロまで |
30% |
| 32.075~62.080ユーロまで | 41% |
| 62.080~93.120ユーロまで | 48% |
| 93.120~1.000.000ユーロまで | 50% |
| 1.000.000ユーロ以上 | 55% |
この数字のボーダーライン付近の稼ぎがある人は、どのくらいのGewinnになるかある程度計算して仕事をしている人がたくさんいます。
例えばGewinnが19.000ユーロであれば20%の所得税ですから3.800ユーロの納税ですね。
しかし、19.135ユーロのGewinnとなると次のランクである30%となるので5.740ユーロに跳ね上がるわけです。135ユーロ多く稼いだだけで、税金が1.940ユーロも増えるわけです。
これなら計算して仕事をしない方が得ということになります。
ちなみにオーストリアでは年間11.000ユーロの所得を超える場合や、他からの収入が730ユーロ以上あって年間12.000ユーロ以上の場合はSteuererklärung(いわゆる確定申告)をする義務があります。
税金はなるべく払いたくないのが本音ですから、ボーダーラインには注意をしたいですね。
夏至の日照時間
今週の月曜日からウィーンは日中の気温が今年初めて30℃を超えています。
今年はちょっと遅い気がします。
例えば去年初めて30℃を超えた日は5月20日でしたからひと月近く遅かったわけですね。
今日は夏至です。
ドイツ語ではSommersonnnenwendeと言い、年間を通して一番日が長い日ですね。
夏至のこの時期は学校ももうすぐ終わり、年度末、もうすぐ休暇と気持ちがワクワクする時期で、ウィーンの街にはそんな空気がそこらじゅうに漂っています。
実際、どのくらいの日照時間があるのでしょうか?
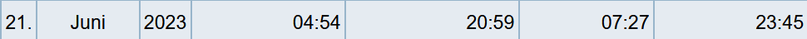
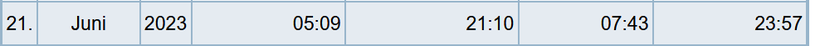

こちらは今日夏至の日照時間の比較で、一番上からウィーン、ザルツブルク、インスブルックです。
時間は左から日の出、日の入り、月の出、月の入りです。
ウィーンは日の出が4:54、日の入りが20:59なので日照時間が16時間5分もあります。
ザルツブルクが16時間2分、インスブルックが15時間56分ですね。
実際、日の入り後でも空はすぐには暗くならないので、西の空が22:00過ぎごろまで少し明るさが見られます。
インスブルックでは月の入りがないということですね。
こちらはGeoSphere Austriaから引用しました。
数字で見るウィーン市あれこれ (2022年度) 2
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
前回の数字で見るウィーン市あれこれ 2022年最新版が好評を頂きましたので今日はその続編です。
| 2010年~2020年の人口増加率 | 13.1% (ローマ8.4%、ベルリン6.6%、ワルシャワ4.4%) |
| 初婚の平均年齢 | 男性33歳 女性31歳 |
| 最初の子供が生まれる平均年齢 | 31歳 (1990年は26歳) |
| 双子以上が生まれる割合 | 3.1% |
| 人気ある名前 |
男性 Matteo,Leon,Maximiian 女性 Sophia,Sara,Emilia |
| 人口密度 | 1km² 4656人 |
| 人口密度が一番多い区と一番少ない区 |
5区(26.710人/1km²)、 13区(1.431人/1km²) |
| 住居に利用されている土地面積の割合 | ウィーン全体 24% (個人賃貸など55%、持ち家21%) |
| 1人当たりの平均居住空間面積 | 35m² |
| 1世帯の平均居住者数 | 2.0人 |
この統計はウィーン市2022年の統計によるものです。
人口密度が一番多いのはウィーン5区、少ないのは13区ですね。
持ち家よりも圧倒的に賃貸の方が多いです。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその3をまとめてみたいと思います。
現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その22
今年3月1日よりウィーンでの公共交通機関利用時のマスク着用義務もなくなり、5月からは医療施設などでのマスク着用義務もなくなり、6月終わりをもってコロナ危機が終了する方向でオーストリア政府は準備を続けています。
実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?
今日は前回の休暇前からしばらく日が経ったので1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を、5月21日にはその19を、7月4日にはをその20を、9月1日はその21を掲載しました。
今日は半年以上ぶりに現在どうなっているか感染状況を見てみましょう。


上の表は今年3月11日から3月25日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。
半年前と比較するとオーストリア全体的かなり減少しています。
実際には2回目、3回目、4回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。
各表の一番右側の数字は100.000人単位です。

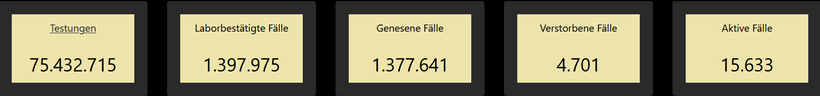
上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
前回と比べると現在の発病数はやはり少なくなっています。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
国立オペラ座舞踏会(2023年)
1月6日のHeilige Drei Königeが過ぎるとウィーンの街は舞踏会が至る所で開かれ、それに伴うカレンダーもあるぐらいです。
舞踏会の中で最も頂点であるのは国立オペラ座の舞踏会(Opernball・・・オペルンバル)です。
この舞踏会は復活祭がいつ来るかによって開催される日が毎年変動し ます。
謝肉祭の最高点である火曜日(Faschingsdienstag)の前の週の木曜日と決め られていますので、今年は2月16日の木曜日・・・つまり昨日ということになりますが、まだ現在進行形でやっていますね。


国立オペラ座正面入り口で、ちょうど舞踏会の正面入り口の構築が始まっています。
相当大掛かりな作業で、どこから見ても目立ちます。
正面入り口だけではなく、後ろの搬入口や横の部分でも作業が行われています。
<国立オペラ座舞踏会の歴史>
国立オペラ座舞踏会は、有名なウィーン会議(1814-1815) の時からだとされていますが、場所は宮廷関係の劇場ではなかったようです。
そもそも国立オペラ座自体、1868年に完成していますからウィーン会議の50年以上後ということになります。
その1820~30年代、この帝国の都ウィーンでは数々の大小の舞踏会が開かれるようになっていました。
ヨーゼフランナー、ヨハン・シュトラウス(父)が活躍する時代ですね。
それから王宮のレドゥーテンザールで開かれるようになっていきますが、1848年の革命時からはしばらく静かになります。
1862年Theater an der Wienが舞踏会開催を許されました。
1869年にリンク道路の現在の国立オペラ座を宮廷が使い始めますが、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世がここでの舞踏会を拒んでいたため、1870年に完成したニューイヤーコンサートで有名な楽友協会ホールで "Ball in der Hofoper"として開かれました。
1877年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が賛同し、初めて現在の国立オペラ座の一角で祭典が行われました。
ハプスブルグ帝国崩壊後、オーストリアが共和国となり、すぐに帝国時代の懐かしさから1921年にはすでに舞踏会が開かれました。
1935年には「Wiener Opernball」という名で開かれ、1939年第2次世界大戦前日の夜、最後のオペラ座舞踏会が開かれます。
戦後壊された国立オペラ座が1955年に修復され、1956年2月9日に現在のオーストリア共和国の初めての国立オペラ座舞踏会が開かれ、現在に至っています。
つまり今年は現在のオーストリアになって63回目ということですね。
国立オペラ座舞踏会は世界各国の著名人、貴賓が集まり、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスと決められています。
<国立オペラ座舞踏会についての色々な数字>
ゲストの数は5.150人、146万人が国立オペラ座舞踏会のテレビ中継を見ている、144組の社交界デビュー、会場構築時間は350人の専門作業員、150人のアルバイトで30時間、解体時間は21時間、50の業者、総費用140万ユーロ、46.000以上のグラス、1.000枚のテーブルクロス、4.000のナイフとフォーク、1.300のSekt、ワイン900本、ビール900本、150人の音楽家・・・。
国立オペラ座の普段の運営もすごいものがありますが、たった1回のこの舞踏会でも物凄いものを感じます。
さて、気になる今年の料金はというと・・・
| 入場料 | EUR 350,- |
| ボックス席(ロジェ) | EUR 23.600,- |
| 舞台側ボックス席 (ダブル) | EUR 23.600,- |
| 舞台側ボックス席 (シングル) | EUR 13.300,- |
| 舞台側ロジェ テーブル付き | EUR 11.500,- |
|
6人用テーブル |
EUR 1.260,- |
| 4人用テーブル | EUR 840,- |
| 3人 テーブル(相席) | EUR 630,- |
|
2人 テーブル (相席) |
EUR 420,- |
| 6階 4人用テーブル席 | EUR 420,- |
| 6階 2人用テーブル(相席) | EUR 210,- |
今年は2020年以来、65回目の国立オペラ座舞踏会です。
今年の料金は2020年度と入場料以外は全く変わりません。
厳密に言えば、入場料は315ユーロで、35ユーロは寄付になり、税金申告で経費として認められます。
それぞれの料金は入場料とは別で、飲食も別です。
入場料だけでも350ユーロですから国立オペラ座の最高額の座席よりも高いです。
ちなみにミネラルウォーターの0.3Lが9.90ユーロで販売されていますね。
年間を通して数え切れないぐらい国立オペラ座の内部案内をしていますが、毎年思いますが舞踏会だけは別世界です。
国立オペラ座舞踏会の様子のビデオが見られますので、興味ある方は御覧下さい。
https://www.wiener-staatsoper.at/opernball/
※国立オペラ座オフィシャルサイトより
数字で見るウィーン市あれこれ 最新版
今日は成人の日ですね。
自分がはるか昔に成人式に行ったことを思い出します。
私がウィーンに住み始めて日本で成人の日を迎えるのは初めてです。
ウィーンはクリスマス休みも終わり、今日から学校が始まります。
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
今日は数字で見るウィーン市あれこれの最新データを更新をかねてお届けします。
| 人口 (2022年1月1日現在) | 1.931.593人 |
| 男女の割合 | 男性48.9% 女性51.1% |
| ここ10年の人口増加率 | 214.509人の増加 (+12.5%) |
| 出生と死亡 (2021年) | 出生19.359人 死亡18.086人 |
| 平均寿命 | 男性77.7歳 女性82.6歳 |
| 国籍 | オーストリア国籍67.8% |
| 外国人 | EU 国籍14.1% EU以外18.0% 179ヵ国の国籍数 |
| ウィーンに移民した数 | 88.073人 |
| ウィーンから出て行った数 | 78.492人 |
| 移民国籍ベスト3 | シリア+31.251人 ドイツ+18.677人 ルーマニア+18.556人 |
この統計はウィーン市2022年の統計によるものです。
ウィーンは23区で分けられたかなり広い街です。
全人口1.897.491人のうちで約68%が地元オーストリア人、約32%が外国人ということになります。
国籍数も179と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいます。
ウィーンは国連都市があることも大きいですが、ハプスブルグ帝国時代からもともと多民族国家でしたので、その流れが受け継がれていると言えるでしょう。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いですね。
数字で見るウィーン市あれこれ 4
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
前回の数字で見るウィーン市あれこれ3 が好評を頂きましたが、その後かなり時が流れていきましたが、今日はその4です。
| Samrt City Strategy Index | Wien (1位)、London(2位)、St.Albert(3位) |
| ビックマック指数 | Wien(17.9分)Berlin(18.4分)、Rom(23.5分) |
| 国際会議数 | Paris(212)、Wien (172)、Madrid(165) |
| 市役所で働いている人 | 男性 13.480人、女性 17.201人 |
| 市役所外での職員数 | 住居 702人、病院同盟 28.864人、下水道 518人、電気ガス6.060人 |
| Vindobonaという名称 | AD 50年 |
| ウィーン市議会選挙結果(2015年) | SPÖ 39.6%, FPÖ 30.8%, Grüne 11.8% ÖVP 9.2%, NEOS 6.2% |
| 有効投票数 | 832.987 |
今回はウィーンのビックマック指数、国際会議数、役所関係などを取り上げてみました。
ウィーンは国際会議が非常に多く開かれる街で、パリに次いで2位です。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその5をまとめてみたいと思います。
ウィーンを流れる川の長さ
全長2.800km以上あるドナウ河の最も美しい所がオーストリアにあるヴァッハウ渓谷ですね。
ウィーンにはそのドナウ河が流れていることはあまりにも有名ですが、そのドナウ河以外、ウィーンにある川を意識したことはありますか?
ウィーン川なんかは中心界隈を流れているのですぐ思い浮かぶかもしれませね。
それ以外にもウィーンには実は多くの川があるんですね。
こちらはウィーンの街を流れる川がどのぐらいの長さで、ウィーン23区のどこを流れているかをまとめたものでウィーン市役所のサイトから引用しています。
基本的に数km以上の川がまとめられています。
ドナウ河が一番長いことがすぐに想像できますが、ドナウ河も左岸と右岸とではウィーン市を流れる長さが違うことも面白いです。
これはウィーン市の境界線がどうなっているかを見ればすぐにわかります。
この表では左が川の名称、真ん中が長さ、右が何区を流れているかです。
ウィーンの街には意外と多くの川がありますね。
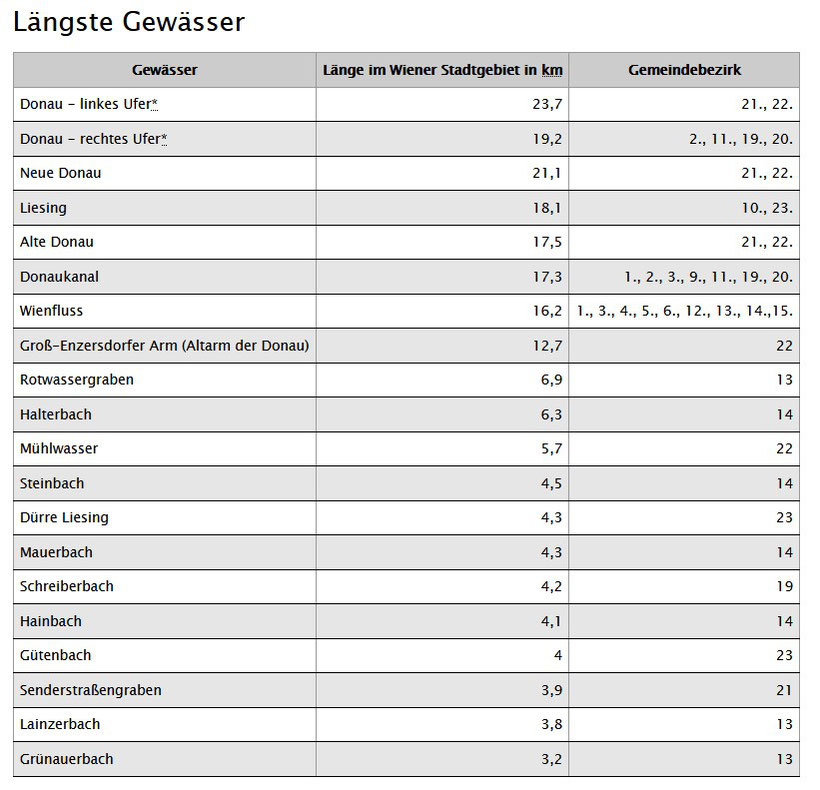
9月7日より日本入国が緩和されました
夏休みも終わり今週月曜日から学校も始まっています。
今年はコロナ禍でも2年前と比べると多くの人が休暇に出かけ、コロナはほぼ終わっているという意識を持っている人が多くなっているようです。
オーストリアでは5月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っていて、8月1日より陽性でも隔離がなくなりました。
日本でも昨日9月7日から日本入国に際しての72時間以内のPCR陰性証明が条件付きで要らなくなり、外国人の入国も少し緩和されましたのでまとめておきます。
<検疫措置:出国前72時間以内の検査証明提出の見直し〉
令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。
詳しくは 検疫措置(NEW)をご覧ください。
令和4年9月7日午前0時以降、アルバニア、シエラレオネについては「赤」から「黄」へ、アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エスワティニ、エリトリア、カーボベルデ、ギニアビサウ、クック諸島、グレナダ、コモロ、サモア、サントメ・プリンシペ、サンマリノ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ソマリア、チャド、ツバル、ナウル、ニウエ、バヌアツ、ブルネイ、ボツワナ、ホンジュラス、モーリシャスについては「黄」から「青」へ、それぞれ変更となります。
3区分の国・地域リスト
〈外国籍の方の新規入国〉
「水際対策強化に係る新たな措置(29)」に基づき、令和4年6月10日以降、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国が原則として認められることとしていましたが、令和4年9月7日午前0時(日本時間)より、下記(2)に該当し新規入国を認める外国人は、すべての国・地域の方が対象となり、添乗員を伴わないパッケージツアーについても認めることとなりました。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヵ月以下)の新規入国(3月1日から引き続き実施)
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(6月10日から)
(3)長期間の滞在の新規入国(3月1日から引き続き実施)
現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その21
夏休みも今週で終わり、来週月曜日から学校も始まります。
気分一新して新年度の始まりです。
今年はコロナ禍でも2年前と比べると多くの人が休暇に出かけ、コロナはほぼ終わっているという意識を持っている人が多くなっているようです。
オーストリアでは5月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っていて、8月1日より陽性でも隔離がなくなりました。
9月7日から日本でも入国に際しての72時間以内のPCR陰性証明が要らなくなるということで、旅行業界でも期待が大きく持たれています。
実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?
今日は前回の休暇前からしばらく日が経ったので1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を、5月21日にはその19を、7月4日にはをその20を掲載しました。


上の表は8月15日から8月30日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。
前回と比較するとオーストリア全体的に半数に減少しています。
オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。
実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。
各表の一番右側の数字は100.000人単位です。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
前回と比べると現在の発病数はやはり少なくなっています。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その20
学校も先週の金曜日で終わり、夏休みに入りました。
社会はそれに合わせて休暇シーズン突入です。
今年はコロナ禍でも2年前と比べると多くの人が休暇に出かけ、コロナはほぼ終わっているという意識を持っている人が多くなっているようです。
オーストリアでは5月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っています。
しかし・・・
学校行事で泊まりに行って帰ってきたらかなりの生徒がコロナに感染してたという話をよく聞きますし、知り合い枠でも感染している人が本当に増えてきています。
実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?
今日は前回からしばらく日が経ったので1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を、5月21日にはその19を掲載しました。

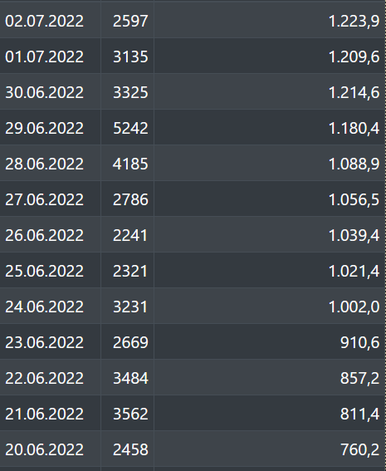
上の表は6月20日から7月2日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。
前回と比較するとオーストリア全体的に2~3倍に増えていますね。
オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。
実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。
各表の一番右側の数字は100.000人単位です。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
前回と比べると現在の発病数は倍以上に増えていますね。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
オーストリアには岩塩抗がいくつある?
オーストリアに旅行に来てお土産に岩塩を買って行く人も多いと思います。
ウィーンは荘厳な建造物に囲まれたかつての帝国の都なので、岩塩との結びつきはあまり感じませんが、オーストリアに来る前にちょっと予習した方はオーストリアでは岩塩が採掘されていることに気付くでしょう。
ウィーンと岩塩の結びつきはあまり感じませんと書きましたが、ウィーンでは岩塩が採掘されないというだけのことで、ローマ時代、中世に塩はザルツブルク方面からウィーンに頻繁に運ばれていました。
今の私達の時代でもオーストリアの家庭では岩塩が使われていますので、現在の生活でも岩塩は切っても切れない関係にあります。
海もないのに塩が・・・と思う方が多いかもしれませんが、オーストリアは国土の63%が山岳地帯で、ヨーロッパアルプスが横たわっています。
そんなオーストリアアルプスの一角では今でも岩塩が採掘されています。
オーストリアには岩塩抗がいくつあるのでしょうか。

※Land schafft Leben より引用
上の図を御覧下さい。
オーストリアには全部で5つ岩塩抗が存在しますが、そのうち現在でも塩が採掘されているのは
Hallstatt、Altaussee、Bad Ischlの3か所です。
HalleinとHall In Tirolは岩塩抗として残されていますが、塩の採掘は行われていません。
さらにHallstatt、Hallein、Altausseeの3ヵ所は一般公開されていて見学することができ、Hall In TirolにはBergbaumuseumという坑道をまねて作った博物館があります。
Bad Ischlは土砂崩れにより岩塩抗への道が塞がったため1999年7月より一般見学は閉鎖されています。

こちらはHallstattですが、岩塩抗がある上の方から湖畔の街を眺めています。
ここまでは徒歩でも行けますが、通常はケーブルカーを利用します。
Hallstattは世界最古の岩塩抗で、7.000年前(紀元前5.000年頃)から塩が採掘されていました。
オーストリアでは前述した3か所で年間1.200.000トンの塩が採掘されています。
1日150トン、1時間2.5トンの採掘量です。
岩塩採掘に関わっている人の2/3は岩塩抗で、1/3は地上での仕事です。
ヨーロッパ全体的に60%がSiedesalz・・・つまりオーストリアのように岩塩抗の地層を溶かして飽和状態の塩水を作り、それを沸騰させて塩を取り出すスタイルで、30%がSteinsalz(塩の岩)・・・文字通り塩の塊をくだいてふるいで分けて精製する、そして10%が海水から太陽光線を利用して塩を作る・・・大きくこの3つの方法が存在します。
オーストリアの家庭で使われている塩は地元で作られている岩塩です。
お土産にもお勧めですし、時間があれば是非岩塩抗も訪れてみたいですね。
現在のコロナ感染状況 オーストリアでの統計 その19
先月4月16日からコロナ規制がさらに緩和されて、ウィーンでもカフェやレストランに入るための2G証明の提示もなくなり、かなり色々な場所でコロナ以前の空気を感じるようになってきました。
さらに今月16日からオーストリア入国にあたってのコロナ規制がなくなりましたので、オーストリア入国はコロナ以前の状態に戻っています。
実際の所オーストリアでのコロナ感染状況は現在どうなっているのでしょうか?
今日は前回から2ヵ月経ったので、1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17、3月17日にはその18を掲載しました。


上の表は5月7日から5月19日までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。
前回と比較するとオーストリア全体では感染者数が1/10に減っています。
ウィーンも同様に減っています。
オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。
実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。
各表の一番右側の数字は100.000人単位です。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
前回と比べると現在の発病数は同様にかなり少なくなっていますね。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
1日の感染者数が6万人を超えた オーストリアでの統計 その18
オーストリアは1日の感染者数が6万人を超えました。
その反面コロナ規制が2月より徐々に緩和され、3月5日からはさらに緩和され2G,3Gなどの規則がほぼなくなりました。(ウィーンは他州よりは規則が厳しくなっていますが)
先日オーストリア政府はワクチン接種義務を一時中断することも発表しています。
今日は前回からちょうどひと月経ったので、1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を、2月17日にはその17を掲載しました。


上の表は3月3日から3月16日0:00までの1日の感染者数で、左がオーストリア全土、右がウィーン市です。
オーストリア全体では1日の感染者数が6万人を超えました。
ウィーンでも13.004人ですね。
オーストリア全人口が約900万人ですから、1日3万人のペースで感染していけば、計算上では300日で全人口が感染することになります。
実際には2回目、3回目の感染だという人の話もよく聞きますし、多くの感染者がワクチン接種を3回済ませています。
各表の一番右側の数字は100.000人単位です。
おそらく感染者数は多くても、重症化が少ない傾向なので規制を緩和していると思われます。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
相変わらず1日の感染者数が多い オーストリアでの統計 その17
オーストリアではコロナ規制が徐々に緩和されています。
3月5日以降、2G,3Gなどの規則がなくなり密集する場所のマスク着用以外は普通に戻るという噂が流れています。
ワクチン接種義務になったからでしょうか。
しかし、オーストリア政府が接種義務を決めても、実際どうなるかはまだわからないという状況です。
1日の感染者が相変わらず多く、自分の知り合いの中でもワクチン接種済にもかかわらず感染する人が多くなってきました。
今日は1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をお知らせします。
新型ウィルスに関しての統計はすでにまとめています。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を、1月23日にはその16を掲載しました。
右の表は2月3日からの1日の感染者数で、
左がオーストリア全土
右がウィーン市
です。
2月8日はオーストリア全体で40.034人もの感染者が確認されています。
2月5日からSemesterferien(学期休み)が始まり、色々な所に出かける人も多かったと思います。
州によってSemesterferienの日が違うので、少しは分散したかもしれません。
私の周りでも前述したようにワクチン接種をしていても感染した人の話を多く聞くようになりました。




上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
1日の感染者数が急増 オーストリアでの統計 その16
ここ数日オーストリアでは1日の感染者数が軒並み増加しています。
1月8日から1日の感染者数が1万人を超え、その後連日増加していきここ数日では3万人弱になっています。
先週木曜日にはオーストリアの国会でワクチン接種義務化に関する投票があり、Nationalrat(国民議会)183議席のうち、賛成が137人、反対が33人,棄権13人という結果になりました。
ほぼワクチン接種義務が成立しそうです。
今日は1日の感染者数の推移と病院状況をオーストリア全体とウィーンの状況をお知らせします。
新型ウィルスに関しての統計はすでにまとめています。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を、2022年1月15日にはその15を掲載しました。
右の表は1月14日からの1日の感染者数で、
左がオーストリア全土
右がウィーン市
です。
1月20日はオーストリア全体で29.611人、ウィーンでは8258人もの感染者が確認されています。
クリスマス以降ほぼ増加傾向でありましたが、クリスマス休暇が終わって社会が始まった1月10日より急激に感染者数が増えています。
私の周りでもワクチン接種をしていても感染した人の話を多く聞くようになりました。




上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。


上段はオーストリア全土、下段はウィーンです。
左上は追加利用可能な病院ベット数、右上は追加利用可能な集中治療のベット数、
左下はベット利用数、右下は集中治療室利用数。
ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その15
今週から学校も始まり、クリスマス休暇を終えて仕事に出る人も多かったでしょう。
クリスマスの空気が徐々に消えて行きました。
うちでも昨日クリスマスツリーを片付けて処分しました。
さて、今日は久しぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を、11月11日にはその14を掲載しました。
去年の12月12日よりワクチン未接種者以外のロックダウンが終了し、クリスマスに向けて、そして年明けと人でも多くなってきたわけですが、オミクロン株がオーストリアでも急激に広がっていて、1日の感染者が軒並み増加しています。
右の表は今年に入ってからの1日の感染者数で、ほぼ増加傾向でありましたが、社会が始まった1月10日より急激に感染者数が増えています。
私の周りでもワクチン接種をしていても感染している人が何人か出て来ました。



左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
ひと月前の比べると全ての場合でかなり増加しています。

右のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、左は100.000人に対しての統計です。
青が男性、黄色が女性です。
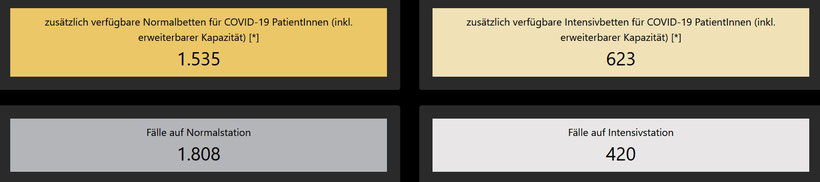
1.535の追加利用可能な病院ベット数、623の追加利用可能な集中治療のベット数、
1.808のベットが利用中、420の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。
右の表は数値で表示されています。
84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。
右の表はオーストリア州別の死亡数の統計です。
割合的に死亡者数が一番多いのはウィーン、次いでSteiermarkとなっていて、オーストリア全体での平均は13.456人です。
死亡者が一番少ないのはBurgenlandですね。
ウィーンは人口から計算すると2.825人が亡くなっていることになります。
割合では0.001479%の死亡率ということになります。
ワクチン未接種者の肩身が相変わらず狭くなっている空気を感じます。
ワクチン接種をした人だって軒並み感染してますし、他人に移す可能性だってあります・・・にもかかわらず自分はもう接種したから大丈夫などと軽はずみな行動を取る人が多く、それが新規感染者数増加につながっている原因のひとつでもあると思います。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
ウィーンにはどのぐらいの街路樹がある?
ここ数日は青空がほとんど見られないどんよりした空模様が続いています。
でも一昨日の日曜日からロックダウンが解除され、街中はクリスマスプレゼントを買おうとする人が繰り出していて、活気が戻って来ました。
昨日はショッピングリゾートのG3に行きましたが、結構人出がありましたね。
知り合いの話だとクリスマスプレゼントになりそうな物は売り切れが続出しているそうです。
さて、ウィーンは"森の都"と形容されていますが、ウィーンはヨーロッパの街の中で、街の広さに対して緑の比率が最も高い街です。
ウィーンの中心のリンク道路沿いだけでも6つの公園があり、それ以外にも様々な公園、庭園、並木、街路樹が多く見られます。
ウィーンの街を歩けば、この街は緑が豊かだな~ときっと思われるでしょう。
しかし、その広大な緑を囲むもっと大きな緑がウィーンの森です。
今日はウィーンの街にはどのぐらい多くの街路樹が植えられているのかをまとめてみました。
ウィーン市の面積は約415km²、人口約191万人、東京と同じ23区で成り立っています。
東京は市がたくさんありますが、ウィーンはウィーン市が23区で成り立っています。415km²と言えば、かなり広い街であることがわかります。
見所も中心界隈だけでなく、外側にも多く点在しています。
ウィーンの街には約93.000本の街路樹が植えられていますが、以下簡単にまとめてみました。
右の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at/index.html(日本労働組合総連合会のような機関)2021年10月号に掲載されていたデータです。
右側はウィーンのそれぞれの区です。
| 9.000本以上 | 21,22 |
| 6.000~9.000 | 2,10,13,19,23 |
| 3.000~6.000 | 11,12,14,16,18,20 |
| 1.000~3.000 | 1,3,9,15,17 |
| 1.000以下 | 4,5,6,7,8 |
Donaustadt (22区)に一番多くの街路樹が植えられているようで、ここだけで1万本以上です。
もっとも22区は面積が一番大きい区でもあり、住居がたくさん建設されていますが、あまりウィーンらしくない区です。
逆に一番少ないのはJosefstadt(8区)で、500本以下です。旧市街の1区はその周辺区と比べると緑が多いことがわかります。
2区にそんなに多くの街路樹があるようには思えないのですが、プラター公園やアウガルテンなどがあるからでしょうか。
ウィーンの街路樹の1/4以上がカエデ、ボダイジュが約15.000本、マロニエが約10.000本です。
ちなみにマロニエが一番多い区は2区です。
緑が多いということは空気の良さにも比例しますね。
ウィーンは"森の都"です。
コロナウィルス ザルツブルク州が過去7日間ヨーロッパで最も感染しやすい!
今日の朝は今年一番の冷え込みとなり、7:00の時点でマイナス1.9℃でした。
日中も5℃前後、金曜日は雪の予報も出ています。
さてオーストリアでは一昨日の月曜日から5度目のロックダウンに入っています。
ロックダウン数日前からたぶんロックダウンになるだろう・・・という空気が流れていて、先週金曜日の午前中に正式に発表がありました。
地元ではおそらく賛否両論だと思いますが、土曜日の午後遅く、それに関しての大規模なデモも行われ、リンク道路も封鎖されて交通渋滞が至る所で発生していました。
その11月20日の土曜日の新聞にヨーロッパではどのぐらいコロナウィルスの発生率があるのかという統計が掲載されていました。

上の表は11月20日付のSalzburger Nachrichtenに掲載されたWHOからのデータです。
ヨーロッパを617の地域に分け、どの地域が最もコロナウィルスに感染しやすいかの統計です。
10月20日の新聞ですから、そこから7日間遡ったデータとなります。
地域が色分けされていますが、過去7日間で100.000人単位で500以上が最も黒い色になっています・・・オーストリアは完全にまっ黒ですね・・・😢
右のデータは過去7日間の100.000人単位とした発生率で、残念なことにザルツブルク州がトップで1782,0、2位がOberösterreichの1606,8となっています。
去年2020年は11月3日からロックダウンが始まりましたが、今年はそれよりも遅く・・・でも同じ時期のロックダウンです。
効果があるでしょうか・・・。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その14・・・また感染者数増加傾向
一昨日から昨日にかけてオーストリアではコロナ禍となって新規感染者数がもっとも多くなり、11.300人となりました。
ワクチン接種がかなり広がっているにもかかわらずです。
オーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめます。
この統計は2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後2021年9月にその12を、10月10日にはその13を掲載しました。

左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
ひと月前の比べると全ての場合でかなり増加しています。

右のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、左は100.000人に対しての統計です。
青が男性、黄色が女性です。

1.535の追加利用可能な病院ベット数、623の追加利用可能な集中治療のベット数、
1.808のベットが利用中、420の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。
右の表は数値で表示されています。
84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。
右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。
割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は126人です。
死亡者が一番少ないのはVorarlbergですね。
ウィーンは人口から計算すると2.521人が亡くなっていることになります。
割合では0.00132%の死亡率ということになります。
最近ワクチン未接種者の肩身が狭くなっている空気を感じます。
ワクチン接種をした人だって感染しますし、他人に移す可能性だってあります・・・にもかかわらず自分はもう接種したから大丈夫などと軽はずみな行動を取る人が多く、それが新規感染者数増加につながっている原因のひとつでもあると思います。
入院している人の40%はワクチン接種者です。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
オーストリアでの自動車メーカー順位(2020年度)
今日は朝6:00の時点で温度計は4.3℃を示していました。
気温的にはもう冬のような感じです。
予報では晴れマークはあるものの日中10℃ぐらいにしかならないようです。
週末はちょっと気温が上がるようですね。
さて、車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。
ウィーンの街にも多くの車が走っています。
日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。
街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。
後から誕生した人間がこの地球に共存させてもらっていることと同じです。
オーストリアは世界的に見てかなりの車の保有率があり、ウィキペディアに掲載されている統計によれば19位となっていて、1.73人に1台の割合で車を所有しているようです。
ちなみに日本は17位、1.69人に1台の割合ですのでオーストリアとほとんど変わりません。
さて、今日はオーストリアにはどのメーカーの車がどれだけ走っているのかという2020年度の統計を紹介します。
| 順位 | 車メーカー | 台数 | 市場割合(%) |
| 1. | VOLKSWAGEN | 1.033.770 | 20.3 |
| 2. | Audi | 385.372 | 7.6 |
| 3. | BMW | 317.582 | 6.2 |
| 4. | Skoda | 309.776 | 6.1 |
| 5. | Ford | 297.557 | 5.8 |
| 6. | Opel | 284.573 | 5.6 |
| 7. | Mercedes | 283.923 | 5.6 |
| 8. | Seat | 211.679 | 4.2 |
| 9. | Renault | 210.067 | 4.1 |
| 10. | Peugeot | 183.250 | 3.6 |
| 11. | TOYOTA | 156.266 | 3.1 |
| 12. | Mazda | 153.443 | 3.0 |
| 13. | Fiat | 151.592 | 3.0 |
| 14. | Hyndai | 147.032 | 2.9 |
| 15. | Citroen | 121.651 | 2.4 |
| 16. | Kia | 109.347 | 2.1 |
| 17. | Suzuki | 107.712 | 2.1 |
| 18. | Nissan | 82.793 | 1.6 |
| 19. | Dacia | 80.905 | 1.6 |
| 20. | Volvo | 65.576 |
1.3 |
| 21. | Mitsubishi | 54.108 |
1.1 |
| 22. | Honda | 41.337 |
0.8 |
上の表はStatistik Austriaからの引用です。
オーストリア全土で2020年にどのメーカーの車がどれだけ走っているかとそのシェア率を示しています。
1位は圧倒的にVolkswagenで全体の20.3%を占めています。
5台に1台はVWですから非常に人気があります。
私も2011年の3月まではVWに乗ってました。
今はもちろん日本車に乗ってます。(笑)
Audi、BMW、Skodaと続き、日本車ではTOYOTAがトップで11位、3.1%のシェア率、次いでMazdaが12位で3.0%です。
この統計は新車認可数ではなく、現在国に登録されて走っている車ですから、新車から20年前やそれ以前の車も含まれます。
非常に興味深い統計です。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その13
先週の火曜日まで日中25℃ぐらいの半袖で過ごせる秋晴れの青空が広がるいい陽気でしたが、水曜日から雨が降り始め、気温がぐっと下がりました。
晴れマークこそ見られるものの日中せいぜい15℃ぐらい、朝は一桁で冷え込んできました。
さて、今日はひと月ぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。
この統計2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。その約9ケ月後にその12を、そして今日は現在の状況をまとめてみました。

左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
ひと月前の比べると全ての場合でかなり増加しています。
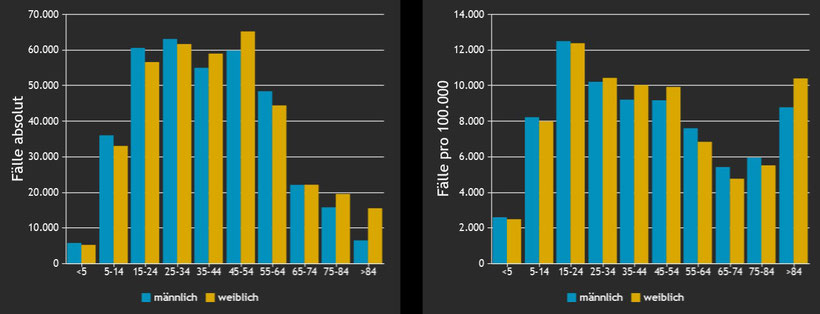
左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。
青が男性、黄色が女性です。

1.751の追加利用可能な病院ベット数、658の追加利用可能な集中治療のベット数、
624のベットが利用中、221の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。
右の表は数値で表示されています。
84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。
右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。
割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は121.5人です。
死亡者が一番少ないのはVorarlbergですね。
ウィーンは人口から計算すると2.433人が亡くなっていることになります。
割合では0.00127%の死亡率ということになります。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、ワクチン接種をした人であっても1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。
軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
ウィーンでワクチン接種をした人、申し込んでいる人は現時点で何人ぐらい? その2
早いもので今日が9月最後の日ですね。
私のライブツアーを楽しみにされている皆さん、9月15日ライブツアーVol.46をお届けして以来、仕事、学校関係や日本語の会などずっと忙しくて、ライブツアーが出来ませんでした。
来週ぐらいから再開したいと思いますので、もう少し待ってて下さい。
今年は去年と比べるとかなり多くの人がオーストリアだけでなく外国にも出かけています。
検査も充実し、ワクチン接種者も増加していますので、状況は去年とは比較にならないでしょう。
ウィーン州においては、飲食店等に入場する際に提示が必要な証明について、検体採取から24時間以内(連邦規定では48時間以内)の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、または検体採取から48時間以内(連邦規定では72時間以内)の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果とされました。
さて、現時点ではウィーンで実際どのくらいの人がワクチン接種をしているのでしょうか?
| ワクチン接種を申し込んでいる人 | 1.129.849人 |
| ワクチン接種を申し込んでいる企業数 | 443.880 |
| すでに接種された数 | 2.380.998 |
| ワクチンの種類 |
Pfizer/Biontech 1.679.084 AstraZeneca 331.940 Moderna 268.234 Johnson&Johnson 101.740 |
| 接種1回目 | 1.277.762 |
以下の統計は男女、年齢別に見たワクチン1回目の接種状況です。
薄い色は男性、濃い色は女性です。
30~39歳と50~59歳が一番多いですね。
若い世代も意外と多くの人が接種していて、10代も数万人が接種しています。
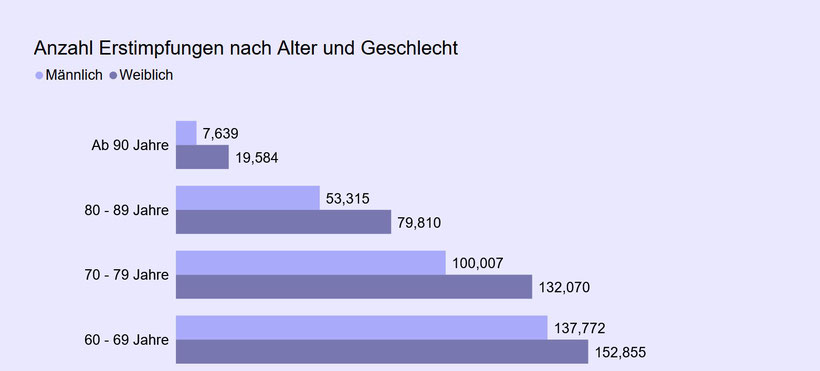

私はオーストリア政府が予防接種をしなければ仕事ができませんと決めない限りは、現時点で接種するつもりは全くありません。
変異ウィルスに対してもまだ効力があるかはわかりませんしね。
結局はインフルエンザのように共存していくようになると思います。
ウィーン主要劇場の年間観客数
ウィーンには多くの劇場があります。
真っ先に思い浮かぶのは国立オペラ座だと思いますが、それ以外にも地元で人気ある劇場がたくさんあります。
ウィーンの街は文化に興味ある方が多く、文化水準が非常に高いと思いますね。
これはウィーンがヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の居城であり、そのハプスブルグ家から歴代神聖ローマ皇帝が多く輩出され、その皇帝の居城であると同時に、ハプスブルグ家自体が芸術・文化を積極的に取り入れたこともあり、ウィーンは非常に文化水準が高い街となっています。
さて、今日はその主要劇場と、年間を通してどのくらいの観客数があるかについてまとめてみます。
| 劇場名 |
座席数 (立ち席は含まない) |
年間の訪問者数(2018/2019) |
| Staatsoper (国立オペラ座) | 1.709 | 628.000 |
| Volksoper | 1.261 | 312.000 |
| Burgtheater | 1.175 | 294.000 |
| Ronach | 1.001 | 268.000 |
| Theater in der Josepstadt | 610 | 168.000 |
| Theater der Jugend | 230(I)/667(VII) | 134.000 |
| Raimundtheater | 1.193 | 131.000 |
| Akademietheater | 500 | 121.000 |
| Kammerspiele | 471 | 121.000 |
| Volkstheater | 970 | 113.000 |
| Theater an der Wien | 1.129 | 72.000 |
全体では2.361.000の訪問者数、3.640の公演数です。
あらためてウィーンはオペラ、演劇がとても充実していることがわかります。
特に国立オペラ座は公演数だけではなく、毎日違った演目を上演しますので、特筆すべきものがあります。
この統計はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft 2021年6月10日号に掲載されていたものです。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その12
夏休みも終わり、来週月曜日から学校も始まります。
新年度ですね。
今年は2回目のコロナ禍での休暇シーズンでしたが、去年と比べるとかなり多くの人がオーストリアだけでなく外国にも出かけています。
検査も充実し、ワクチン接種者も増加していますので、状況は去年とは比較にならないでしょう。
しかし、オーストリア政府は国内における制限措置を9月30日まで延長し、さらにウィーンにおいて陰性証明書の有効期限が9月1日より変更となり短くなっています。
さて、今日は久しぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。
この統計2020年5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。
その後約9ケ月が経過して今年に入って初めての統計を紹介します。

左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。
青が男性、黄色が女性です。

1.624の追加利用可能な病院ベット数、686の追加利用可能な集中治療のベット数、
396のベットが利用中、143の集中治療室が利用中。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。
右の表は数値で表示されています。
84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。
右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。
割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は118.4人です。
死亡者が一番少ないのはVorarlbergですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、ワクチン接種をした人であっても1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。
軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

ここで紹介したデータはオーストリア連邦保健省管轄である Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) の新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードから引用しています。
オーストリア重要企業 (2021年)
ウィーンには地元の企業を始め、様々な外資系企業があり、また国連都市ということもあって各国の政府関係者、報道関係と色々な人が駐在しています。
かつては日本の企業も多くウィーンにはありましたが、日本経済の影響からかなりの企業が撤退しました。
日本から駐在する場合は、それだけ余計な費用がかかるわけですからね。
さて、地元オーストリアでの重要企業の今年度のトップ10が今年6月終りに発表されたので、んな企業が名を連ねているか見てみましょう。
※eurobrand より
(1EUR=¥100 で計算しています)
| 1.Red Bull (エネルギードリンク) | 1兆5988億円 |
| 2.Novomatic (Casino) | 2968億円 |
|
3.SWAROVSKI |
2741億円 |
| 4.Spar (スーパーマーケット) | 2341億円 |
|
5.ÖBB(オーストリア国鉄) |
1967億円 |
| 6.ERSTE (銀行) | 1956億円 |
| 7.Raiffeisen (銀行) | 1915億円 |
| 8.Verbund (電力会社) | 1342億円 |
| 9.OMV (鉱油、ガス) | 1241億円 |
| 10.XXXLutz (インテリア家具) | 1062億円 |
Red Bullが圧倒的な差をつけて1位です。日本でも知られているこのエネルギードリンクはモーツァルトが生まれたザルツブルク州に本社があります。
スヴァロフスキーのクリスタルも日本では有名ですね。
日本からの皆さんもウィーンで買われる方が多いですが、本社はチロルで、インスブルックのそばにあるWattensです。
銀行の利子がつかない中、それでも2つの地元で有名な銀行も入っています。
9位にランクしているOMVはウィーン国際空港から中心に向かう時に左側に見える巨大な石油精製所でお馴染みです。
その他地元で有名な企業がランクインしています。
ウィーン公共交通機関の様々なデータ
ウィーンの公共交通機関はよく発達していて、世界でも5本指に入る営業距離数を持っています。
地下鉄 (U-BAHN)、路面電車(STRASSENBAHN)、路線バス(AUTOBUS)がウィーン市交通局の運営で、国鉄(SCHNELLBAHN)もウィーン市内であれば共通券で乗れるシステムになっています。
公共交通機関はウィーン市民の重要な足であると同時に、観光で訪れる方々にとっても必要不可欠でしょう。
ウィーンを歩けば街の景観に合った路面電車がたくさん走っているのが見られます。
これだけ見てもウィーンを感じますね。
今日はこのウィーンの公共交通機関についての様々なデータをアップデートしましたので御覧下さい。

ウィーン市は415km²、23区から成り立ち、191万の人口を持つかなり広い街です。
そのウィーンの街を2018年までで地下鉄、路面電車、路線バスが162路線、1.149.1kmの営業距離数があります。
これだけの数の公共交通機関が毎日活躍しているわけです。
ウィーンに住んでいると公共交通機関が本当によく網羅されていることを実感しますが、たとえウィーンに住んでいなくても、自分の力で公共交通機関を利用してしっかり観光した方はそれが実感できるはずです。
| ウィーン市全ての路線数 | 162 |
| 車庫数(検車区) | 10 |
| 停留所の数 | 5.390 |
| 営業総距離数 | 1.151.5km |
| 1路線を1区間とした路線総距離数 | 263km |
| 線路の総距離 | 670.30km |
| 気動車の数 | 1.253台 |
| 客車の数 | 269台 |
| バス台数 | 447台 |
| 座席数の総数 | 262.402 |
| 乗客数 | 965.900.000人 |
| 1日の乗客数 | 2.600.000人 |
| 路面電車の路線数と停留所の数 | 28路線 1.051 |
| 路線バスの路線数と停留所の数 | 129路線 4.230 |
ウィーンでワクチン接種をした人、申し込んでいる人は現時点で何人ぐらい?
5月2日でロックダウンが終わり、博物館なども開き始め、17日からは学校も毎日になり、19日からはカフェ、レストランも営業を再開し、コロナ禍でもだいぶウィーンの街の空気も普通に感じるようになりました。
3G・・・getestet(検査結果が陰性)、genesen(コロナから復活)、geimpft(ワクチン接種)である人がレストランやカフェ店内に座れ、街中では開放的な空気が少しずつ漂い、6月10日より規制も少し緩和され、6月24日より日本からの入国後の自己隔離措置が原則不要となっています。
さらに7月1日より規制が緩和され、昨日よりマスク着用義務がスーパー、薬局、銀行、郵便局、公共交通機関以外は無くなり、しかしその反面夜の飲み屋さんなどに入る場合は3Gの抗原検査陰性証明が外されました。
外を見ているとコロナ禍とは思えない状況となっています。
さて、現時点ではウィーンで実際どのくらいの人がワクチン接種をしているのでしょうか?
| ワクチン接種を申し込んでいる人 | 1.102.289人 |
| ワクチン接種を申し込んでいる企業数 | 443.880 |
| すでに接種された数 | 1.884.878 |
| ワクチンの種類 |
Pfizer/Biontech 1.316.632 AstraZeneca 318.137 Moderna 204.367 Johnson&Johnson 53.973 |
| 接種1回目 | 1.087.603 |
以下の統計は男女、年齢別に見たワクチン1回目の接種状況です。
薄い色は男性、濃い色は女性です。
50~59歳が一番多いですね。
若い世代も意外と多くの人が接種していて、10代も数万人が接種しています。


私はオーストリア政府が予防接種をしなければ仕事ができませんと決めない限りは、現時点で接種するつもりは全くありません。
変異ウィルスに対してもまだ効力があるかはわかりませんしね。
結局はインフルエンザのように共存していくようになると思います。
数字で見るウィーン市あれこれ 3
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
前回の数字で見るウィーン市あれこれ2 が好評を頂きましたので今日はその3です。
| 面積 |
415km² |
| 宅地面積 | 35.9% |
| 緑の比率 | 49.6% |
| 公共交通機関の面積 | 14.4% |
| 一番小さい区と一番大きい区 |
Josefstadt (8区)、Donaustadt (22区) |
| 緑の比率が最も少ない区と最も多い区 | Josefstadt (8区 1.9%)、Hietzing (13区 70.7%) |
| 一番高い住居建物、一番高い建築 |
DC Tower (250m)、 Donauturm (252m) |
| 一番標高が高い場所と低い場所 | Hermannskogel (543m)、Lobau (151m) |
| 一番低い地下鉄の駅 | U1 Altes Landgut (地下30m) |
| 一番長い通りと一番短い通り |
Höhenstraße (15km)、Irisgasse (17.5m) |
| 通り(道路)全体の長さ | 2.832km |
今回はウィーンの面積、緑の比率や標高が一番高い場所などを取り上げました。
この統計はウィーン市2019年の統計によるものです。
ウィーンは森の都と言われている通り、街の面積の半分が緑であることがわかります。
皆さんがよく聞くウィーンの森は、その豊かなウィーンの緑をもっと外側から囲んでいる大きな森です。
ウィーンは23区で分けられたかなり広い街ですね。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその4をまとめてみたいと思います。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その12
今日の朝5:00の気温はうちの周りでマイナス0.5℃・・・太陽は出そうですが寒い1日になりそうです。
外はまだ暗く街灯が灯されています。
さて、今日は1月も最後の日となりましたので、久しぶりにオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。
この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を、11月23日にはその11を掲載しました。

上の表は今年2月26日からの感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多く、9月からはさらに増加・・・11月になってからは急激に増加しています。
現在では3度目のロックダウン中で、1月17日の11:00に記者会見が行われ、オーストリア政府は3度目のロックダウンを延長することを発表し、25日よりスーパーや公共交通機関では普通のマスクではなく、FFP2マスク着用が義務付けられました。
現時点ではSemesterferienの終わり、つまり2月7日までということになっています。

左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。
11月と比べれば検査数がものすごく増えていますし、死亡者の数もかなり増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。
青が男性、黄色が女性です。

21.926の現在の感染者数、4.796の追加利用可能な病院ベット数、657の追加利用可能な集中治療のベット数、
20.203人の自宅での療養数、1.428のベットが利用中、295の集中治療室が利用中。
11月と比べれば数が全く違い、かなり少なくなっています。

上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。
84歳以上の死亡数が圧倒的に多く、男性の死亡率が遥かに高いですね。
右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。
割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでKärntenとなっていて、オーストリア全体での平均は85.8人です。
死亡者数はかなり増加しています。
死亡者が一番少ないのはKärntenですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。
軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

オーストリアでの自動車メーカー順位(2019年度)
今日のウィーンはこの冬一番の冷え込みとなりました。
うちの温度計では朝6:00の時点でマイナス7.7℃を表示していました。
車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。
ウィーンの街にも多くの車が走っています。
日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。
街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。
後から誕生した人間がこの地球に共存させてもらっていることと同じです。
オーストリアは世界的に見てかなりの車の保有率があり、ウィキペディアに掲載されている統計によれば19位となっていて、1.73人に1台の割合で車を所有しているようです。
ちなみに日本は17位、1.69人に1台の割合ですのでオーストリアとほとんど変わりません。
さて、今日はオーストリアにはどのメーカーの車がどれだけ走っているのかという2019年度の統計を紹介します。
| 順位 | 車メーカー | 台数 | 市場割合(%) |
| 1. | VOLKSWAGEN | 1.026.451 | 20.4 |
| 2. | Audi | 379.075 | 7.5 |
| 3. | BMW | 306.030 | 6.1 |
| 4. | Ford | 295.667 | 5.9 |
| 5. | Skoda | 294.068 | 5.8 |
| 6. | Opel | 292.238 | 5.8 |
| 7. | Mercedes | 274.973 | 5.5 |
| 8. | Renault | 210.415 | 4.2 |
| 9. | Seat | 202.868 | 4.0 |
| 10. | Peugeot | 186.760 | 3.7 |
| 11. | TOYOTA | 160.713 | 3.2 |
| 12. | Mazda | 155.740 | 3.1 |
| 13. | Fiat | 153.422 | 3.0 |
| 14. | Hyndai | 143.320 | 2.8 |
| 15. | Citroen | 123.608 | 2.5 |
| 16. | Kia | 107.386 | 2.1 |
| 17. | Suzuki | 106.386 | 2.1 |
| 18. | Nissan | 84.015 | 1.7 |
| 19. | Dacia | 76.408 | 1.5 |
| 20. | Volvo | 63.956 |
1.3 |
| 21. | Mitsubishi | 54.167 |
1.1 |
| 22. | Honda | 42.739 |
0.8 |
上の表はStatistik Austriaからの引用です。
オーストリア全土で2019年にどのメーカーの車がどれだけ走っているかとそのシェア率を示しています。
1位は圧倒的にVolkswagenで全体の20.4%を占めています。
5台に1台はVWですから非常に人気があります。
私も2011年の3月まではVWに乗ってました。
今はもちろん日本車に乗ってます。(笑)
Audi、BMW、Fordと続き、日本車ではTOYOTAがトップで11位、3.2%のシェア率、次いでMazdaが12位です。
この統計は新車認可数ではなく、現在国に登録されて走っている車ですから、新車から20年前やそれ以前の車も含まれます。
非常に興味深い統計です。
クリスマスプレゼントの傾向(2020年)
今日のウィーンは朝7:00で3.5℃、日中も5℃ぐらいで、しかも雨マークが見られ、太陽がすがたを見せないどんよりとした1日になりそうです。
ここ数日はずっと空はグレーですね。
クリスマスがどんどん近づいて来ていますね。
今年は11月3日以降の再ロックダウンが12月6日まで続き、クリスマス市も中止となる異例のAdvent時期となりました。
それでも一昨日ADVENTKRANZに2本目のロウソクを多くの人が灯したはずですし、ニコロの習慣もきっと各家庭で楽しまれたはずです。
12月7日より、再ロックダウンの規制が少し緩和されたことにより、商店も感染対策をしっかりした上で営業を再開しています。
クリスマス市は中止になっても、クリスマスプレゼントが無いクリスマスはあり得ない・・・やはりこれからクリスマスプレゼントを買う人が多くなるはずです。
ちなみにKMU Forschung Austriaによればこの再ロックダウンでの地元商業の損失はウィーンだけでも300.000.000ユーロということですから相当なものです。
多くの人は家族とクリスマスを過ごします。
そのため、それぞれにクリスマスプレゼントを渡すので買い物も大変です。
さて、今日はウィーンではクリスマスプレゼントに何を贈るかという傾向を見てみましょう。
右の表は今年2020年度のクリスマスに何を贈るか・・・という統計で、オーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年12月3日号に掲載されていたものです。
本が一番多く、おもちゃ、商品券がベスト3となっています。アルコールやタバコが好きな人にとっては、クリスマスプレゼントとしてもらうのは嬉しいのでしょうか。
クリスマスは年間を通して一番重要ではありますが、誕生日ではないのでプレゼントは高価な物ではなくても、気の利いた物がよしとされていることからも納得できます。
実際には一人に買うわけではなく、複数のプレゼントを用意するわけですから、金銭的にも1人だけにそう多くはかけられません。
| 本 | 43% |
| おもちゃ | 35% |
| 商品券 | 33% |
| 衣料品 | 32% |
| 香水、化粧品 | 23% |
| 嗜好品(酒、コーヒー、タバコなど) | 16% |
| 現金 | 16% |
ここでちょっと私の過去の経験をお話しします。
当時付き合っていた彼女にクリスマスプレゼントをどうしようかと考えていました。
彼女は当時、新車に乗っていてスノータイヤが必要になっていたんです。
タイヤまとめて4つは結構高いので出費がかさむな~と嘆いていたのを見て、そうだ、スノータイヤをクリスマスプレゼントにすればいい、これはいいアイデアだと自信を持って提案しました。
(本来クリスマスプレゼントは相手に内緒で用意しますが、この場合は状況的に先に提案しました)
彼女の反応はとっても驚いて、同時に呆れたようにスノータイヤをクリスマスプレゼントにするなんて、何ロマンのないこと言ってるのと、半ば怒られて「Sicher, nicht!」とハッキリ断られました。
自分は役に立つものだし金銭的に助かるだろうと思ったんですけどね・・・。
まぁ、確かにクリスマスプレゼントがスノータイヤなんて夢が無さすぎますね。(笑)
この統計ではウィーンの85%の人がクリスマスプレゼントを買い、1人の平均支出額は320ユーロとなっています。
今年は新型コロナウィルスの影響で予算も去年と比べたら少ないということです。
どうしてクリスマスプレゼントを買うかということについては
70%が相手を幸せにさせることが、自分の喜びであると答え、
伝統であると答えた人は36%、
相手も自分にプレゼントしてくれるからと答えた人は17%でした。
こちらではクリスマスプレゼントを持って来るのは、Christkind(クリストキント)・・・子供のキリストで、サンタクロースではありません!
電気自動車の普及率(2020年9月時点)
ウィーンはヨーロッパの街では車の所持率がかなり高いと言われています。
街中を歩けば至る所に路上駐車が見られます。
お客様からも「ものすごい路駐の状況ですね」とか「こちらは路駐が許可されているのですか」という質問がよくあります。
ウィーンの生活に慣れてしまうと当たり前ですが、日本で路駐をすればすぐにレッカー移動でしょう。
街の歴史がずっと古いので、後から来た車が共存させてもらっている・・・という感じです。
ここ数年ぐらいから電気自動車が普及し始めています。
街中の一角やスーパーの駐車場など知らないうちに充電スタンドが設置されていますね。
2017年5月16日付で電気自動車は普及するか?というタイトルで電気自動車の導入や主要自動車メーカーの電気自動車の種類と価格を、2019年7月11日には電気自動車の普及率を紹介しました。
その後オーストリアでの電気自動車はどうなっているでしょうか?

こちらはオーストリアの連邦産業院(WKO)が発行する経済新聞 "Wiener Wirtschaft"
2020年9月3日号に掲載されていたもので、情報源はStatistik
Austriaからです。
左の統計はすでに登録済みの電気自動車数です。
2016年以降毎年増加していて、今年はすでに35.077台が走っています。
右の統計は新車認可数で今年はすでに5869台認可されています。
電気自動車を購入するにあたってオーストリア政府からの補助金が今年7月1日より5.000ユーロとなりました。
3年前は一時的に4.000ユーロでしたが、その後は3.000ユーロの補助でした。
これも条件が良くなっています。
地球にやさしい環境を作り出すためにオーストリアは積極的に取り組んでいます。
今後はディーゼル、ガソリン車の数がどんどん減少して、電気自動車に移行せざるを得ない環境になっていく傾向にあります。
うちもいずれ電気自動車になりそうです。
コロナ禍・・・冬の休暇をどう思うか
今日から12月です。
早いもので今年も残す所、あと1ヶ月となりました。
今日の朝の気温は6:30の時点でマイナス1.3℃でした。
こちらの学校は前期と後期の2学期で、Semester(セメスター)と呼ばれています。
9月から新年度が始まり、7月、8月はFerien(フェーリエン)と言われる大きな夏休みで、社会ではUrlaub(ウアラウプ)・・・休暇という表現が多く使われます。
学校では夏休みの他にはOsterferien(復活祭休み)、Semesterferien(学期休み)、Herbstferien(秋休み)、Weihnachtsferien(クリスマス休み)などの短い休みがあり、親御さんなどは学校の休みに合わせて、休暇を取ることが多いです。
特にWeihnachtsferienはクリスマスから1月6日ぐらいまでの2週間あり、その時期には毎年多くの人が休暇に出かけます。
冬ですからやっぱりスキー休暇が多いでしょうか。
オーストリアは御存知の通りスキー王国ですから、スキーは国民的スポーツとなっています。
雄大なアルプスの大自然の中を滑る楽しさは経験した人でないと分かりません。
さて、そんな冬の休暇は今年はコロナ禍で地元での意識はどうでしょうか?
| Winterurlaubを計画しているか? |
計画している32% 計画していない68% |
| どこで冬休暇を過ごす? |
オーストリア90% イタリア5% ドイツ4% スイス2% |
| なぜ冬休暇に行かない? |
コロナ不安52% 冬休暇は好きではない31% 金銭的問題25% 家庭の事情10% |
| 冬休暇のスタイルは? |
スキー51% SPA38% 知り合い訪問20% 市内観光15% 南の暖かい所4% 体験旅行4% クルーズ1% |
| コロナに感染する恐れがある場所は |
Après-Ski66% リフトやゴンドラに並んでいる時31% ゴンドラの中30% Wellnes領域15% レストラン11% ホテル9% リフト上6% ショップ3% ゲレンデ2% |
上の統計はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年11月19日号に掲載されていたものです。
冬休暇を計画しいない人は約70%で、オーストリアが再ロックダウンに入ったことも理由のひとつでしょう。
冬休暇をする場合は90%がオーストリア国内で、それ以外は隣接国です。
半数がスキー休暇ですが、実際にスキー場がオープンするのかどうかも分かりません。
たった30%の人が冬休暇をプランしていて、中でも実際に予約した人は非常に少ないということです。
5泊、1人481ユーロの支出が平均となっているようですが、冬休暇を検討中の2/3は様子を見ている状態で、休暇開始の2週間前から最終決定するということです。
統計を見ている限りでは、休暇をプランしていても、コロナに対する不安はあるようですね。
やはり寒くなってきたと同時に感染者数も増加してきました。
冬休暇は行かない方が賢いでしょうか。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その11
今日の朝6:00の気温はうちの周りで0.8℃・・・昨日よりは4℃ほど高いですね。
外はまだ暗く街灯が灯されています。
日本ではGo Toトラベル、イートの見直しが話題になっていますが、多くの人が色々な所に出向いているので感染者数がかなり増加していますね。
こちらと比べれば数は違っていても、同じような傾向を辿っています。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計をまとめてみます。
この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を、10月1日にはその10を掲載しました。

上の表は今年2月26日からの感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多く、9月からはさらに増加・・・11月になってからは急激に増加しています。現在では再ロックダウン中で外出規制が強化されています。

左から・・・
検査数、確定症例、治癒数、死亡数、現時点での発病数です。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布の統計、右は100.000人に対しての統計です。
青が男性、黄色が女性です。

119.359の現在の感染者数、3.532の追加利用可能な病院ベット数、504の追加利用可能な集中治療のベット数、
114.762人の自宅での療養数、3.900のベットが利用中、697の集中治療室が利用中。
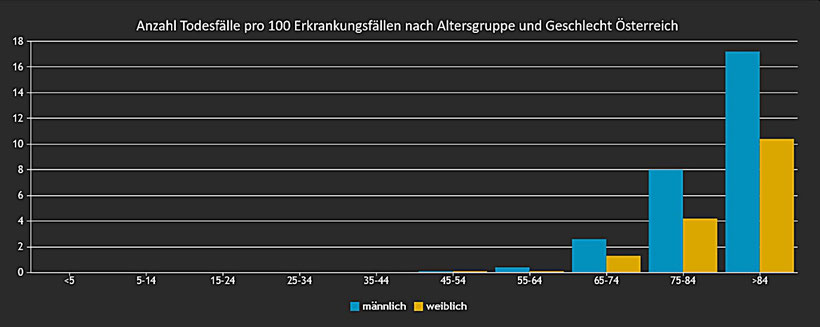
上の表は発病数100人に対しての年齢別死亡数で、青が男性、黄色が女性です。
84歳以上の死亡数が圧倒的に多いです。
右の表はオーストリア州別の統計で、100.000人に対しての死亡数となっています。
割合的に死亡者数が一番多いのはSteiermark、次いでTirolとなっていて、オーストリア全体での平均は24.7人です。
死亡者が一番少ないのはKärntenですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大はある程度抑えられると思います。
軽率な行動をとる人が多くなっていることも増加に拍車をかけているでしょうか。

コロナ禍で買い物スタイルがどう変わった?
オーストリアでは2020年3月16日から"Corona-Krise"と称して様々な給付金、補助金などを始め、様々なサポートを受ける目安の日となっています。
最初のロックダウンを経験し、試行錯誤的に規制が一部解除されたり、また厳しくなったりと・・・そして11月3日より再ロックダウン・・・明日から規制がもっと強化されます。
日本でもテレワークという言葉も頻繁に登場し、自宅で勤務する人も多くなっています。
こちらでも同様に仕事場所が自宅になったという人は非常に多くなっています。
一時的ではあると思いますが、このコロナ過中、ライフスタイルは大きく変わりました。
さて、今日はそのコロナ禍での買い物がどう変わったか、地元での意識を見てみましょう。
コロナ流行に対しての評価
●コロナ感染拡大を抑えることに貢献できるのであれば一時的にもいくつかのことを諦められる
10月70% 3月終り95%
●オーストリア政府は新型コロナウィルスに対して正しく対応している
10月55% 3月終り90%
●自分、もしくは家族の誰かがコロナに感染する不安がある
10月45% 4月始め74%
●新型コロナウィルスの危険性に関して大げさだと思う
10月40% 3月始め53%
コロナ危機が始まった頃の方が、人々は慎重に考えていたことがわかります。
特に感染する不安がある人が今は45%、逆に半数以上の人が不安がないと思っているわけですから、マスク無しで公共交通機関を利用したりとか、スーパーに入ってきたりとかするわけです。
自分も振り返ればそのような人々を見かけた時に数回ぐらい注意をしたことがあります。
そのような人々は無責任極まりないです。
買い物スタイルがどう変わったか?
●自分が住んでいる地域から生産されたものをより多く買う 75% (女性80%、男性70%)
●オーストリア産の物をより多く買う 70% (女性74%、男性66%)
●18:00までの営業時間でも満足できる 68%(16歳~30歳までは53%が満足)
スーパーでの買い物は?
快適である 7%
まあ、そこそこ 33%
コロナ以前よりも快適ではない 58%
ノーコメント 2%
●なぜ快適ではないか?
マスクが邪魔 65%
以前よりストレスを感じる 40%
コロナに感染するかもしれない不安 30%
これらの統計はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年11月12日号に掲載されていたものです。
今でも続くコロナ過を振り返って自分も理解できることがたくさんあります。
とにかく、個人個人責任を持ってしっかり意識しながら行動するべきであり、それが結果的に自分を守るだけでなく、家族や他人を守ることになるわけですからね。
日本も感染者数が増加していますが、必ず終わりは来るので希望を捨てず乗り切りましょう。
子供1人に対しての遊び場の面積
ウィーンは"森の都"と言われているぐらい緑が多い街で、街の至る所に緑が見られます。
中心のリンク道路の並木やたくさんの公園を始め、外側にもシェーンブルン宮殿やプラター公園などの大きな緑・・・そしてその豊かな緑を囲むもっと大きな緑がウィーンの森です。
ウィーンの街を歩けば、この街は緑豊かだなということがすぐにわかります。
公園には遊び場が設置されていることが多く、ウィーンには1.720以上の子供の遊び場、サッカー、バスケットボールや卓球などのスポーツが楽しめるスペース、スケーボードスペース、水の遊び場などがあります。
今日はウィーンの子供1人に対してどのくらいの面積の遊び場が割り当てられいることになるかを見てみましょう。
| 2区 | 9 ㎡ 以上 |
| 13、22区 | 5~9 ㎡ |
| 6、10、18、19、21、23区 | 3~5 ㎡ |
| 1、3、4、5、7、8、9、11、12、14、15、20区 | 2~3 ㎡ |
| 16、17区 | 2㎡ 以下 |
上の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at の2019年9月号に掲載されていたデータで、子供1人当たりの遊び場の広さです。
ウィーンは190万弱の人口があり、子供の数は96.330人で、そのうち6歳以下の子供が94%を占めています。
ウィーン23区では2区が最も子供一人当たりに対しての遊び場の広さがありますね。
もっともこの区はプラター公園がありますから納得できます。
中心部には遊び場などありそうもないですが、いえいえリンクの内側にだってちゃんとあります。
区によっての差はありますが、ウィーンでは15歳以下の子供1人に対して平均3.57㎡の遊び場が割り当てられているということになります。
オーストリアでのディーゼル車とガソリン車の割合(2019年度)
ウィーンは公共交通機関が非常に発達しているので、ウィーンに住んでいる限り車が無くても不便さは感じないでしょうか。
にもかかわらずウィーンは車の所持率がかなり高い街と言われています。
ウィーンは415km²とかなり広い街ですから、実際には車があれば便利ですし、ウィーンの郊外にも魅力的な場所が多くあり、何と言ってもオーストリアはアルプスを大きく横たえて持っている国で、郊外に美しい長閑な風景が広がっていますので、車はある意味では必需品とも言えます。
最近は電気自動車の割合も多くなってきました。
オーストリアではディーゼル車やガソリン車など、どのくらいの割合なのかを見てみましょう。
| PKW (一般乗用車) | 割合 | |
| 全登録台数 | 5.039.548 | 72% |
| ディーゼル車 | 2.772.854 | 55% |
| ガソリン車 | 2.179.235 | 43.2% |
| 電気自動車 | 29.523 | 0.6% |
| 天然ガス車 | 2.602 | 0.1% |
| 液体ガス車 | 2 | 0% |
| ガソリンと天然ガス | 3.144 | 0.1% |
| ガソリンと液体ガス | 330 | 0% |
| ハイブリッドガソリン | 45.645 | 0.9% |
| ハイブリッドディーゼル | 6.172 | 0.1% |
| 水素自動車 | 41 | 9% |
上の統計はStatistik Austriaからのもので2019年度のまとめです。
対象はPKW (Personenkraftwagen)・・・いわゆる一般乗用車です。
全登録台数72%とはオーストリアにおいての"車両"全体の割合です。
以前よりも少なくなりましたが全体の55%がディーゼル車で半数以上を占めています。
ガソリン車は43.2%ですね。
電気自動車はまだ0.6%ですが、今後はもっと普及してくるでしょう。
ディーゼルの燃費がいいこともあり、ハイブリッド車は思ったほど普及しなかったようです。
環境問題を考えて自動車税も高くなり、徐々に規制もされていくと思うので今後は状況も変わって行くことになるでしょう。
オーストリア コロナ禍での宿泊数大激減
秋の深まりを感じるウィーンです。
この時期はまだ夏時間ということもありますが、朝7:00ちょっと前ぐらいから空が白んできます。
日がどんど短くなっていますね。
さて、今日はオーストリアでは新型コロナウィルス感染拡大の影響で、宿泊数が前年度と比べてどのくらい激減したかをまとめてみます。
オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日でした。
生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。
イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。
6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。
EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れましたが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。
(現時点では9月28日より日本からオーストリアへの入国が可能です)コロナ禍の9月7日から信号機システムを伴って学校も始まり、何となく通常の生活が始まっていますが、最近はまた感染者数が増加傾向にあり、再ロックダウンのうわさが流れています。
そんな状況の中で、オーストリアへ観光や商業などの目的で入国する人が激減し、去年と比べると宿泊数が大激減しています。
右の表はオーストリアの経済情報新聞Wiener Wirtschaft2020年10月8日号に掲載されていたもので、
コロナ危機期間2020年3月~8月までの宿泊数状況をまとめたものです。
ウィーンは前年度と比べると-83%、ザルツブルクは-72.5%と宿泊数が大激減しています。
オーストリア全体では-77.5%となっています。
Klagenfurtは-49.2%と他と比べると減少率が少ないのは、今年の夏の休暇シーズンに国境超えを避けて、地元オーストリアで休暇を楽しんだ人が多かったことなどが考えられます。
オーストリアは観光立国的なイメージがありますが様々な産業があり、観光業が全てではありません。
しかし、観光業はもちろん大きな収入のひとつになっているため、非常に厳しいシーズンとなっています。
| 州都 | 2019年度との比較 |
| Wien |
-83.0% |
| Salzburg |
-72.5% |
| Innsbruck |
-71.5% |
| Graz |
-63.6% |
| Linz |
-68.4% |
| Klagenfurt |
-49.2% |
| Bregenz |
-53.4% |
| St.Pölten |
-60.3% |
| Eisenstadt |
-75.3% |
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その10
早いもので今日から10月です。
ウィーンはどんどん秋らしくなっていきます。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日10月1日 朝6:00時点での統計を紹介します。
この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を、8月31日のその9を掲載しました。

上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多く、9月からはさらに増加しています。
第2波でしょうね。
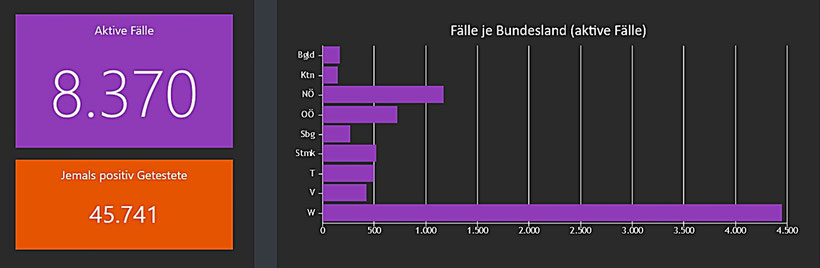
8.370人が発病、45.741人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
8月31日に掲載した統計では3.363人が発病していましたが、クロアチアなどのバルカン方面へ休暇に出かけた人などが感染したようで増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
15-24歳が一番多く、次いで25-34歳、若い人が多く感染しているようです。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が52%、女性が48%です。

1.617.987の検査数、7.221の通常の病院ベットの空き数、640の集中治療室の空き数、406のベットが利用中、90の集中治療室が利用中、7.874人が自宅での療養数。

35.644人が再び健康に、799人の死亡報告、779人が実際に死亡が確認、死亡者数の割合は男性が57%、女性が43%です。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで248名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

数字で見るウィーン市あれこれ 2
ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
前回の数字で見るウィーン市あれこれが好評を頂きましたので今日はその続編です。
| 2008年~2018年の人口増加率 | 13% (ミュンヘン11%、ブダペスト2.8%) |
| 初婚の平均年齢 | 男性32歳 女性30歳 |
| 最初の子供が生まれる平均年齢 | 29.9歳 (1987年は25.4歳) |
| 双子以上が生まれる割合 | 3.1% |
| 人気ある名前 |
男性 Maxmilian,Alexaner,David 女性 Sophia,Sara,Anna |
| 人口密度 | 1ヘクタール(100m x 100m) 46人 |
| 人口密度が一番多い区と一番少ない区 |
5区(257.4人/1ha)、 13区(14.3人/1ha) |
| 住居に利用されている土地面積の割合 | ウィーン全体 25.4% (2区14.5%、8区60.9%) |
| 1人当たりの平均居住空間面積 | 35m² |
| 1世帯の平均居住者数 | 2.07人 |
この統計はウィーン市2019年の統計によるものです。
人口密度が一番多いのはウィーン5区、少ないのは13区ですね。
また住居に利用されている土地面積が2区が一番少ないですが、これはプラター公園という大きな緑が存在しているからでしょう。
ウィーンは23区で分けられた広い街です。
全人口1.897.491人のうちで約70%が地元オーストリア人、約30%が外国人ということになります。
国籍数も180と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいます。
国際色豊かな街です。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いのでまた近いうちにその3をまとめてみたいと思います。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その9
早いもので8月も今日で最後となりました。
何となく秋の訪れを感じるウィーンです。
一昨日から雲が多く、風も強く雷を伴った強い雨が局地的に降っています。
昨日の夜も非常に強い雨が降り、雹も降って来ました。
これを書いている現在、雨は降っていませんが非常に風が強く夏の終楽章を飾るような天気です。
今年は8月30日が日曜日なのでその翌週も休暇となり、学校は9月7日から始まります。
現時点では感染対策を施しながら通常通りということになっています。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月31日 朝6:00時点での統計を紹介します。
この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を、8月23日にその8を掲載しました。

上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向で、特に8月は休暇に出かけた人が多いためさらに増加しています。

3.363人が発病、27.219人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
8月23日に掲載した統計では2.924人が発病していましたが、クロアチアなどのバルカン方面へ休暇に出かけた人などが感染したようで増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
45-54歳が一番多く、次いで25-34歳、若い人も多く感染しているようです。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が51%、女性が49%です。

1.172.092の検査数、8.176の通常の病院ベットの空き数、741の集中治療室の空き数、110のベットが利用中、30の集中治療室が利用中、3.223人が自宅での療養数。

23.070人が再び健康に、733人の死亡報告、726人が実際に死亡が確認、死亡者数の割合は男性が57%、女性が43%です。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで219名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

数字で見るウィーン市あれこれ
日中の気温が25℃前後と気持ちのいい8月後半です。
夏なのですが、しかし自然を見ていると秋の訪れを少しずつ感じます。
日もだいぶ短くなってきていますね。
さて、ウィーンの街は今でもかつての帝国の都であった面影を残し、荘厳な建造物が建ち並ぶ、緑豊かな洗練された美しい街です
それもハプスブルグ家というヨーロッパで一番長く続いた王朝の居城がこの街にあり、そしてそのハプスブルグ家の下にかなりにわたって神聖ローマ帝国の皇帝やローマ王の称号が置かれていたことで、様々な人たちがこの帝国の都に集まって来ました。
そこでウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したとても奥深い街となったわけです。
ウィーンは様々な角度から楽しめる街です。
だいぶ前にウィーン市の概要やウィーンは意外と広いこと、ウィーン市の人口統計などを紹介していますが、ここでまたウィーン市についてのデータを少しまとめてみます。
| 人口 (2020年1月1日現在) | 1.911.191人 |
| 男女の割合 | 男性48.7% 女性51.3% |
| ここ10年の人口増加率 | 217.356人の増加 (+12.9%) |
| 出生と死亡 (2019年) | 出生20.038人 死亡16.887人 |
| 平均寿命 | 男性78.4歳 女性82.9歳 |
| 国籍 | オーストリア国籍69.8% |
| 外国人 | EU 国籍13.1% EU以外17.1% 180ヵ国の国籍数 |
| ウィーンに移民した数 | 88.535人 |
| ウィーンから出て行った数 | 82.856人 |
| 移民国籍ベスト3 | シリア+23.337人 ルーマニア+18.550人 ドイツ+17.669人 |
この統計はウィーン市2019年の統計によるものです。
ウィーンは23区で分けられたかなり広い街です。
全人口1.897.491人のうちで約70%が地元オーストリア人、約30%が外国人ということになります。
国籍数も180と世界各国からの人がウィーンに移り住んでいます。
ウィーンは国連都市があることも大きいですが、ハプスブルグ帝国時代からもともと多民族国家でしたので、その流れが受け継がれていると言えるでしょう。
このようなデータを改めて見ると非常に興味深いので、シリーズにしてまとめてみようと思います。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その8
もう何回も書いていますが今年のウィーンは6月13日に日中の気温が初めて30℃を越え、6月は合計3日、7月は30℃を越えた日が合計で8日ありました。
7月28日が今年で一番暑く日中35℃を越えた猛暑日となり、その週は8月2日までは毎日30℃を越えた真夏日となりました。
8月3日から気温がぐっと下がり、日中20℃前後と雨の多い、どんよりした天気となりました。
夜は14℃と物凄く涼しくなりましたが、その後日中30℃を越える日が多くあり、昨日までで8月は30℃を越えた日が10日となっています。
昨日のウィーンは午後から暗くなり始め、雷を伴った強い雨が降りました。
今日から気温が下がっています。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月23日 朝6:00時点での統計を紹介します。
この統計は5月2日が最初で6月6日には新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を、8月14日にその7を紹介しました。

上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向です。

2.924人が発病、25.099人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
8月14日に掲載した統計では1.523人が発病していましたが、クロアチアなどのバルカン方面へ休暇に出かけた人などが感染したようで増加しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が51%、女性が49%です。

1.087.155の検査数、7.758の通常の病院ベットの空き数、734の集中治療室の空き数、94のベットが利用中、22の集中治療室が利用中、2.808人が自宅での療養数。

21.406人が再び健康に、732人の死亡報告、725人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで218名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その7
ここ数日間日中30℃を越える暑い日が続いていましたが、昨日から天気が崩れ始めオーストリア各地で雷を伴った雨が降り始めました。
今日から天気予報の予報では気温が26℃~28℃、雨マークが多く登場しています。
さて、オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。
生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。
イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。
6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を、7月20日にはその5を、8月3日にはその6を紹介しました。
6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは以下の特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。
・食品小売店の敷地内(食品生産者の直売所及び食品販売店併設ガソリンスタンドを含む。)
・銀行
・郵便局
・老人ホーム、病院、保養所、医療・介護サービスの来館者エリア
EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れるということですが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。
現時点でのオーストリアへの入国に関してはこちらを参照して下さい。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月14日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向です。

1.523人が発病、22.766人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
8月3日に掲載した統計では1.602人が発病していましたが減少しています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

991.508の検査数、7.437の通常の病院ベットの空き数、746の集中治療室の空き数、92のベットが利用中、22の集中治療室が利用中、1.409人が自宅での療養数。

20.346人が再び健康に、725人の死亡報告、713人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで211名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。
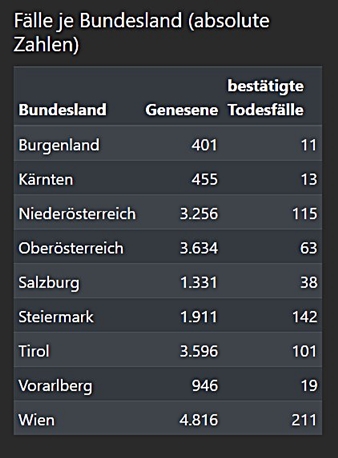
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その6
オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。
生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。
イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。
6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を紹介しました。
6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは以下の特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。
・食品小売店の敷地内(食品生産者の直売所及び食品販売店併設ガソリンスタンドを含む。)
・銀行
・郵便局
・老人ホーム、病院、保養所、医療・介護サービスの来館者エリア
EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れるということですが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。
現時点でのオーストリアへの入国に関してはこちらを参照して下さい。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日8月3日 朝6:00時点での統計を紹介します。
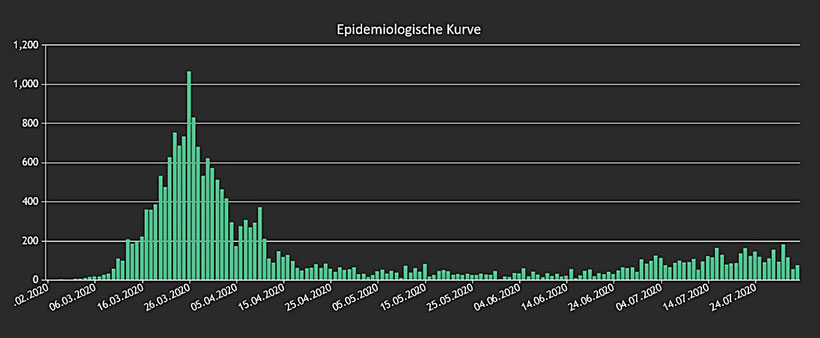
上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向です。
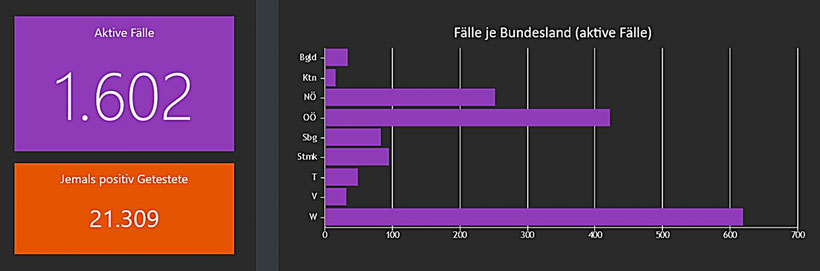
1.602人が発病、21.309人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
7月20日に掲載した統計では1.345人が発病していましたが増えていますね。
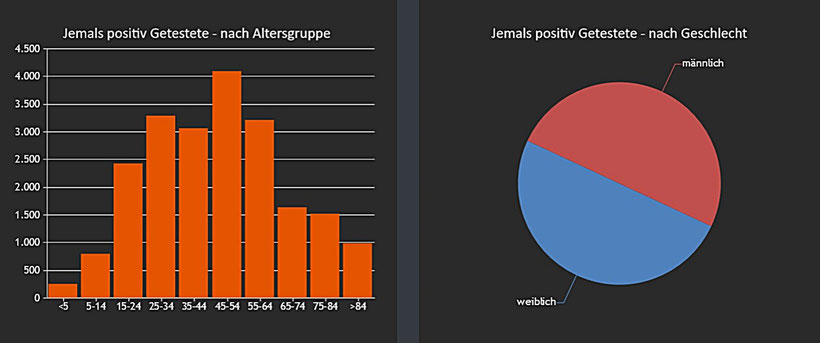
左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

905.314の検査数、8.594の通常の病院ベットの空き数、742の集中治療室の空き数、73のベットが利用中、20の集中治療室が利用中、1.509人が自宅での療養数。

18.984人が再び健康に、718人の死亡報告、698人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで210名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから少しの増加傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

オーストリア 新型コロナウィルスに対する支援の途中経過
オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。
生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。
イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。
6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を紹介しました。
6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつありますが・・・7月24日(金)からは以下の特定場所においてマスク着用義務が再導入されています。
・食品小売店の敷地内(食品生産者の直売所及び食品販売店併設ガソリンスタンドを含む。)
・銀行
・郵便局
・老人ホーム、病院、保養所、医療・介護サービスの来館者エリア
日本は顕著ですが、こちらでも少しずつですが感染者が増加傾向を示しています。
オーストリアではこの新型コロナウィルスに対して国からの様々な補助がそれなりに迅速に対応されていると感じていますが、現時点では大幅に支払いがされてないようです。
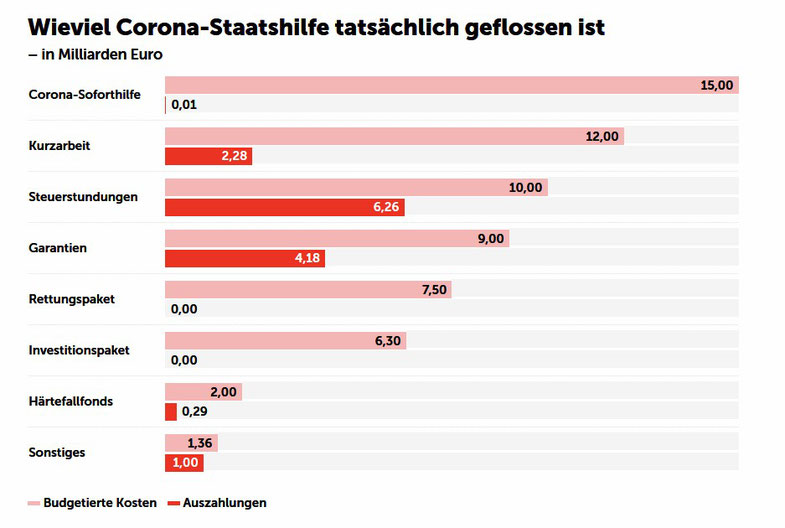
上の統計はAgenda Austriaに掲載されていたオーストリア財務省からの報告をベースにまとめたものです。
薄いピンクのグラフはオーストリア政府が決めた新型コロナウィルス補助金の予算で、Milliarden(億)が単位になっています。
その下の赤いグラフは実際に支払いされた割合ということになっています。
例えば私も該当するHärtefallfonds(災害基金)は2億ユーロ (約2.570億円)の予算枠になっていますが、実際は14.5%ぐらいしか支払われていません。
Kurzarbeit(短時間労働)やSteuerstundungen(税金猶予)などは支払われていますが、それでも予算枠がまだまだ多くなっていますね。
オーストリア政府が定めたガイドラインに沿わないことが非常に多いようで、認められない中小企業、個人事業主が結構あるようです。
個人的にはもっと多くの支払いがされていたと思っていたので、この中間統計は意外でした。
今後どうなるか注目したい所ですね。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その5
オーストリアでは3月16日からがコロナ危機期間の始まりの日です。
生活に必要最低限の所しか営業せず、後は全部クローズを余儀なくされました。
イースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となり、21日からスペインに対しても解除されました。
6月6日にはオーストリア政府からの新型ウィルスに関しての統計その2を、6月17日には新型ウィルスに関しての統計その3を、7月5日にはその4を紹介しました。
6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつあります。
EUとしては7月1日以降、日本やカナダ、オーストラリアなどの15ヵ国からの入国を受け入れるということですが、これはあくまでも"勧告"なので強制力はないため、オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されています。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日7月20日 朝6:00時点での統計を紹介します。
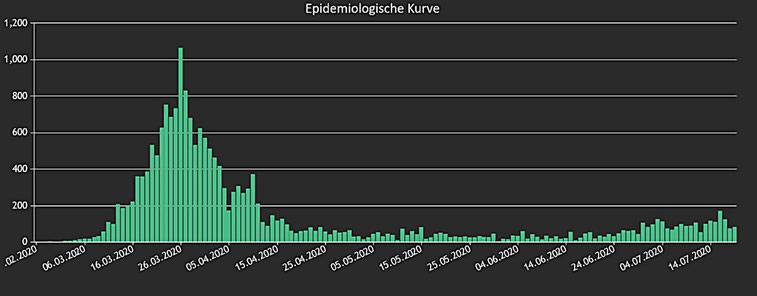
上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向にあります。
正直こうなることは予想がつきました。

1.345人が発病、19.642人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
7月5日に掲載した統計では853人が発病していましたが増えていますね。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

748.669の検査数、8.273の通常の病院ベットの空き数、775の集中治療室の空き数、85のベットが利用中、14の集中治療室が利用中、1.246人が自宅での療養数。

17.599人が再び健康に、711人の死亡報告、685人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで199名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから第2波が来るような傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

Home-Officeをどう思う?
オーストリアでは2020年3月16日から"Corona-Krise"と称して様々な給付金、補助金などを始め、様々なサポートを受ける目安の日となっています。
日本でもテレワークという言葉も頻繁に登場し、自宅で勤務する人も多くなっています。
こちらでも同様に仕事場所が自宅になったという人は非常に多くなっています。
実際には様々な職種があるため、自宅でも問題なくこなせる、効率が上がる、今までの仕事経験の中で一番いい時期という意見もあれば、逆に仕事にならない、効率が悪い、仕事とプライベートは切り離したいという意見もありかなり分かれていますね。
今日はその辺にちょっと焦点を当ててみましょう。
自宅で仕事するのは?
| 仕事とプライベートをしっかり分けられる | 49% |
| 総合で見るとより仕事が多い | 42% |
|
自宅ではより多くの仕事ができる |
41% |
| 自宅だと休憩が稀になった | 35% |
| 総合で見ると仕事時間が少なくなった | 16% |
| 集中するのが難しい | 12% |
| その他 | 9% |
自宅での仕事はどこで?
| 自分の書斎 | 43% |
| 居間 | 33% |
|
キッチンテーブル |
9% |
| 寝室 | 8% |
| その他 | 7% |
チームとしてうまく行くか?
| 今後もうまく行く Ja 92% Nein 8% |
| 目的がハッキリする Ja 82% Nein 18% |
| チームの雰囲気がいい Ja 82% Nein 18% |
| 団結力が生まれた Ja 60% Nein 40% |
| 仕事に制限がある Ja 45% Nein 57% |
ミィーティングはうまく行く?
| 明らかに効率がいい 44% |
| 変わらない 42% |
| 明らかに効率が悪い 14% |
こちらのデータはオーストリアの連邦産業院(WKO)が発行する経済新聞 "Wiener Wirtschaft" 2020年7月2日号に掲載されていたものです。
該当している人の意見は様々です。
色々な職種がありますから、より仕事の効率が上がって仕事環境が良くなった人もいれば、現場でないと仕事にならないという人も多いでしょう。
日本も同じような傾向ではないかと思います。
新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その4
6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となりました。
6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、7月1日より飲食店の営業規制も緩和され普通の生活に戻りつつあります。
オーストリア政府は日本を含む第三国からのオーストリアへの入国規制を残念ながら継続することが7月1日に発表されました。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日7月5日 朝6:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい状況でしたが7月1日以降また増加傾向にあります。
正直こうなることは予想がつきました。

853人が発病、18.186人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
6月17日に掲載した統計では419人が発病していましたが、倍以上に増えています。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が50%、女性が50%です。

642.679の検査数、7.622の通常の病院ベットの空き数、694の集中治療室の空き数、60のベットが利用中、8の集中治療室が利用中、785人が自宅での療養数。

16.607人が再び健康に、705人の死亡報告、681人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで196名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が緩和された後から再び1日の感染者数が増加傾向になってきました。
もう大丈夫だろうと軽率な行動をする人が多くなってきていることから第2波が来るような傾向となっています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その3
オーストリアではイースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
また6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表され、6月16日以降は特定の31か国(以下特定国一覧参照)からの入国制限の解除となりました。
今週6月15日(月)からマスク着用義務が緩和されていて、通常の生活スタイルに戻りつつあります。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日6月17日 朝5:00時点での統計を紹介します。

上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい的です。
残念ながらまだゼロではありません。

419人が発病、17.106人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
5月2日に掲載した統計では1850人が発病してましたから1431人も少なくなっています。
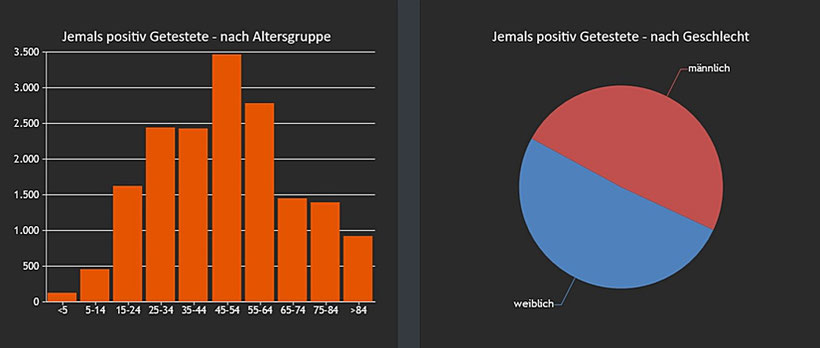
左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が49%、女性が51%です。

532.700の検査数、9.834の通常の病院ベットの空き数、833の集中治療室の空き数、66のベットが利用中、12の集中治療室が利用中、341人が自宅での療養数。

16.089人が再び健康に、681人の死亡報告、660人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が56%、女性が44%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで184名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が大きく緩和され、数字だけ見ていると終息に向かっているように思いますが、ここで油断してしまうと第2波がやって来る可能性が強いことを多くの人が意識しています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計 その2
オーストリアではイースター明けの4月14日から400平米までの小規模店舗,ホームセンター及び園芸用品店の営業が許可され、5月1日からは全ての店舗,ショッピングセンター,理髪店の営業も再開、そして5月15日からはレストラン、カフェも再開し、シェーンブルン宮殿や王宮もオープンしてい、5月29日からホテルも営業も再開、30日から美術史博物館もオープンしています。
ガイド業務としては5月1日より可能となっておりましたが、5月29日より団体ツアーの皆様にも御案内することができるようになっております。
また6月4日より隣国からの入国時の検査及び自己隔離措置をイタリアを除き以降停止することも発表されました。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日6月6日 朝5:00時点での統計を紹介します。
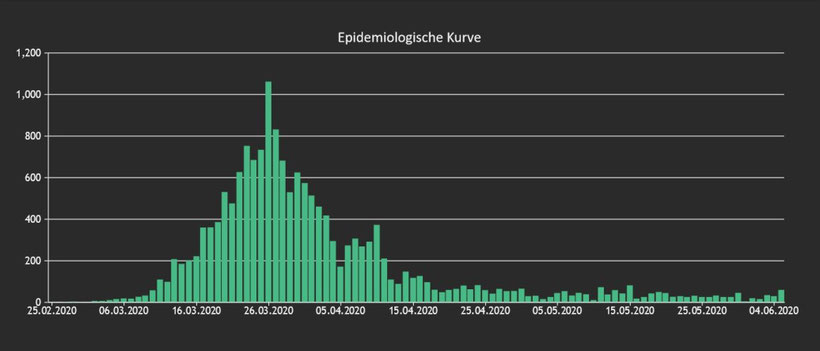
上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少し、4月後半からはさらに減少しながら横ばい的です。
残念ながらまだゼロではありません。
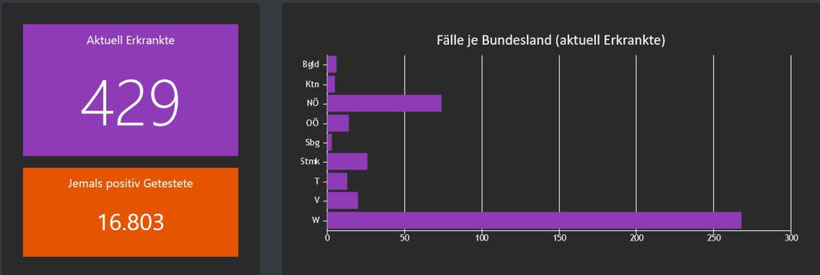
429人が発病、16.803人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。
5月2日に掲載した統計では1850人が発病してましたから1421人も少なくなっています。
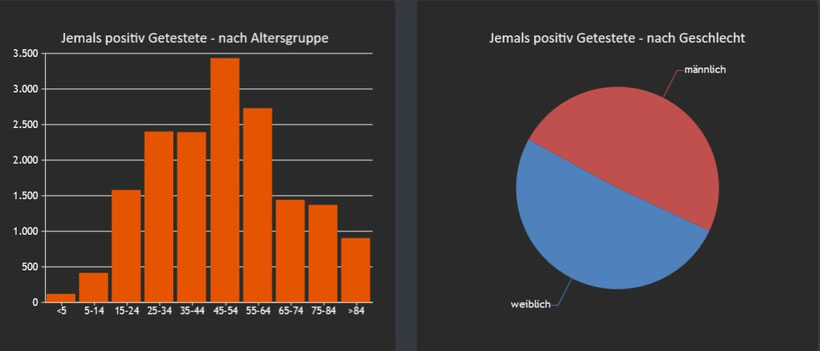
左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が49%、女性が51%です。

479.449の検査数、8.674の通常の病院ベットの空き数、780の集中治療室の空き数、55のベットが利用中、20の集中治療室が利用中、354人が自宅での療養数。
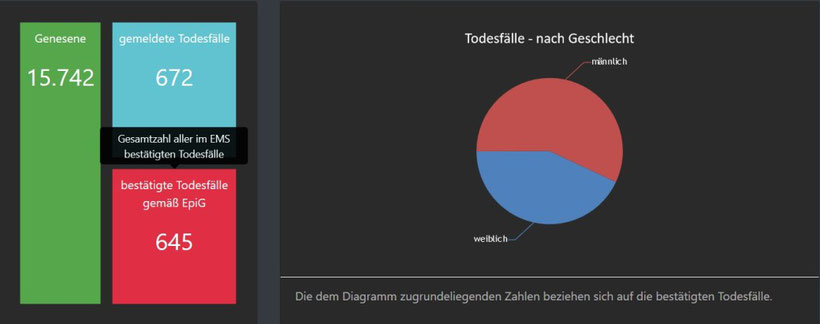
15.742人が再び健康に、672人の死亡報告、645人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで174名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州で11名ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
規制が大きく緩和され、数字だけ見ていると終息に向かっているように思いますが、ここで油断してしまうと第2波がやって来る可能性が強いことを多くの人が意識しています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。

新型コロナウィルス オーストリアでの統計
昨日からオーストリアでは店舗が再開されました。
レストラン、カフェなどは5月15日から、シェーンブルン宮殿、シシィ博物館、皇帝の部屋、銀器博物館なども5月15日からオープンが決まり、条件の下で入場が可能となります。
オーストリア連邦保健省(日本で言う厚生労働省)の Rudolf Anschober 大臣は今月の5月が„Monat der Entscheidung“・・・決定の月とコメントしています。
日常生活に戻る大きな一歩を踏み出しましたが、決してウィルスを甘く見ないで下さいと全国民にしつこく注意を促しています。
私達は成果を上げたが、まだ勝ったわけではありませんし危機は終わっていませんので、規制を守って下さいとも言っています。
さて、今日はオーストリア政府からの新型ウィルスに関して本日5月2日 朝6:00時点での統計を紹介します。
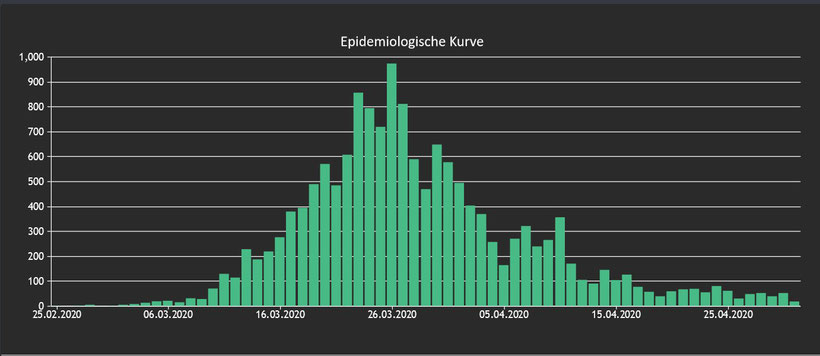
上の表は感染者数の推移です。
3月26日に向かって急上昇、その後は徐々に減少しています。

1.850人が発病、15.479人がテストの結果陽性。
右は州別の発病者のグラフです。
"W"はウィーンです。

左のグラフは陽性となった人の年齢分布です。
右は陽性となった男性と女性の割合で、男性が49%、女性が51%です。

264.079の検査数、16.203の通常の病院ベットの空き数、1.008の集中治療室の空き数、348のベットが利用中、124の集中治療室が利用中、1.378が自宅での療養数。

13.092人が再び健康に、589人の死亡報告、565人が実際に死亡が確認、死亡者数で男性が57%、女性が43%。
右の表はオーストリア州別の統計で、Geneseneが再び健康になった人、bestätigte Todesfälleは実際に死亡が確認された数です。
死亡者数からすれば人口が一番多いウィーンで132名がこの時点で亡くなっています。
死亡者が一番少ないのはBurgenland州ですね。
ウィルスの感染拡大はウィルス自身ではなく、人間が感染させているので、1人1人がしっかり自覚して行動すれば、結果的に自分、家族を守り、感染拡大は抑えられると思います。
昨日から規制が大きく緩和され、数字だけ見ていると終息に向かっているように思いますが、ここで油断してしまうと第2次波がやって来る可能性が強いことを多くの人が意識しています。
経済もこれ以上止められないということ、しかし人の命が最優先、状況をしっかり把握しながら適切な対応が取れるようにとオーストリア政府は他国と同様日夜努力をしています。
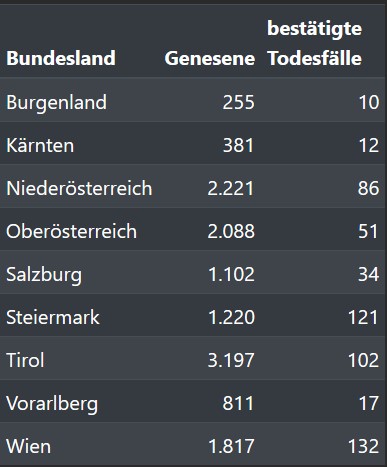
オーストリア連邦保健省の新型コロナウィルスに関する情報掲載ページ
新型コロナウィルスに関しての話題はここ1週間あえて掲載しませんでしたが、アメリカ、日本でも感染者が急増していますね。
こちらでも新たな感染者が増えないよう、できる限りの対策を行っています。
ウィルス自体が広がるのではなく、人間が広げているので個人レベルで意識してしっかり注意すれば自分だけでなく、他の人も守ることができるわけですね。
オーストリア政府では、食料品店、薬局、医療機関、銀行、郵便など必要最低限の営業以外を停止させ、学校も休校、公園も閉鎖、イベント、演奏会、博物館などもクローズ、家族以外の見知らぬ人との接触をしない、5人以上で集まらない、不必要な遠出はしないなど、その効果が表れ始めていると言われていました。
しかし全体の5%程度はまだまだそれを守らず甘く考えている人がいるという指摘もありました。
さて、オーストリアのGesundheitsministerium (日本では厚生労働省にあたり、ウィーンの日本大使館はオーストリア連邦保健省と表現していますが直訳すれば健康省です)が感染状況を知らせるページがオンライン上に公開されました。
昨日27日,オーストリア連邦保健省ホームページ(ドイツ語)の新型コロナウイルス情報掲載ページが新しくなり,より詳細な感染状況に関する情報が閲覧できるようになりました。
https://info.gesundheitsministerium.at/
オーストリア連邦保健省は国内検査施設が入力するデータバンクに基づき,新型コロナウイルスの感染状況を示す統計ダッシュボードの提供をオンライン上で開始しました。
以下のデータを1時間毎に更新します。
・死亡者数,治癒者数を含めた感染者数(Gesamtzahl aller positiv getesteter Personen)
・入院者数(hospitalisiert),集中治療室 (Intensivstation)での入院者数(別リンク)
・男女別感染者数の割合 (Geschlechtsverteilung)
・年齢別感染者数(Altersverteilung)
・行政区毎の人口10万人当たりの感染者数(色分け地図)
・行政区毎の感染者数(色分け地図及び詳細な数字)
・感染者数の推移
・州毎の感染者数
しっかりした情報を国民の皆様に提供しようということで、非常に分かりやすくまとめられています。
掲載されている地図やグラフの上にマウスを乗せると詳細が見られます。
早く収束して欲しいですね。
皆さんも健康に気を付けて下さい。
ウィーンを訪れた観光客の国籍 (2019年度)
ウィーンは年間を通して様々な国からの観光客が訪れます。
一般的な観光から専門分野まであらゆるバリエーションがありますが、これもウィーンという街がかつての帝国の都であったことでヨーロッパ文化が凝縮したとても多くが深い街だからでしょう。
2016年の2月にウィーンを訪れた観光客の国籍(2015年度)というテーマで、2019年3月にはウィーンの宿泊数(2018年度)を紹介しましたが、その後去年2019年度はどうだったかという統計を紹介します。
| 国 | 宿泊数 | 前年度との比較 |
| ドイツ | 3.360.000 | +6.0% |
| オーストリア | 3.046.000 | +2% |
| アメリカ | 1.032.000 | +8% |
| イタリア | 837.000 | +13% |
| イギリス | 736.000 | -3% |
| スペイン | 650.000 | +2.5% |
| 中国 | 524.000 | +3.0% |
| フランス | 511.000 | +10% |
| ロシア | 464.000 | +2% |
| スイス | 458.000 | +4% |
| 全体 | 17.605.000 | +6.8% |
※ウィーン市観光局より
https://b2b.wien.info/de/statistik/daten
この統計は2019年1月~2019年12月までのものです。
ベスト10は2018年度とはイタリアがイギリスを上回った以外は全く変わっていませんが、全体の観光客数が327万人増えています。
毎年そうですがドイツからの観光客が地元オーストリアを上回ってトップです。
以前は日本も唯一ベスト10に入っていたのですが、中国とロシアが急増したため、ベスト10からはじき出されてしまいました。
日本からのお客様が少なくなったわけではありません。
日本からのお客様は極端に増えることもなければ、また逆に少なくなることもなく非常に安定しています。
お陰様で私もいつも忙しいです。
仮に団体ツアーでも結果的に1人しか集まらず、エージェントさんの都合でそれでも添乗員をつけて1+1でツアーを催行する時もあります。
その場合でもガイド業務は必要ですから仕事が成り立つわけですね。
オーストリアでのガイド業務は国家ライセンス制度ですから、ガイドが必要な場合は正規の国家公認ガイドを手配することが国で定められているため、1名でも40名でもツアーが催行されれば国家公認ガイドがアテンドします。
国立オペラ座舞踏会(2020年)
1月6日のHeilige Drei Königeが過ぎるとウィーンの街は舞踏会が至る所で開かれ、それに伴うカレンダーもあるぐらいです。
舞踏会の中で最も頂点であるのは国立オペラ座の舞踏会(Opernball・・・オペルンバル)です。
この舞踏会は復活祭がいつ来るかによって開催される日が毎年変動し ます。
謝肉祭の最高点である火曜日(Faschingsdienstag)の前の週の木曜日と決め られていますので、今年は2月20日の木曜日・・・つまり今日ということになります。
去年は2月28日でかなり遅かったです。


左上の写真は2月17日の15:30頃です。
国立オペラ座正面入り口で、ちょうど舞踏会の正面入り口の構築が始まっています。
右上に写真は昨日11:00頃です。
正面の入口が完成していて、白いテント小屋が立っていますがこれはクロークです
相当大掛かりな作業で、どこから見ても目立ちます。
正面入り口だけではなく、後ろの搬入口や横の部分でも作業が行われています。
<国立オペラ座舞踏会の歴史>
国立オペラ座舞踏会は、有名なウィーン会議(1814-1815) の時からだとされていますが、場所は宮廷関係の劇場ではなかったようです。
そもそも国立オペラ座自体、1868年に完成していますからウィーン会議の50年以上後ということになります。
その1820~30年代、この帝国の都ウィーンでは数々の大小の舞踏会が開かれるようになっていました。
ヨーゼフランナー、ヨハン・シュトラウス(父)が活躍する時代ですね。
それから王宮のレドゥーテンザールで開かれるようになっていきますが、1848年の革命時からはしばらく静かになります。
1862年Theater an der Wienが舞踏会開催を許されました。
1869年にリンク道路の現在の国立オペラ座を宮廷が使い始めますが、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世がここでの舞踏会を拒んでいたため、1870年に完成したニューイヤーコンサートで有名な楽友協会ホールで "Ball in der Hofoper"として開かれました。
1877年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が賛同し、初めて現在の国立オペラ座の一角で祭典が行われました。
ハプスブルグ帝国崩壊後、オーストリアが共和国となり、すぐに帝国時代の懐かしさから1921年にはすでに舞踏会が開かれました。
1935年には「Wiener Opernball」という名で開かれ、1939年第2次世界大戦前日の夜、最後のオペラ座舞踏会が開かれます。
戦後壊された国立オペラ座が1955年に修復され、1956年2月9日に現在のオーストリア共和国の初めての国立オペラ座舞踏会が開かれ、現在に至っています。
つまり今年は現在のオーストリアになって63回目ということですね。
国立オペラ座舞踏会は世界各国の著名人、貴賓が集まり、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスと決められています。
<国立オペラ座舞踏会についての色々な数字>
ゲストの数は5.150人、146万人が国立オペラ座舞踏会のテレビ中継を見ている、144組の社交界デビュー、会場構築時間は350人の専門作業員、150人のアルバイトで30時間、解体時間は21時間、50の業者、総費用140万ユーロ、46.000以上のグラス、1.000枚のテーブルクロス、4.000のナイフとフォーク、1.300のSekt、ワイン900本、ビール900本、150人の音楽家・・・。
国立オペラ座の普段の運営もすごいものがありますが、たった1回のこの舞踏会でも物凄いものを感じます。
さて、気になる今年の料金はというと・・・
| 入場料 | EUR 315,- |
| ボックス席(ロジェ) | EUR 23.600,- |
| 舞台側ボックス席 (大) | EUR 23.600,- |
| 舞台側ボックス席 (小) | EUR 13.300,- |
| 舞台側ロジェ テーブル付き | EUR 11.500,- |
|
6人用テーブル |
EUR 1.260,- |
| 4人用テーブル | EUR 840,- |
| 3人 テーブル(相席) | EUR 630,- |
|
2人 テーブル (相席) |
EUR 420,- |
| 6階 4人用テーブル席 | EUR 420,- |
| 6階 2人用テーブル(相席) | EUR 210,- |
今年の料金は去年2019年度全く変わりません。
ちなみに一昨年は入場料290ユーロ、一番高いボックス席は20.500ユーロでした。
一番高いボックス席(ロジェ)は12人までが入れます。
それぞれの料金は入場料とは別で、飲食も別です。
入場料だけでも315ユーロですから国立オペラ座の最高額の座席よりも高いですね。
年間を通して数え切れないぐらい国立オペラ座の内部案内をしていますが、毎年思いますが舞踏会だけは別世界です。
国立オペラ座舞踏会の様子のビデオが見られますので、興味ある方は御覧下さい。
https://www.wiener-staatsoper.at/opernball/
※国立オペラ座オフィシャルサイトより
昨日はバレンタインデーでした(2020年)
昨日の2月14日はバレンタインデーでした。
私が小学校の頃からこの習慣はかなり広がっていましたが、女の子が男の子にチョコレートを贈る=好きな気持ちを告白する・・・というのが一般的だと思います。
こちらでもバレンタインデーの習慣は定着していて、女性からではなく、男性から女性にというのが一般的です。
バレンタインデー・・・こちらではValentinstagと呼ばれ、聖人のヴァレンティヌスの日ということになります。
ヴァレンティヌスはドイツ語では"Valentin"、彼は3世紀頃のキリスト教の聖職者で、269年2月14日に亡くなったということになっています。
結婚を禁止されたローマ兵士達のために、キリスト教的結婚式を挙げたことによりローマ帝国から迫害されます。
よく知られた伝説のひとつで、彼が迫害され、捕らえられている間に彼が面倒を見ている盲目の娘の目を直したそうです。
彼の死刑の直前にその娘に別れの手紙を書き、„Dein Valentin“と署名したそうです。
ヴァレンティヌスを祝う習慣は14世紀に宮廷で大流行りとなり、頂点を迎えました。
18世紀にイギリスで愛し合う2人がお互いにそれを表現し、花とお菓子、クリスマスカードのようにカードを贈る習慣が生まれました。
私の子供の頃は女性がチョコレートを贈る習慣でしたが、こちらでは前述したように男性が女性に贈るのが一般的ですが、どのような物が好まれているのか今年の傾向を見てみましょう。
右の統計は昨日の新聞ÖSERREICHに掲載されていたものです。
1位は圧倒的に花です。
特にバラの花が好まれるでしょうか。
昨日は花屋さんも忙しかったでしょう。
日本では当たり前のチョコレートは2位にランクされていますが、24%とそこまでチョコレートには固執してないようですね。
例えば普段料理を作ってくれているから、今日は僕が作るから・・・とか、掃除を代わりにするからとかそのようなことも夫婦関係などでは見られるようです。
まぁ~ちょっとした気遣いでしょうね。
聖ヴァレンティヌスが男性であったことなどが理由で、こちらでは男性が女性に気持ちを伝えるわけですね。
| 1. 花 | 59% |
| 2. チョコレート | 24% |
|
3. 出かける |
17% |
|
4. レストランでの食事 |
15% |
| 5. 商品券 | 12% |
|
6. 香水、化粧品など |
10% |
|
7. 自分の料理 |
10% |
| 8. アルコール | 9% |
| 9. アクセサリー | 8% |
| 10.洋服 | 8% |
ウィーンのある中国レストランでの新型コロナウィルスによる影響
先日ウィーンの日本大使館からの新型コロナウィルスの関連情報を掲載しました。
中国政府が国内外の団体ツアーを1月27日より禁止にしているため、ウィーンでも明らかに中国からの旅行者が減っていることがわかります。
街中を歩いていてもアジア人を警戒しよう(こちらの普通の人は日本人、韓国人、中国人の区別は難しいですし、知らない人はいっしょに見てしまうことも多いです)という空気は特に感じていません。
日本の厚生労働省のホームページから引用させて頂きますが、2月4日9:00現在で、海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下の通りです。
・中国:感染者名20,438名、死亡者425名。
・タイ:感染者19名、死亡者0名。
・韓国:感染者15名、死亡者0名。
・台湾:感染者10名、死亡者0名。
・米国:感染者11名、死亡者0名。
・ベトナム:感染者8名、死亡者0名。
・シンガポール:感染者18名、死亡者0名。
・フランス:感染者6名、死亡者0名。
・オーストラリア:感染者12名、死亡者0名。
・マレーシア:感染者8名、死亡者0名。
・ネパール:感染者1名、死亡者0名。
・カナダ:感染者4名、死亡者0名。
・カンボジア:感染者1名、死亡者0名。
・スリランカ:感染者1名、死亡者0名。
・ドイツ:感染者12名、死亡者0名。
・アラブ首長国連邦:感染者5名、死亡者0名。
・フィンランド:感染者1名、死亡者0名。
・イタリア:感染者2名、死亡者0名
・インド:感染者3名、死亡者0名
・フィリピン:感染者2名、死亡者1名
・英国:感染者2名、死亡者0名
・ロシア:感染者2名、死亡者0名
・スウェーデン:感染者1名、死亡者0名
・スペイン:感染者1名、死亡者0名

オーストリアでは幸いにしてまだ感染者は確認されおりません。
さて、右の写真はウィーンでいつも地元の人で混んでいるある中国レストランです。
ここは注文した物をロボットが運んで来るというユニークさがあり、もちろん食べ放題のビュッフェもあり店も大きくて清潔感もあり常にはやっています。
私はここのそばのアジア食材店によく買い物に来るのですが、この店が数年前にオープンした時にたまたまこのレストランのオーナーと出会い、しばらく話をして、店内を案内してもらったことがあります。でも未だかつて一度もここで食事をしたことがありませんでした。(笑)
昨日、急にチャーハンが食べたくなり、
買い物ついでに持ち帰りをしようと店に入ったらテレビのカメラチームが店内の撮影をしていました。
私はてっきりこの店がはやっているので、それをメディアに取り上げるのかと思っていたら、全く違いました。
中国からの新型コロナウィルスが広まる中、ウィーンの地元で営業する中国レストランの現状を取材するためだったのです。
オーナーは私のことを覚えていて、ブランクがあったにも関わらずいきなり"Du"フォームで話しかけてきて、親切に挨拶してくれました。
この店に中国の団体客が来ることはなくお客さんは地元の人が主流なのですが、新型ウィルスのせいでお客さんの数が激減しているということです。
武漢の市場から・・・食材・・・中国レストラン・・・という流れで、地元の人の先入観があるのでしょう。
現状ではどうにもならないとオーナーが嘆いていました。
お客さんはもちろんゼロではないので、私達が話をしている間にも何組か食べに来ましたが、いつもは満席の状況がガラガラということでした。
ちなみに持ち帰ったチャーハンの味はイマイチでした。(笑)
難民問題その後 14
2019年の始めに難民問題その後 13で状況をお伝えしました。
以前と比べれば明らかに難民の流れは大きく減少していて、数から言えば終わったとされていますが、解決したわけではありません。
トルコが協力して難民が欧州に流入するのを防いでいますが、そのトルコが欧州や米国から十分な支援が得られなければ欧州ルートを開放するという警告を9月に出しています。
難民問題を外交の駆け引きに利用しているようです。
トルコが協力してくれる以前と比べればそれでもまだ数は少ないですが、難民の数は再び増加しています。
今日はちょっと遅れて去年のデータですがここに掲載しておきます。
ギリシャエーゲ海の北島にあるレスボス島は2015年の難民問題の始まりを思い出させる状況で、1日に500人もの難民が夜に押し寄せています。
希望が無いボートに詰め込まれたトルコから来たシリアの難民達、シリア以外のアフリカからも多くレスボス島を目指します。
当然レスボス島も大変です。
結果的にバルカンルートがまた利用されているようです。
中にはトルコ当局に捕らえられてトルコに戻された難民も少なくありません。
実際トルコ国内でも難民数が大きな問題となっていて、トルコ国民より不満が持ち上がっています。
これはEUでもトルコでも同じような状況です。
イスタンブールにはオフィシャルで500.000のシリア難民が生活していて、アフガニスタンなどからも多くの難民が入り込んでいます。
右の表は去年9月後半の新聞に記載されていた統計で、トルコが欧州へのルートを開放するという警告をした時のデータです。
イタリア、スペインは去年と比べるとかなり減少していますが、ギリシャ、マルタ、キプロスの地中海の島は難民がかなり増えています。
|
難民はどこへ? |
2018年 |
2019年 |
| イタリア | 20.859 | 6.570 |
| マルタ | 714 | 2.260 |
| ギリシャ | 22.261 | 32.767 |
| キプロス | 300 | 4.926 |
| スペイン | 34.238 | 16.894 |
UNOによれば去年9月18日までに63.417人の難民が地中海経由でヨーロッパに来ました。
オーストリアでは当局が週平均355人の難民とかかわっていて、ドイツからのデータによれば週平均700人がオーストリアとドイツ国境で難民と接していると言うことです。
ということはオーストリアでは週平均1.000人の難民が国内に留まるか通過しているということになります。
毎回書いていますが、難民問題は観光や生活には何の影響もありません。
舞踏会に関しての傾向
ウィーンでは謝肉祭シーズン=舞踏会シーズンです。
謝肉祭に関してはまたここで話題にしますが、19世紀以降からは11月11日の11:11から始まるとしている所が多いです。
ウィーンでは実際に1月6日のHeilige Drei Königeが過ぎてからその空気が感じられると思います。
この時期には舞踏会が毎日のように開かれていて、ウィーンのまたひとつの伝統を感じることができます。
舞踏会カレンダーを見ると様々な分野の舞踏会がローカルで開かれています。
その舞踏会の最高峰が国立オペラ座の舞踏会で、今年は2月20日です。
舞踏会と言えばウィーンナーワルツが真っ先に思い浮かびますね。
観光とはあまり縁がないかもしれませんが、ウィーンナーワルツはウィーンならではです。
でも日本からのツアーでもウィーンナーワルツをちょっと体験できるツアーもあります。
さて、今日はその舞踏会にどのくらいの人数が集まって、どのくらい支出するのかという統計を紹介します。
| シーズン | ウィーンから | 他の州から | 外国から |
| 2011/2012 | 360.000 | 65.000 | 50.000 |
| 2013/2014 | 380.000 | 65.000 | 50.000 |
| 2017/2018 | 390.000 | 60.000 | 55.000 |
| 2018/2019 | 400.000 | 60.000 | 55.000 |
| 2019/2020 | 405.000 | 60.000 | 55.000 |
| 入場券、テーブル予約 | 105ユーロ |
| 食事、飲み物 | 75ユーロ |
| ダンス教室、クローク | 55ユーロ |
| 舞踏会前の夕食 | 20ユーロ |
| 美容室などでのセット | 20ユーロ |
| タクシー | 15ユーロ |
上の2つの表を御覧下さい。
オーストリア事業主のための情報新聞Wiener Wirtschaft2019年11月14日号に掲載されていたものです。
左上は舞踏会に参加する人数ですが、ウィーンからの参加が圧倒的に多いですが、オーストリアの他の州からや外国から参加する方も50.000~55.000人もいるわけです。
ウィーンの場合は全人口の20%以上の割合になります。
右上の表は1回の舞踏会で1人が支出する平均金額を項目別に並べててあります。
この統計によれば1人平均290ユーロ支出することになっています。
国立オペラ座のような入場だけで数百ユーロするものもあれば、数十ユーロで楽しめる舞踏会もあり様々です。
会場でテーブルなどを持つとそれだけで高くなり、飲食もえそれなりには高いですからね。
私も過去王宮舞踏会、お菓子屋さんの舞踏会など何回か参加したことがあります。
色々な人がいて社交的な場であると同時に、結構くせになるかもしれません。
舞踏会はこちらでは老若男女問わず楽しまれていますね。
人気ある子供の名前(2018年度)
クリスマスがどんどん近づいているウィーンです。
明日はAdventの第3日曜日となり、Adventskranzに3本目のロウソクが灯されます。
今日はクリスマスの話題からちょっと離れます。
赤ちゃんが生まれて名前を付けるのは両親の喜びのひとつですね。
こちらの名前はキリスト教ローマカトリックに登場する聖人の名前が一般的に多いと思いますが、近年では必ずしもキリスト教的な名前でない人もたくさんいます。
また、こちらでは親しい間柄ではあだ名で呼ぶ習慣が多く見られ、10年以上その人のことを知っていても苗字を意識しなかったなんてことはよくあります。
日本でもその年ごとに人気のある名前という統計が発表されますね。
ウィーンではどんな名前が人気があるのでしょうか?
今日はそれを少し見てみましょう。
| 男の子 | |
| 1.Paul | 830 |
| 2.David | 822 |
| 3.Jakob | 803 |
| 4.Maximilian | 783 |
| 5.Felix | 751 |
| 6.Elias | 726 |
| 女の子 | |
| 1.Anna | 869 |
| 2.Emma | 825 |
| 3.Laura | 661 |
| 4.Marie | 643 |
| 5.Lena | 632 |
| 6.Mia | 632 |
※Statistik Austria より
これは2018年度のウィーンの統計です。男の子はPaul、女の子はAnnaが一番多いです。
男の子はAlexander、Lukas、女の子はSophia、Johannanaなども人気があり、ベスト10入りです。
名前もそれなりに流行りすたれがあるので、その時代を反映しています。
オーストリア クリスマス市ベスト10
もう何回も書いていますが、年間を通して生活の中で一番重要なイベントはクリスマスです。
ひと月以上もクリスマスの空気を楽しむことからも理解できます。
このクリスマスの時期には街中の主要な通りにイルミネーションが灯され、クリスマス市やプンシュ屋台が立ち、レストランやカフェ、商店のデコレーションなど・・・街中を歩くだけで楽しいです。
またもみの木を売る業者が準備を始め、また場所によってはもみの木がすでに売られている所もあります。
このクリスマス時期の仕事は年間を通してやっぱり特別な気持ちになりますね。
さて、今日はオーストリアクリスマス市ベスト10というタイトルで、オーストリアのどこのクリスマス市が人気があるかという統計をお知らせします。
こちらではクリスマス市のことをChristkindlmarkt(クリストキンドルマルクト)、Adventmarkt(アドヴェントマルクト)、Weihnachtsmarkt(ヴァイナハツマルクト)などといつくかの呼び方があります。
クリスマスにはサンタクロースが登場せず、プレゼントはChristkind・・・子供のキリストが持って来ることからChristkindlmarktと言うわけですね。
市庁舎のクリスマス市にもそのロゴがハッキリ見られます。
Advent(アドヴェント)はクリスマスがいつやって来るのだろう・・・とわくわく待つ習慣なのでAdventmarkt、ドイツ語でクリスマスは"Weihnachten"ですからWeihnachtsmarktとも言うわけですね。
右の表は12月9日の新聞Österreich (oe24)に掲載されていた現時点でのクリスマス市のランクです。
1位はWolfgangseeです。
ここはWolfgang湖に面しているSt.Wolfgang、St.Gilgen、Stroblの3つの街で楽しむことができ、ロマンチックでムード満点なクリスマス市です。
St.Wolfgangは私の大好きな白馬亭があります。
2位にはウィーン市庁舎のクリスマス市がランクしました。
3位は私も大好きなウィーンのSpittelberg、9位にはシェーンブルン宮殿のクリスマス市が入っています。
ウィーンからは4つがベスト10入りです。
最後のSchloss Hofもうちが毎年行っている所です。
| 1. | Wolfgangsee(Salzburg,Oberösterreich) |
| 2. | Rathausplatz (Wien) |
| 3. | Spittelberg(Wien) |
| 4. | Mariazell(Steiermark) |
| 4. | Schloss Hellbrunn(Salzburg) |
| 6. | Altes AKH (Wien) |
| 6. | Domplatz (Salzburg) |
| 6. | Goldenes Dachl(Tirol) |
| 9. | Schönbrunn(Wien) |
| 9. | Schloss Hof(Niederösterreich) |
市庁舎のクリスマス市はオーストリア最大であり、350万人が訪れます。
今年はプンシュなどのフード系にはオーストリア全体で390.000.000ユーロ(約470億円)が消費されるということです。
屋台でいつも混んでいるのはフード系です。
それぞれのクリスマス市にはそれぞれの空気があります。
そんな違いを地元の人は楽しんでいるようです。
オーストリアでの職種による年間所得
オーストリアの物価は意外と高く、税金や社会保険などもかなりの天引き率があるので、まとまったお金を持っている人というのはそんなに多くないと思います。
2002年にユーロが導入されてからは、物価は明らかに上昇しています。
かつての通貨シリングの方が良かったという声はいまだに多く聞かれますね。
今日はオーストリアでの主だった職種別の年間所得を見てみましょう。
<男性>
<女性>
| 会社役員 | 165.796 |
| 歯科医 | 118.818 |
| ギムナジウム教員 | 63.208 |
| システム管理者 | 51.797 |
| ソフトウェア開発者 | 49.940 |
| 建築主任 | 49.746 |
| 電気技師 | 45.493 |
| 銀行員 | 47.704 |
| 市バス、路面電車の運転士 | 36.975 |
| 配管工 | 34.397 |
| 男性の平均 | 33.776 |
| 大型トラックの運転手 | 32.737 |
| 自動車修理工 | 31.472 |
| 販売員 | 21.067 |
| 警備員 | 17.914 |
| コック | 17.288 |
| 歯科医 | 77.600 |
| ギムナジウム教員 | 46.488 |
| マーケティング管理者 | 42.851 |
| 小学校の先生 | 36.808 |
| 銀行員 | 33.522 |
| 税理士 | 31.030 |
| 事務局長 | 30.703 |
| 秘書 | 26.844 |
| 介護員 | 26.274 |
| 手工業者 | 22.301 |
|
女性の平均 |
21.178 |
| 販売員 | 16.428 |
| 保育士 | 15.846 |
| 受付嬢 | 15.335 |
| 厨房補佐 | 15.027 |
| 清掃員 | 12.667 |
上の表は今年8月の終わりに新聞に掲載されていたRechnungshof Österreichからのデータで、オーストリアでの主要な職業における税込みの年収で、数字はユーロです。
男性と会社役員や歯科医は抜きに出て所得が多いですね。
こちらではよく言われているように男性と女性の収入の差がかなり大きいことがわかります。
男性の平均年収は33.776ユーロ、女性は21.178ユーロです。
ここから税金や社会保険が引かれますので、実際は手元に残る金額はもっと少なくなります。
平均収入だけ見ていると、オーストリアの高い物価水準からすると、皆さんかなりぎりぎりでやりくりしている人が多いと思います。
最も共稼ぎが多いですから、2人の収入を合わせてうまくやって行くということですね。
でもウィーンで生活をしていると、地元の人は心にゆとりを持って人生を楽しんでいる空気が多く感じられます。
よく寝られていますか?
皆さん、夜はしっかり寝られていますか?
肉体的な疲れと精神的な疲れとでは熟睡できる度合いが違うと思います。
精神的に疲れている場合や遅く仕事から戻った場合などはすぐに寝ることが出来ない人は多いと思います。
こちらではどうでしょうか?
ウィーンは東京と比べれば生活のリズムはゆっくりしていると思いますが、何らかの理由で熟睡できない人は多いと思います。
今日はその辺の傾向を見てみましょう。
右の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at/index.html(日本労働組合総連合会のような機関)2019年2月号に掲載されていたどのくらい睡眠時間をとっているかというデータです。
平均的に7時間~8時間睡眠をとる方が約60%ということで一番多いですね。
私に関しては6時間~7時間の睡眠時間が平均的だと思います。
| 5時間まで | 4% |
| 5.5時間~6時間 | 15% |
| 6.5時間~7時間 | 31% |
| 7.5時間~8時間 | 28% |
| 8.5時間~10時間 | 8% |
| 無回答 | 14% |
同時によく寝られない方の状況などもここに掲載されていました。
実際に眠るまでに30分以上もかかる人は38%
途中で目が覚めて寝返りを打つ人は50%
よく寝られるようになるための医療的助けを探している人16%
日中に居眠りをする人は38%
仕事上の理由で寝られない人は32%
ということです。
それなりに悩んでいる人が多いですね。
オーストリアでの新車登録台数(2018年度)
車文化もヨーロッパ文化のひとつでしょう。
ウィーンの街にも多くの車が走っています。
日本では路駐がほとんどないわけですが、逆にこちらは路駐が当たり前です。
多くのお客様が「これだけ路駐をしていても問題ないんでしょうか?」という質問をよく受けます。
街の歴史の方がずっと古いですから、後から来た車が街に共存させてもらっている・・・そんな感じです。
もちろんウィーンは路駐はしっかり規則の下に行われています。
オーストリアは世界的に見てかなりの車の保有率があり、ウィキペディアに掲載されている統計によれば19位となっていて、1.73人に1台の割合で車を所有しているようです。
ちなみに日本は17位ですのでオーストリアとほとんど変わりません。
さて、今日はオーストリアにおいて、どこのメーカーの車がどのくらい普及しているかという統計をお届します。
| VOLKSWAGEN | 56.932 | 16.7% |
| Skoda | 25.434 | 7.5% |
| Ford | 19.916 | 5.8% |
| Opel | 19.152 | 5.6% |
| Seat | 18.713 | 5.5% |
| Hyundai | 18.609 | 5.5% |
| Renault | 18.609 | 5.5% |
| BMW | 18.554 | 5.4% |
| Mercedes | 16.384 | 4.8% |
| Fiat | 14.649 | 4.3% |
上の表はStatistik Austriaからの引用です。
オーストリアにおける2018年度の新車認可台数とそのシェア率を示しています。
1位は圧倒的にVolkswagenで、56.932台が新車登録されていて、全体の16.7%を占めています。
トップのVolkswagenはここ何年も変わっていませんので、安定したシェア率を持っています。
2位以下からは毎年、毎月ランクが変動しますが、数年来から勢いを示しているSkodaやHyundaiがかなりのシェアを持っていることがわかります。
でも2位のSkodaが7.5%ですから、Volkaswagenがいかに人気があるか、そしてそれ以下は言って見ればどんぐりの背比べのようなものです。
ちなみに日本メーカーは、2011年の震災の影響もあり、Mazdaが10.739台で13位の3.1%、Suzukiが8476台で16位の2.5%、Toyotaが7961台で17位の2.3%、Nissanが6304台で19位の1.8%となっています。
2021年よりプラスチック製品が消える
もう何年も前にビニール袋の環境汚染について話題にしたことがありました。
このままだと2050年には魚よりもプラスチック製品の方が海で多く見られると言われています。
日本でもこのテーマは結構取り上げられていますね。
EUでは今年3月の末に2021年よりかなりのプラスチック製品を禁止することを決定しました。
実際にはどんなプラスチック製品が該当するのでしょうか?
右の表を御覧下さい。
2021年より姿を消していくプラスチック製品です。
どれも基本は1回限りの利用物です。
EUはこれを始めとして、プラスティックカップや食品を入れるパックなどの製造を減らす取り決めもしています。
1回限りの品物には製造元も環境に悪い影響を与えるというような注意書きを入れなければならないことや、2029年までにペットボトルもしっかりと所定の場所に捨てられ、2030年までには全体のペットボトルの30%リサイクルであるなどと決められました。
オーストリアは環境に関してもヨーロッパでは最先端の国のひとつです。
例えば2020年よりビニール袋は禁止されます。
|
1. プラスチックのお皿 |
|
2. プラスチックのナイフやフォーク |
|
3. ストロー |
|
4. 綿棒 |
|
5. 風船を留める部分 (Luftballonstäbe) |
|
6. コーヒーなど砂糖をかき混ぜるスティック |
|
7. スーパーにある小さなビニール袋 |
日常生活にすっかり定着している製品なので意識が薄いと思いますが、やはり地球の環境は個人それぞれが個人レベルでも配慮すれば大きな効果があるでしょう。
9月29日オーストリア総選挙 クルツさん大勝利
先週の日曜日、9月29日はオーストリアの総選挙・・・Nationalratswahl(国民議会選挙)が行われました。
御存知のように欧州諸国最年少の首相であったSebastian Kurzさん率いる国民党が大勝利を納めました。
地元の方にとってこの結果は予想通りだったと思います。
先に"首相であった・・・"と書きましたが、Kurzさんは2年前2017年10月の国民議会選挙で新国民党の党首として勝利を納め、同年12月18日より首相として活躍していました。
しかし・・・その後副首相が引き起こしたスキャンダルに巻き込まれることになります・・・。
2017年の国民議会選挙ではKurzさんが党首となったÖVP(国民党)がトップとなりましたが、183議席の過半数を超えなかったため、連立政権となったわけですが、3位であった右派のFPÖ(自由党・・・Freiheitliche Partei Österreichs)との方針が決まって、連立政権がスタートしました。
その自由党の党首であったHeinz-Christian Stracheさんが副首相となりますが、2019年5月にスペインの地中海の島、イビサの別荘でロシア新興財閥の姪と密談している様子が隠し撮りされて公表されることになります。選挙支援を得る見返りに公共事業受注を約束したとする疑惑で、5月18日に副首相、自由党党首を辞任します。
クルツさんは翌19日にオーストリア大統領と善後策を協議し、大統領は今秋にも総選挙を行うべきであると主張しました。
5月27日に野党である社会民主党が提出した内閣不信任案が可決され、与党であった自由党もそれに投票して首相クルツさんは退陣に追い込まれることになります。
クルツさんは不信任案可決後、「きょうは議会が決めたが、9月には国民が決めるだろう。それを楽しみにしている」と言った通りの選挙結果となりました。ちなみに6月3日より暫定的に無所属であるBrigitte Bierleinさんが現首相となっています。
右の表はオーストリア内務省からの引用です。
一番右の数字は議席数です。
ÖVP(国民党)が37.5%と圧倒的な勝利を納めました。
スキャンダルを引き起こしたFPÖ(自由党)は3位という結果になり、16.1%と激減しました。
2位には社会民主党が21.2%となっていますが、彼らも前回よりも少ない数字となりました。


上の表は前回2017年との比較で、SPÖ、FPÖが大幅に落ち込んだ分、クルツさんのÖVP、NEOS、GRÜNEが議席を増やしました。
有権者数6.396.802、投票者数4.802.397(75.1%)、有効投票4.744.496(98.8%)、無効投票57.901(1.2%)が今回の選挙データです。
ウィーンでの持ちアパートの1m²の価格
ウィーンは土地の値段が高騰しています。
まだ土地が多くある外側の区では多くの集合住宅が建設されています。
持ち家として売られるもの、賃貸として、また最初は家賃のように払って10年後に購入できるようになるスタイルなどがあります。
持ち家の方が理想でしょうが、月々の支払は自由に決められても、最初にまとまったお金が必要であることや土地が高いこともあり、ウィーンでは庭があるような持ち家に住んでいる人の割合は20%ぐらいに過ぎません。
賃貸だって何十年も同じ所に住んでいる人は別として、年々家賃が上がっていますから、お手頃な住居を見つけるのが非常に難しくなっているのが現状です。
さて2016年9月6日付でオーストリアの住宅価格について触れましたが、現在ではどのくらいまで高騰しているのでしょうか?
去年2018年7月に持ち家の場合での1m²の価格をウィーンそれぞれの区で比較しましたが、今回はWohnung(アパート、集合住宅の一室)・・・持ちアパートの1m²の価格を見てみましょう。
| ウィーンそれぞれの区 | 1m²の価格(ユーロ) |
| 1. Innere Stadt | 9.606 |
|
2. Leopoldstadt |
3.803 |
|
3. Landstraße |
4.618 |
|
4. Wieden |
4.651 |
|
5. Margareten |
4.013 |
|
6. Mariahilf |
5.124 |
|
7. Neubau |
3.392 |
|
8. Josefstadt |
3.392 |
|
9. Alsergrund |
5.180 |
|
10. Favoriten |
3.439 |
|
11. Simmering |
2.824 |
|
12. Meidling |
3.842 |
|
13. Hietzing |
4.135 |
|
14. Penzing |
3.272 |
| 15.Rudolfsheim-Fünfhaus | 3.244 |
| 16.Ottakring | 3.206 |
| 17.Hernals | 3.846 |
| 18.Währing | 4.571 |
| 19.Döbling | 4.992 |
| 20.Brigittenau | 3.113 |
| 21.Floridsdorf | 3.412 |
| 22.Donaustadt | 3.819 |
| 23.Liesing | 3.495 |
※RE/MAXより
これはWohnung(いわゆる集合住宅のアパート)を持ち家として(Eigentum)購入する場合の1m²の価格で、一戸建て(Haus)は含まれていません。
ウィーンは中心からかなり外側までは集合住宅で、もっと外側には一戸建てが多く立っています。
ウィーン1区だけが極端に高く、次に9区のAlsegrund,6区のMariahilfとなっています。
ちなみに23区の平均価格は4.130ユーロです。
住居は年々上昇傾向にあり、留学などの短期滞在者が賃貸する場合も家賃的にお手頃の住居を探すのは難しくなっているようです。
公共交通機関の年間定期利用者数が新記録
ウィーンは415km²、人口190万弱、東京と同じ23区で成り立っているかなり広い街です。
ヨーロッパでは大都会と言っていいでしょう。
そのウィーンの公共交通機関はよく発達していて、世界でも5本指に入る営業距離数を持っています。
地下鉄 (U-BAHN)、路面電車(STRASSENBAHN)、路線バス(AUTOBUS)がウィーン市交通局の運営で、国鉄(SCHNELLBAHN)もウィーン市内であれば共通券で乗れるシステムになっています。
公共交通機関はウィーン市民の重要な足であると同時に、観光で訪れる方々にとっても必要不可欠でしょう。
ウィーンに個人旅行で滞在する観光客の皆さんはウィーンの公共交通機関を利用しない方はまずいないでしょう。1回券、24時間券、48時間券、72時間券が一般的だと思います。
その他1週間定期や1ヵ月定期もあるので、滞在が長い方はこれらも無記名で利用できますので割引率が高く、利用価値大です。
しかし、多くの地元の人はそれよりももっと割引率が高い年間定期を所有しています。
この年間定期の利用者が去年2018年度は過去最多となり記録となりました。
右の表は"STADTleben"2019年3月号に掲載されていたものですが、情報元はWiener Linienからのものです。
2005年には30万ぐらいしか利用者がいなかったわけですが、2015年には倍以上の70万人となり、きょねん2018年度は822.000とウィーンに住む人の44%が年間定期を所有していることになります。
ウィーンはECOの街でもあり、カーシェアリングやcitybikeなども人気があり、なるべく車に乗らないように・・・という空気が感じられます。
実際には車はあった方が便利ですが、公共交通機関がこれだけ網羅していますからそういう意味で普段の通勤には車は必要ないと考える人も多いでしょう。
| 2005年 | 303.000 |
| 2009年 | 336.000 |
| 2011年 | 363.000 |
| 2012年 | 501.000 |
| 2013年 | 582.000 |
| 2014年 | 650.000 |
| 2015年 | 700.000 |
| 2016年 | 733.000 |
| 2017年 | 778.000 |
| 2018年 | 822.000 |
年間定期の料金は一括で払えば1日1ユーロ・・・つまり365ユーロです。
オーストリアは税金が高い国ですので、このような所にも還元されていると思います。
年間定期はカードスタイルですが、ウィーンに住所が無ければ購入できませんし、顔写真が必要です。
私も年間定期をもう25年以上利用しています。
オーストリア24時間 その4
"ウィーンこぼれ話"ではその時に思いついた色々なことをテーマにしています。
ためになる内容からどうでもいい内容まで様々です。
オーストリアはいまでこそ北海道よりもちょっと広いぐらいの小さい国ですが、この国がヨーロッパに与えた歴史的、文化的な影響は計り知れないものがあります。
今日は久しぶりに"オーストリア24時間"です。
このオーストリアにおいて、24時間の間に何がどのくらい起こるのかということをStatistik Austriaを始め、オーストリアの様々な専門分野や政府関係からの統計からまとめています。
| 有罪判決を受ける | 99人 |
| 犯罪届 | 1501件 |
| 何らかの事情で子供達の住む場所がなくなる | 7人 |
| 事故 | 112人 |
| アルプスでの事故 | 20人 |
| 仕事中の事故 | 310人 |
|
交通事故 |
111件 |
| ボランティア | 67.356人 |
| 臓器移植 | 4人 |
| 手術 | 872人 (その内223人は白内障) |
| 歩行者もしくは自転車に乗っている人の死亡 | 3日に1人 |
| 死亡数 | 209人 |
どうでもいい統計もありますが、オーストリアを知っていれば非常に興味深い内容だと思います。
このオーストリアでは24時間に色々なことが起こっていますね。
オーストリア24時間その1、オーストリア24時間その2、オーストリア24時間その3も好評を頂きましたので興味ある方は是非御覧下さい。
ウィーン ホイリゲベスト10
ホイリゲと言えば必ずガイドブックに紹介されているウィーンやその周辺にあるこちらの文化のひとつで自家製ワインを飲ませる店・・・日本的に言えば居酒屋です。
多くの団体ツアーでも夕食にホイリゲに行くということがよくあります。
ホイリゲはちょっと郊外に行かないとその雰囲気を味わうことができません。
「ホイリゲ」とはドイツ語でheuer (ホイヤー)、heurig (ホイリヒ)「今年、今年の」という意味があり、新種のワインの名称でもあり、それを飲ませるお店もホイリゲと言います。
多くのホイリゲがウィーンや郊外のワイン産業地域にありますが、今年の5月に恒例のウィーンのホイリゲベスト10が発表されました。
右の表はFalstaffが今年5月23日に発表したウィーンホイリゲベスト10です。
25.000人以上の意見をまとめたものということになっています。
1位は23区のEdlmoser、2位は21区StammersdorfのKrenekとWieningerです。
ベスト10入りしたホイリゲを見ると、料理の質、店の雰囲気でポイントを上げていて、雰囲気としてはぶどう畑があり、ウィーンの街が眺められる素敵なロケーションを持つホイリゲが多くランクされています。
日本のガイドブックにはおそらくベートーヴェンが住んだMayer am Pffarplatzぐらいしか紹介されてないと思います。
| 1. Heuriger Edlmoser | 23区 Mauer |
| 2. Helmut Krenek | 21区 Satmmersdorf |
| 2. Heuriger Wieninger | 21区 Stammersdorf |
| 4. Buschenschank Obermann | 19区 Grinzing |
| 4. Buschenschank Wieninger | 19区 Nussdorf |
| 4. Buschenschank in Residence | 19区 Grinzing |
| 7. Weingut Christ | 21区 Jedlersdorf |
| 8. Mayer am Pfarplatz | 19区 Heiligenstadt |
| 9. Weingut Wailand | 19区 Kahlenbergerdorf |
| 9. Weingut Walter Wien | 21区 Strebersdorf |
| 10. Buschenschank Bernreiter | 21区 Jedlersdorf |
| 10. Weingut Werner Welser | 19区 Heiligenstadt |
| 10. Buschenschank Mayer | 19区 Nussdorf |
私個人的にはMayer am Pffarplatzは以前と比べて観光客に対してかなり不親切さを感じるホイリゲになったと思っているので、個人的に行くことはまずないですね。
好みや意見などは人によって様々でしょうから、この統計はあくまでも目安です。
これ以外にも話題性があるホイリゲは星の数ほど存在します。
しかし、これらは地元で有名なホイリゲであることには間違いないです。
それぞれのホイリゲにはホームページが出されているので、時間がある方はちょっと下調べをして行ってみてはいかがでしょうか。
特に21区のSatmmersdorf界隈は昔ならではの本来のホイリゲが多く存在しています。
電気自動車の普及率がヨーロッパで第2位(2019年2月時点)
約2年前の2017年5月16日付で電気自動車は普及するか?というタイトルで電気自動車の導入や主要自動車メーカーの電気自動車の種類と価格を紹介しました。
それから約2年が経ち、ウィーンの街中でもより多くの電気自動車が見られるようになり、充電スタンドも色々な所に設置されているので明らかに普及していることがわかります。
オーストリア政府がその当初2017年3月に電気自動車を購入する消費者へ4.000ユーロの援助金(一時的)が支払われるようになったことも急速な普及につながっています。
ヨーロッパ全体的に見ると現時点でオランダの次にオーストリアは第2位の電気自動はの普及率となっています。
右の表を御覧下さい。
これはウィーンで電気自動車がどのくらい普及しているかという統計です。
2017年からは政府のテコ入れもあって急増していますね。
| 2015年 | 5.032 |
| 2016年 | 9.075 |
| 2017年 | 14.618 |
| 2018年 | 20.831 |
今年2019年の3月からオーストリア政府は93万ユーロ(約120億円)の予算を組み込み、プライベート利用の電気自動車購入の際には3.000ユーロ、ハイブリット車には1.500ユーロ、電動バイクには1.000ユーロ、電動スクーターには700ユーロ、電動カーゴバイクには400ユーロの補助金が支払われています。
現在の電気自動はのシェア率は2%となっていますが、専門家によれば2030年には25%に達すると見られています。
そうなるとガソリン車やディーゼル車が禁止になる可能性があります。
実際オーストリアの政党のひとつはそれを促進しています。
電気自動車はやはりこれからもっと普及していきますね。
治安のいい街 ベスト10
今年3月15日にウィーンは世界で一番住みやすい街に10年連続で第1位となったことを話題にしました。
ウィーンが大好きな私にとっては非常に嬉しい結果となりました。
個人的にもウィーンは生活すること、人生を歩んで行くことに関してクオリティーが高い・・・ということを実感しています。
地元の人はそれを意識しているかどうかはわかりませんが、ウィーンの街を歩けば優雅さと上品さだけではなく、生活のリズムも何となくゆったりしていることを感じます。
さて、この環境都市調査を毎年行っているMERCER(マーサー)は、今年は治安面の関してのランク付けも発表しました。
今日はそれをちょっと見てみましょう。
| 1. | ルクセンブルク(ルクセンブルク) |
| 2. | バーゼル (スイス) |
| 2. | ベルン(スイス) |
| 2. | ヘルシンキ(フィンランド) |
| 2. | チューリッヒ(スイス) |
| 6. | ウィーン (オーストリア) |
| 7. | ジュネーブ (スイス) |
| 7. | オスロ(ノルウェー) |
| 9. | オークランド(ニュージーランド) |
| 9. | ウェリントン(ニュージーランド) |
MERCER (マーサー・・・世界最大の組織・人事マネージメント・コンサルティング会社)は毎年世界231都市を、政治、経済、社会福祉、教育、医療、文化、自然など39項目を様々な角度から調査しランク付けを行っています。
左の表は「世界生活環境調査・都市ランキング」ですが、その治安面です。
総合点で10年連続トップだったウィーンは残念ながら治安面では第6位です。
それでもウィーンはベスト10にランクされています。
オーストリアは永世中立国、その首都ウィーンには国連都市があることもその理由のひとつです。
第1位はルクセンブルクですね。
スイスのバーゼル、ベルン、フィンランドのヘルシンキ、スイスのチューリッヒの4都市が第2位です。
スイスの都市が4つもランクされていますが、スイスも永世中立国ですね。
ジュネーブも国連都市がありますから、オーストリアと似たような立場です。
ただ・・・
オーストリアはスイスと違い、EUに加盟していますし、通貨もユーロが導入されていますので、スイスのような孤立国ではありません。
治安がいいということは旅行者にとっても非常に嬉しいことですね。
御興味があれば以下マーサーのサイトを御覧下さい。
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
強制送還の数(2018年度)
ウィーンは一昨日6月4日に日中今年になって初めて30℃を超えました。
昨日も30℃あり、夏の空気が漂っています。
しかし、今日は天気が崩れるようで、朝は昨日よりも涼しく、日中25℃には達しない予報です。
さて、ウィーンはヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の居城であり、かつての"帝国の都"を今でも偲ぶことができます。
ハプスブルグ帝国時代は多民族国家であり、日本では考えることができない10以上の言語を持った民族から成り立っていました。
そのため帝国が解体し、オーストリア共和国となってもその首都ウィーンには今でも多くの外国人が住んでいます。
先日ウィーンに住む外国人はどのくらいかというデータを紹介しました。
さらに規制が厳しくなり数はぐっと減ったとは言え、難民の申請があり、審査の結果が出るまではオーストリアのどこかに滞在することになります。
難民として認められなければ強制送還ですが、難民以外でも滞在許可等の問題などで強制送還される人も多くいるようです。
今日は去年2018年度にどこの国籍の人がどのくらい強制送還をされているかのデータを紹介します。
右の表を御覧下さい。
こちらはÖ1が発表した2018年度のAbschiebestatistik(強制送還の統計)2018のベスト10です。
どの国からの人々がどのくらい強制送還されているかということなのですが、ランクされた国を見ると意外なことに難民が多く来る国ではなく、かつての共産圏・・・旧東欧諸国が多いことがわかります。
スロヴァキアがトップで578人も強制送還されています。
アフガニスタンは8位で187人です。
| 1. スロヴァキア | 578 |
| 2. セルビア | 535 |
| 3. ハンガリー | 450 |
| 4. ルーマニア | 382 |
| 5. ナイジェリア | 305 |
| 6. ポーランド | 266 |
| 7. ジョージア | 218 |
| 8. アフガニスタン | 187 |
| 9. ロシア | 130 |
| 10. アルバニア | 115 |
スロヴァキアの首都ブラティスラヴァはウィーンからたったの65kmですし、旧共産圏と言えども今はEUにも入っていて、通貨もユーロが導入されていますね。
日本からの団体ツアーでもかなり頻繁にブラティスラヴァに寄って行きますね。
2位がセルビア、3位がハンガリーです。
オーストリア政府のBMI (Bundesministerium für Inneres)によると、強制送還される45%はヨーロッパ諸国ということです。
これは滞在許可などが下りなかったり、こちらで事業が認められなかったりなど色々な要因があると思います。
旧東欧圏はEUに入っている国が多くなっても、オーストリアと比べればまだまだ物価的には安いので、収入も違います。
難民の強制送還はむしろここ数年で目立ち始めたわけですが、実際はヨーロッパ諸国からの人の方が多く強制送還されてるようです。
Orthodoxe Kirche (正教会)の割合
オーストリアはキリスト教ローマカトリックが国内全体の80%を下りません。
これはヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ家がカトリックを守って来たことにも大きな関係があるでしょう。
ローマカトリックはかなりの矛盾を修正し、教理を作り上げて現在に至っていますが、絵画、建築、音楽などの分野で素晴らしいものを生み出しています。
でもキリスト教の本来の性格はOrthodoxe Kirche と言われる東方正教会が流れを受け継いでいます。
キリスト教の成立も参照して下さい。
ローマのコンスタンティヌス帝が313年ミラノ勅令により、キリスト教を公認し、コンスタンティヌス帝はその後まもなくの330年、都をローマから、ビザンティオンに移します。
この街は現在のイスタンブールで、当時コンスタンティノープルと呼ばれました。
ここを首都として、更にキリスト教が発展をしていき、392年には、テオドシウス帝はキリスト教をローマ帝国の国教とします。395年、ローマ帝国が西と東に分裂し、西ローマ帝国は476年、ゲルマン民族によって崩壊しますが、東ローマ帝国は、オスマントルコにやられる1453年まで、1000年以上も続き、ある意味では正統にキリスト教を守っていきました。
昔の名称ビザティオンから東ローマ帝国は、ビザンティン帝国とも言われますね。
なのでそこからの基本となるキリスト教は東方教会、俗にオーソドクスと呼ばれ、現在のギリシャ正教に通じる流れが形成され、いわゆる正統派としてキリスト教の習慣を受け継いでいるわけです。
今日はこの正教会がどのくらい分布しているかをちょっと見てみましょう。
| イスタンブール | 3.500.000 |
| アレクサンドリアとアフリカ | 350.000 |
| アンティオキアと中東 | 750.000 |
| エルサレム | 260.000 |
| モスクワとロシア | 90.000.000 |
| セルビア | 8.000.000 |
| ルーマニア | 20.000.000 |
| ブルガリア | 8.000.000 |
| ジョージア | 3.500.000 |
| キプロス | 500.000 |
| ギリシャ | 9.000.000 |
| ポーランド | 800.000 |
| アルバニア | 260.000 |
| チェコ、スロヴァキア | 100.000 |
コンスタンティノープルはEhrenoberhaupt(エーレンオーバーハウプト)と呼ばれ、正教会の総本山です。
正教会ではローマ教皇に当たるのがエキュメニカル総主教と呼ばれますが、ローマ教皇のように絶対的権力はなく、名誉的なものです。
原始教会、初期キリスト教時代に地中海沿岸には5つの総主教座がありましたが、その内エルサレム、コンスタンティノープル、アンティオキア、アレクサンドリアの4つは現在でも総主教庁として正教会の中心的な役割を担っている宗教都市です。
正教会はこれらの街界隈に多く分布しています。
ギリシャ正教会やロシア正教会、セルビア正教会、ルーマニア正教会、ブルガリア正教会などが属します。
世界の3大宗教と言えばキリスト教、イスラム教、ヒンズー教であり、キリスト教の3大宗派と言えば、
ローマカトリック、プロテスタント、正教会となります。
比率的にはカトリックが圧倒的に多いですが、正教会の方が、本来のキリスト教の性格を受け継いでいます。

こちらはおまけです。
ギリシャエーゲ海サントリー二島のフィロステファニにある教会です。
オーストリアに住んでいる外国人の国籍
先日はオーストリアに住んでいる外国人の数についてちょっと紹介しました。
オーストリアはハプスブルグ帝国時代からの多民族国家のカラーが現在でも浸透しています。
中でもかつての帝国の都であるウィーンにはオーストリア全体の40%にも上る外国人が住んでいます。
2018年2月26日付でウィーンに住む外国人はどの国からどのくらい?というタイトルでデータを紹介しましたが、今日はオーストリア全体です。
右の表は2018年12月31日の新聞に掲載されたオーストリア外務省が発表した2018年度の統計です。
オーストリア全体ではドイツ人が一番多い外国人ということになります。
もっとも言葉がドイツ語ですし、ドイツもEU諸国ですから滞在条件は日本人よりもはるかに楽でしょう。
2位がボスニア・ヘルツェゴビナです。
ここに挙げた国を見てもわかる通り、旧東欧圏の国が半数以上を占めています。
オーストリアはそれなりに物価が高く、そこそこ裕福な国で、すので、ここで働こうと思う人は多いのかもしれません。
このデータはあくまでもオーストリア政府から正当に居住を認められている数です。
| ドイツ | 227.790 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 196.752 |
| トルコ | 160.313 |
| セルビア | 141.898 |
| ルーマニア | 113.267 |
| ハンガリー | 75.787 |
| ポーランド | 75.069 |
| シリア | 46.968 |
| クロアチア | 45.240 |
| アフガニスタン | 44.356 |
| スロヴァキア | 41.507 |
| チェコ | 37.807 |
| ロシア | 34.380 |
| イタリア | 33.264 |
| コソボ | 32.339 |
| ブルガリア | 27.426 |
| マケドニア | 26.114 |
| スロヴェニア | 23.771 |
闇滞在している人も多いでしょうから、そうなると正確な数はわかりません。
例えば中国人はウィーンだけでも数万人以上滞在していると言われていますから、オーストリア全体ではここに挙げた数字よりも多くなる可能性があります。
そうは言ってもオーストリアは、第三国から来た人が観光以外で滞在するには滞在許可などを取得することがかなり大変です。
オーストリアに住んでいる外国人の数(2018年度)
オーストリアはウィーンを含めて9つの州から成り立ち、北海道よりもちょっと広いぐらいの国にもかかわらず、それぞれの州に個性があり、"旅"の全ての魅力を持っている美しい国です。
ヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の拠点であり、伝統的に他民族国家のカラーを持っていましたから、今でも多くの外国人(オーストリアから見ての)が住んでいます。
特にウィーンはかつての帝国の都を今でも偲ばせる街で、多くの外国人が住んでいます。
大多数がヨーロッパ人の顔立ちをしてドイツ語を話しているので、観光としてウィーンを訪れた方には、誰がオーストリア人で、外国人であるということをすぐに判別するのは難しいでしょう。
私も日本人ですからここでは外国人ですが、いわゆる永久ビザを持っていますので、オーストリア人同様、税金、社会保険、年金を納めています。
2018年2月26日付でウィーンに住む外国人はどの国からどのくらい?というタイトルで、ちょっとした統計を御紹介しました。
今日はオーストリア全体での外国人の数と国籍の新しい数を紹介します。
右の表は2018年の大晦日に新聞に掲載されたオーストリア外務省による統計です。
外国で生まれ、オーストリアに住んでいる数と全体の割合を示しています。
約170万人の外国で生まれた外国人がオーストリアに住んでいて、ウィーンは679.616人と全体の40%になり、圧倒的に外国人が多いことになります。
2位はÖberösterreichの225.567人、3位はNiederösterreichです。
これはオーストリアの地理的状況を知っていると理解できる結果でしょうか。
| Wien | 679.616 | 40% |
| Niederösterreich | 210.865 | 12.4% |
| Oberösterreich | 225.567 | 13.3% |
| Salzburg | 104.206 | 6.1% |
| Tirol | 137.919 | 8.1% |
| Vorarlberg | 81.485 | 4.8% |
| Steiermark | 155.456 | 9.2% |
| Kärnten | 69.259 | 4.1% |
| Burgenland | 32.750 | 1.9% |
オーストリアの概要を見て下さい。
この3つの州はオーストリアの北側に位置しています。
隣接している国はドイツ、チェコ、スロヴァキアです。
EUという枠の自由性もあると思いますが、彼らの先祖などが帝国時代から居住していたことにも関係があります。
オーストリアでは全人口約882万人の内、約160万人が外国人ということになります。
私の場合はウィーンが大好きだったので、ここに住み着きました。
オーストリアは国が小さいこともあり、EU諸国以外からの外国人が観光以外の目的で滞在するのは大変です。
子供におこづかいをいくら渡す?
皆さんはお子さんに定期的におこづかいを渡していますか?
またいくらぐらいでしょうか?
それぞれの家庭によって、1週間に1回決められた日に、1ヶ月に1回、もしくは不定期・・・色々あると思います。
こちらではどうでしょうか?
オーストリアでは法律的に子供におこづかいを与えるということは定義されていませんので、子供達は両親との話し合いで決めて下さい・・・ということです。
ただ、定期的におこづかいをもっらている子供は、社会でのお金の価値、感覚を早く理解できるので良しとされています。
右の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at,
(日本労働組合総連合会のような機関)2018年11月号に掲載されていたデータです。
1ヵ月に1回が43%、1週間に1回が25%で全体の7割弱にのぼります。
| 1ヶ月に1回 | 43% |
| 1週間に1回 | 25% |
| 毎日 | 4% |
| 無し | 13% |
| 不定期 | 15% |
実際にいくらおこづかいをあげているのでしょうか?
右の表は1ヶ月のおこづかいです。
実際の統計の右側にはオーストリアでの推奨金額を記載しています。
オーストリアの物価水準からすると少ない気がします。
| 11歳 | 12ユーロ | 14ユーロ(推奨) |
| 12歳 | 20ユーロ | 20ユーロ(推奨) |
| 13歳 | 20ユーロ | 20ユーロ(推奨) |
| 14歳 | 25ユーロ | 35ユーロ(推奨) |
表の年齢は11歳からですが、こちらは10歳で小学校が終わるのでということですね。
うちは子供が小学校に入ってからずっと1週間1回、決めた曜日にあげてます。
ちなみにどんな物におこづかいを使うのでしょうか?
この統計によると
●おやつ、ファーストフードが54%、
●友達、映画、コンサートが49%
●スイーツ 46%
●服 43%
●贈り物 38% となっています。
ウィーン 国別での観光収入 (2018年)
昨日のウィーンは日中の気温が20℃に達し一挙に春が来たかんじでしたが、今日は曇り模様、気温も7℃ぐらいと肌寒さを感じます。
さて、先日ウィーンの2018年度の宿泊数を話題にしました。
ドイツからの観光客が圧倒的に多く、2位は地元オーストリアからでした。
2018年度はドイツだけで3.158.000、2位オーストリアは2.997.000で共に100万を余裕で超えています。
今日はどの国がどのくらいの売り上げがあったかを紹介します。

上の表は前回同様、ウィーン観光局(ウィーン市MA23)から送られてきた2018年度1月~11月の国別売り上げベスト10です。
1位はもちろんドイツで144.049.000ユーロ、2位オーストリアは128.586.000ユーロと他国を大きく引き離しています。
宿泊数の順番と同じだと思いきや、中国がスペインを抜いて6位となっています。
ヴィトンの店などでは中国人が多く並んでいるのが目立ちます。
日本はもう物欲というのが薄れていて、物を買うというよりも旅行そのものにお金をかける傾向に変わっていると思います。
宿泊数ではフランスが8位でしたが、売り上げでは10位となっています。
この数字を見るとウィーンは観光都市というイメージがあります。
もちろん観光も重要な産業ですがそれが全てではありません。
オーストリアは色々な産業があり、それなりの経済国です。
先日ウィーンは世界で一番住みやすい街に10年連続第1位となりました。
10年連続! ウィーンは世界で一番住みやすい街(2019年)
ウィーンはヨーロッパ文化が凝縮したかつての帝国の都です。
荘厳な建造物が多く建ち並び、豊かな緑に囲まれ、上品で高貴な一面もありながら、どこかいい意味での人間らしいいい加減さが感じられる街で、とても住みやすいと思います。
私はウィーン以外に住むことは考えられないほど、ウィーンの魅力に取りつかれてしまいました。(笑)
実際にウィーンの生活のクオリティーが高いことは世界的に知られています。
さて、今年もウィーンの街は世界で一番住みやすい街に選ばれました。
10年連続で11回目です!
| 1. | ウィーン(オーストリア) |
| 2. | チューリッヒ (スイス) |
| 3. | バンクーバー(カナダ) |
| 3. | ミュンヒェン (ドイツ) |
| 3. | オークランド(ニュージーランド) |
| 6. | デュッセルドルフ (ドイツ) |
| 7. | フランクフルト (ドイツ) |
| 8. | コペンハーゲン(デンマーク) |
| 9. | ジュネーヴ(スイス) |
| 10. | バーゼル(スイス) |
左のランキングを見て下さい。
これはMERCER (マーサー・・・世界最大の組織・人事マネージメント・コンサルティング会社)が毎年行う統計で、世界231都市を、政治、経済、社会福祉、教育、医療、文化、自然など39項目を様々な角度から調査しランク付けを行っています。「世界生活環境調査・都市ランキング」です。
ウィーンが1位です!!
ウィーンは特に文化、教育、住居、医療面などで高得点で、オーストリアは昔から芸術・文化の水準が高かったことがうかがえます。
治安面も重要です。
ウィーンの治安はよく、パリなどとは比べ物になりません。
オーストリアは永世中立国、その首都ウィーンには国連都市があることもその理由のひとつです。
ベスト10にランクされた街は、バンクーバーが去年の5位から3位に上がりオークランド、ミュンヘンと肩を並べ、コペンハーゲンが9位からジュネーヴを抜いて8位に、シドニーがベスト10から陥落した以外は去年と同じです。
ベスト10の中ではヨーロッパの街が8つと大半です。
私はここにランクされたヨーロッパ全ての街を見てますが、これには納得できます。
ちなみに今年のマーサーによれば日本の東京、神戸は49位、横浜55位、大阪58位です。
アジアでのトップはシンガポールの25位です。
最下位231位は10年連続でイラクのバグダッドでした。
私はウィーン大好きですから、この結果はプライベート、仕事領域を含めて大変嬉しいですね。
実際に生活をしていると、もちろん全てがいいことだけではありませんが、しかしそれを含めてもウィーンは住みやすい街であることを実感しています。
御興味があれば以下マーサーのサイトを御覧下さい。
https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
ウィーンの宿泊数(2018年度)
ウィーンはヨーロッパで一番長く続いたハプスブルグ王朝の居城があり、そのハプスブルグ家の下に歴代神聖ローマ帝国の皇帝、ローマ王、ドイツ王などの称号があったことから、"皇帝の居城"として永らく栄えてきました。
そこで他のヨーロッパの街とは歴史的立場も違っていて、様々な物がウィーンに集まり、切磋琢磨されながら洗練されていきました。
まさに"ヨーロッパ文化が凝縮した街"となったわけです。
よく言われる"音楽の都"なんてほんの一部分に過ぎなかったわけです。
ウィーンの街の奥深さを知った方は、繰り返し来られます。
団体ツアーのお客様でももう3回目とか4回目の方も多く、私のホームページからお声をかけて頂いたお客様の中にも、ウィーンに繰り返し来られる方も多くいらっしゃいます。
そうです。それだけウィーンは魅力的な街なのです。
さて、今日は去年2018年度のウィーンの宿泊数を国別で紹介します。

上の表はウィーン観光局から送られてきた2018年度の宿泊数のベスト10です。
この統計はウィーン市MA23からのもので、中々興味深いものがあります。
それぞれのグラフの一番右にある数字は前年度との伸び率です。
1位はドイツで3.158.000の宿泊数です。
お隣ドイツはオーストリアでは常連さんで、毎年最も多くの方が訪れます。
ウィーンの街中を歩いていると、"ドイツのドイツ語"がよく聞こえてきますね。(笑)
ドイツが他の国と比べると圧倒的に多いですね。
2位は地元オーストリアです。
ウィーン以外に住んでいる地元オーストリア人にとっても、やはりウィーンは魅力的な街です。
以前は私達日本もベスト10の8位~9位あたりに毎年ランクしていたのですが、中国、ロシアの勢いに負けて、ベスト10圏外にはじき出されてしまいました。
日本からのお客様が少なくなったわけではありません。
日本からのお客様は極端に増えることもなければ、また逆に少なくなることもなく非常に安定しています。
お陰様で私もいつも忙しいです。
それ以外ベスト10にランクする国はヨーロッパのイギリス、イタリア、スペイン、フランスなどの常連と、アメリカも去年は7%も伸びました。
この結果は地元では喜びの高評価となっています。
オーストリア 交通事故での死亡者数
ウィーンは公共交通機関が非常に発達しているので、ウィーンに住んでいる限り車が無くても不便さは感じないでしょうか。
にもかかわらずウィーンは車の所持率がかなり高い街と言われています。
ウィーンは415km²とかなり広い街ですから、実際には車があれば便利ですし、ウィーンの郊外にも魅力的な場所が多くあり、何と言ってもオーストリアはアルプスを大きく横たえて持っている国で、郊外に美しい長閑な風景が広がっていますので、車はある意味では必需品とも言えます。
ウィーンは189万の人口の街にもかかわらず、車での交通事故の死亡者が以外と少ないです。
今日はオーストリアにおいての交通事故の死亡者数を見てみましょう。
| 過去10年間 | Wien(ウィーン) | Niederösterreich | Burgenland | オーストリア全体 |
| 2009 | 32 | 189 | 24 | 633 |
| 2010 | 29 | 163 | 20 | 552 |
| 2011 | 22 | 159 | 21 | 523 |
| 2012 | 24 | 145 | 30 | 531 |
| 2013 | 17 | 112 | 17 | 455 |
| 2014 | 21 | 121 | 22 | 430 |
| 2015 | 13 | 131 | 24 | 479 |
| 2016 | 19 | 112 | 19 | 432 |
| 2017 | 20 | 93 | 25 | 414 |
| 2018 | 16 | 99 | 13 | 401 |
上の表はÖAMTC(日本で言えばJAFのようなもの)が毎月発行するauto touring2019年2月号に掲載されていたデータです。
こちらで車に乗っている人であれば誰でも知っているÖAMTCは信頼性があって、多くの人が加盟しています。
私もずっと前からお世話になっています。
過去10年間の交通事故死亡者の統計ですが、明らかに減少しています。
ウィーンは道もそれなりに複雑で、一方通行も多く、路面電車との共存でありながらも去年は16件しかありませんでした。
最も"死亡者数"ですから事故数で言えばもっとあるでしょう。
Niederösterreichはウィーンの外側にあり、オーストリアでは最も広い州ですので、それなりに数が高いですね。
オーストリアの郊外では、街の中に入ればたいてい50km/hですが、街と街を結ぶ国道などでは100km/hで走れる所も多く、夜などは暗いですから事故も必然的に起こるのでしょう。
ちなみにオーストリアでは1972年が統計を取り始めて最も最悪で、2.948人でした。
去年2018年が401人ですから大変少なくなっていることがわかります。
国立オペラ座舞踏会(2019年)
1月6日の聖三王が過ぎるとウィーンの街は舞踏会が至る所で開かれ、それに伴うカレンダーもあるぐらいです。
舞踏会の中で最も有名なのは国立オペラ座の舞踏会(Opernball・・・オペルンバル)です。
この舞踏会は復活祭がいつ来るかによって開催される日が毎年変動し ます。
謝肉祭の最高点である火曜日(Faschingsdienstag)の前の週の木曜日と決め られていますので、今年は2月28日の木曜日・・・つまり今日ということになります。
去年は2月8日でしたので今年はかなり遅いですね。

右の写真は2月25日の12:00頃です。
国立オペラ座正面入り口で、ちょうど舞踏会の正面入り口の構築が始まっています。
毎年恒例のこの正面入り口セットが出来上がっています。
でも国立オペラ座の中ではこの時点ではまだ通常通りオペラが上演されています。
相当大掛かりな作業で、どこから見ても目立ちます。
正面入り口だけではなく、後ろの搬入口や横の部分でも作業が行われています。
<国立オペラ座舞踏会の歴史>
国立オペラ座舞踏会は、有名なウィーン会議(1814-1815) の時からだとされていますが、場所は宮廷関係の劇場ではなかったようです。
そもそも国立オペラ座自体、1868年に完成していますからウィーン会議の50年以上後ということになります。
その1820~30年代、この帝国の都ウィーンでは数々の大小の舞踏会が開かれるようになっていました。
ヨーゼフランナー、ヨハン・シュトラウス(父)が活躍する時代ですね。
それから王宮のレドゥーテンザールで開かれるようになっていきますが、1848年の革命時からはしばらく静かになります。
1862年Theater an der Wienが舞踏会開催を許されました。
1869年にリンク道路の現在の国立オペラ座を宮廷が使い始めますが、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世がここでの舞踏会を拒んでいたため、1870年に完成したニューイヤーコンサートで有名な楽友協会ホールで "Ball in der Hofoper"として開かれました。
1877年に皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が賛同し、初めて現在の国立オペラ座の一角で祭典が行われました。
ハプスブルグ帝国崩壊後、オーストリアが共和国となり、すぐに帝国時代の懐かしさから1921年にはすでに舞踏会が開かれました。
1935年には「Wiener Opernball」という名で開かれ、1939年第2次世界大戦前日の夜、最後のオペラ座舞踏会が開かれます。
戦後壊された国立オペラ座が1955年に修復され、1956年2月9日に現在のオーストリア共和国の初めての国立オペラ座舞踏会が開かれ、現在に至っています。
つまり今年は現在のオーストリアになって63回目ということですね。
国立オペラ座舞踏会は世界各国の著名人、貴賓が集まり、男性は燕尾服、女性はイブニングドレスと決められています。
<国立オペラ座舞踏会についての色々な数字>
ゲストの数は5.150人、146万人が国立オペラ座舞踏会のテレビ中継を見ている、144組の社交界デビュー、会場構築時間は350人の専門作業員、150人のアルバイトで30時間、解体時間は21時間、50の業者、総費用140万ユーロ、46.000以上のグラス、1.000枚のテーブルクロス、4.000のナイフとフォーク、1.300のSekt、ワイン900本、ビール900本、150人の音楽家・・・。
国立オペラ座の普段の運営もすごいものがありますが、たった1回のこの舞踏会でも物凄いものを感じます。
さて、気になる今年の料金はというと・・・
| 入場料 | EUR 315,- |
| ボックス席(ロジェ) | EUR 23.600,- |
| 舞台側ボックス席 (大) | EUR 23.600,- |
| 舞台側ボックス席 (小) | EUR 13.300,- |
| 舞台側ロジェ テーブル付き | EUR 11.500,- |
|
6人用テーブル |
EUR 1.260,- |
| 4人用テーブル | EUR 840,- |
| 3人 テーブル(相席) | EUR 630,- |
|
2人 テーブル (相席) |
EUR 420,- |
| 6階 4人用テーブル席 | EUR 420,- |
| 6階 2人用テーブル(相席) | EUR 210,- |
今年の料金は去年2018年度と比べると値上がりしています。
去年は入場料290ユーロでしたが、今年は315ユーロ、一番高いボックス席が去年は20.500ユーロでしたが、今年は23.600ユーロとなっています。
一番高いボックス席(ロジェ)は12人までが入れます。
それぞれの料金は入場料とは別で、飲食も別です。
入場料だけでも315ユーロですから国立オペラ座の最高額の座席よりも高いですね。
年間を通して数え切れないぐらい国立オペラ座の内部案内をしていますが、毎年思いますが舞踏会だけは別世界です。
国立オペラ座舞踏会の様子のビデオが見られますので、興味ある方は御覧下さい。
https://www.wiener-staatsoper.at/opernball/
※国立オペラ座オフィシャルサイトより
ウィーンの上水道について
ウィーンの上水道はアルプスの湧水であることは御存知でしたか?
ウィーンから90kmほど離れたアルプスの一角から4本の水道管によって直接ウィーンに水が供給されています。
ちなみにその水源を見学することができます。
ウィーンは家庭の水道をひねるとエビアン水が出て来る街と言ってもいいでしょう。
その質が高い水道水がまた美味しいカフェを生み出すわけですね。
EU諸国の中ではオーストリアの水質はトップクラスです。
ウィーンの街にはその上水道の象徴的なものとして、Hochstrahlbrunnen(ホッホシュトラールブルンネン)があります。
さて今日はそのウィーンの上水道についてちょっとしたデータをお届けしましょう。
| 水道水を定期的に飲んでいるオーストリア人 | 89% |
| 水道水の質が非常にいいと考えている人の割合 | 90% |
| ウィーンにおける水道管の長さ | 3.000km |
| 泉などの公共の水飲み場 | 900 |
| 水道水1リットルの料金 | 0.15~0.30セント |
| ミネラルウォーター1リットルの値段 | 0.25~0.85ユーロ |
上の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at,
(日本労働組合総連合会のような機関)2018年10月号に掲載されていたデータです。
オーストリアではほぼ9割の人が水道水を定期的に飲んでいて、質の良さを意識しています。
私も毎日水道水は飲んでいますね。
水道をひねると水がすぐに冷たくなります。
右の表は1人が1日に利用する水道水の量です。
合計すると130L・・・約40セントということになりますね。
このデータはあくまでも平均ですから水道水の使用量には当然個人差があります。
しかし、中々興味深いデータです。
ウィーンの上水道はEU圏だけでなく、世界でもトップクラスの質の良さです。
| 1人が1日に使う水道水の量 | |
| 入浴(シャワー、浴槽) | 44L |
| トイレ | 40L |
| 洗濯 | 15L |
| 掃除、ガーデニングなど | 13L |
| 手洗い | 9L |
| 食器洗い | 6L |
| 料理 | 2L |
| 飲料 | 2L |
ウィーンは森の都・・・どのぐらいの街路樹がある?
ウィーンは"森の都"と形容されていますが、ウィーンはヨーロッパの街の中で、街の広さに対して緑の比率が最も高いです。
ウィーンの中心のリンク道路沿いだけでも6つの公園があり、それ以外にも様々な公園、庭園、並木、街路樹が多く見られます。
ウィーンの街を歩けば、この街は緑が豊かだな~ときっと思われるでしょう。
しかし、その広大な緑を囲むもっと大きな緑がウィーンの森です。
今日はウィーンの街にはどのぐらい多くの街路樹が植えられているのかを簡単にまとめてみます。
ウィーン市の面積は約415km²、人口約187万人、東京と同じ23区で成り立っています。
東京は市がたくさんありますが、ウィーンはウィーン市が23区で成り立っています。415km²と言えば、かなり広い街であることがわかります。
見所も中心界隈だけでなく、外側にも多く点在しています。
ウィーンの街には約87.000本の街路樹が植えられていますが、以下簡単にまとめてみました。
右の表はArbeiterkammer・・・略してAK https://www.arbeiterkammer.at/index.html(日本労働組合総連合会のような機関)2018年11月号に掲載されていたデータです。
右側はウィーンのそれぞれの区です。
| 8.000本以上 | 22,2 |
| 6.000~8.000 | 10,13,21,23 |
| 4.000~6.000 | 11,12,14,19 |
| 2.000~4.000 | 1,15,16,17,18,20 |
| 2.000以下 | 3,4,5,6,7,8,9 |
昨日はバレンタインデー
昨日の2月14日はバレンタインデーでした。
私が小学校の頃からこの習慣はかなり広がっていましたが、女の子が男の子にチョコレートを贈る=好きな気持ちを告白する・・・というのが一般的だと思います。
こちらでもバレンタインデーの習慣はありますが、女性からではなく、男性から女性にというのが一般的です。
バレンタインデー・・・こちらではValentinstagと呼ばれ、聖人のヴァレンティヌスの日ということになります。
ヴァレンティヌスはドイツ語では"Valentin"、彼は3世紀頃のキリスト教の聖職者で、269年2月14日に亡くなったということになっています。
結婚を禁止されたローマ兵士達のために、キリスト教的結婚式を挙げたことによりローマ帝国から迫害されます。
よく知られた伝説のひとつで、彼が迫害され、捕らえられている間に彼が面倒を見ている盲目の娘の目を直したそうです。
彼の死刑の直前にその娘に別れの手紙を書き、„Dein Valentin“と署名したそうです。
ヴァレンティヌスを祝う習慣は14世紀に宮廷で大流行りとなり、頂点を迎えました。
18世紀にイギリスで愛し合う2人がお互いにそれを表現し、花とお菓子、クリスマスカードのようにカードを贈る習慣が生まれました。
私の子供の頃は女性がチョコレートを贈る習慣でしたが、こちらでは前述したように男性が女性に贈るのが一般的ですが、どのような物が好まれているのでしょうか?
右の統計は昨日の新聞ÖSERREICHに掲載されていたものです。
1位は圧倒的に花です。
花屋さんでは猛烈な勢いでバラを中心に買われていて、午前中にはもう赤いバラが売り切れた店がある程です。
4位の無形は色々な可能性があります。
例えば普段料理を作ってくれているから、今日は僕が作るから・・・とか、掃除を代わりにするからとかそのようなことです。
まぁ~ちょっとした気遣いでしょうね。
聖ヴァレンティヌスが男性であったことなどが理由で、こちらでは男性が女性に気持ちを伝えるわけですね。
| 1. 花 | 49% |
| 2. チョコレート | 22% |
| 3. レストランでの食事 | 16% |
| 4. 無形 | 13% |
| 5. 商品券 | 12% |
| 6. 劇場、映画 | 11% |
| 7. 香水 | 10% |
| 8. アルコール | 10% |
| 9. アクセサリー | 8% |
| 10.個人的な物 | 8% |
オーストリアではこのバレンタインデーにおける経済効果は120.000.000ユーロと言われています。
因みに1人当たり平均58ユーロの予算という統計です。
ウィーンで3人に1人はシングル・・・Partnerschaftについてのちょっとした統計
家族といるのが一番幸せ?
恋人と一緒にいるのが幸せ?
好きなことができることが幸せ?
お金がいっぱいあることが幸せ?
社会で自分が貢献できることが幸せ?
幸せの価値観は人によって違います。
今日はオーストリアでのPartnerschaft・・・夫婦関係、恋人関係などいわゆる特定のパートナーがいる場合のちょっとした傾向を見てみましょう。
これは"Parship"が18歳~69歳を対象に去年12月初旬に発表した統計です。
オーストリアでは3/4が特定のパートナーとの関係にあり、その半分の人達がその関係に満足しているということです。
オーストリアでは440万人・・・72%がすでに特定のパートナーとの関係にある。
シングルが一番多い街はウィーンで、36%。
全体では49%がパートナーとの関係に満足している、しかしウィーンでは37%。
余暇でパートナーと一緒にいる割合は22%、多くを一緒に過ごすが別々にもの割合が58%。
恋愛関係の長さが5年以内が27%、20年以上が41%。
上記の20年以上の半分がザルツブルク州とケルンテン州に住んでいる。
右の表は主だったテーマに対してお互いの意見が一致している割合を示しています。
子供が欲しいというテーマではお互いの希望が一致している割合は64%に上ります。
家族の価値、夫婦関係もやはり大事のようです。
逆に食事はそれぞれ好みがあることを示していますね。
うちは家族の価値、子供の教育などは頻繁に出て来るテーマですね。
夫婦関係、恋人関係といった特定のパートナーがいる方はどうお考えになりますか?
| 子供が欲しい | 64% |
| 家族の価値 | 58% |
| 夫婦関係 | 55% |
| ペット | 51% |
| 旅行 | 49% |
| SEX | 47% |
| 政治 | 42% |
| 子供の教育 | 39% |
| お金 | 35% |
| 清潔性 | 30% |
| 食事 | 27% |
ヨーロッパでもインフルエンザが流行っている
日本でインフルエンザの流行が過去患者数が過去10年で最大となり、2019年1月21日~1月27日(2019年第4週)の推定患者数は約228万人に上っているようです。
インフルエンザはインフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、一般的に例年11月下旬から12月上旬にかけて始まり,1月下旬から2月上旬にピークを迎え,3月頃まで続きます。
こちらヨーロッパでもインフルエンザは蔓延していて、このまま行けばオーストリアでも55万人が感染するのではないか・・・と1月29日の新聞に掲載されていました。
インフルエンザはドイツ語では"Grippe"(グリッペ)と呼ばれています。
今日はこのインフルエンザの話題をお届けしましょう。
1月の4週目はオーストリアでは5万人がインフルエンザでベットに横になっていると報道され、その数は日ごとに増えているようです。
ケルンテン州では去年よりもすでに多い患者数として社会保険庁が発表されています。
このペースで行けば前述したようにオーストリアでは55万人がインフルエンザに感染すると見込まれ、その内約1.000人が死亡するだろうと言われています。
この現象はオーストリアだけではなく、他のヨーロッパ諸国でも同じで、ドイツではすでの20人が死亡し、イギリスでは26人が死亡しています。
ウィーンの学校でも、オーストリア政府から感染を抑えるために具合が悪い子供達を無理に登校させないように・・・との呼びかけもされています。
インフルエンザにかからないように予防接種があるわけですが、このインフルエンザの予防接種を受けている人がヨーロッパレベルで見るとオーストリアでは以外と少ないようです。
オーストリアは医療レベルが高い国ですが、インフルエンザの予防接種に関しては全体でたった6%しか受けていないということです。
他のヨーロッパ諸国はどうかというと・・・
右の表はヨーロッパ諸国でのインフルエンザの予防接種を受けている人の割合です。
イギリスは10人に7人の割合で予防接種を受けていて、他の国よりもはるかに比率が高いですね。
2位がスペインの56%、3位がアイルランドの54%となっています。
それから見るとオーストリアの6%は非常に少ない割合ですね。
これはウィーンで長く生活をして、近所付き合いをしている私は理解できることで、インフルエンザに限られることではありませんが、このような予防接種に慎重になっている親御さんが多くいます。
| イギリス | 71% |
| スペイン | 56% |
| アイルランド | 54% |
| イタリア | 50% |
| フランス | 50% |
| スウェーデン | 49% |
| フィンランド | 47% |
| デンマーク | 41% |
| ルクセンブルク | 38% |
| ドイツ | 35% |
絶対にうちの子には予防接種はさせない・・・という家庭も意外と多くあります。
もしかしたら私が住んでいるウィーンのこの界隈だけのことかもしれませんが・・・いや、そうではないと思います。
私はお陰様で元気に仕事をしていますが、仕事でよく行くシェーンブルン宮殿とか、美術史博物館の係がインフルエンザで休んでいる・・・ということをよく聞きます。
皆さんも気を付けて下さいね。
難民問題その後 13
去年の11月後半ごろから年末にかけてはクリスマス関係の話題が多くなり、ウィーンのクリスマスの空気を少しでもお伝えできたかなと思います。
クリスマス時期の週末、そして年末から年始にかけてのウィーンは例年以上の混雑で・・・というよりも毎年混雑の度合いが高くなってきているように感じます・・・観光も大変でした。
さて、今日は解決することがない難民問題のその後について状況を簡単にまとめておきます。
難民申請中の彼らもオーストリアで年越しをしたでしょう。
去年2018年の1月~9月に関しての統計を見ると、明らかに難民の流れは大きく減少していて、数から言えば終わったとされています。
この期間に来た難民数は10.413で、2017年と比べると46.3%の減少です。
年の終わりまででは14.000ぐらいということになり、2015年に難民問題が大きく取り上げられた時は90.000でしたからいかに減少してきたかがわかります。
しかし、国内では難民申請をしたその処理・・・つまり難民と認めるか、強制送還をするかが30.000件あり、47.183人がオーストリア政府からの補助で生活をしながら結果を待っています。
この費用も膨大なものがあり、その辺は難民問題その後11を御覧下さい。
右の表を御覧下さい。
シリアが圧倒的に多く、次がアフガニスタンですね。
これを全部足すと前述した10.413人になります。
難民申請をしたからといってオーストリアに残れるわけではありません。
申請後はその人物が本当に難民として正当なのか審査が行われ、難民として認められなければ強制送還となります。
|
難民はどこから来るか? (2018年1月~9月) |
|
| シリア | 2.590 |
| アフガニスタン | 1.570 |
| イラン | 834 |
| ロシア | 727 |
| イラク | 582 |
| その他 | 4.110 |
毎回書いていますが、難民問題は観光や生活には何の影響もありません。
オーストリアの物価は上昇傾向 (2018年8月のデータ)
日常生活ではあまり意識しないのですが、オーストリアは確実に物価が上がっています。
ある時ふと振り返ると、これが数十セントも値上がりしているということがよくあります。
ユーロが導入されたのが2002年ですが、もうすぐ17年経つ今でも、それまでのオーストリアシリング通貨で考える地元の人が非常に多いです。
この品物に~シリングなんて絶対にあり得ない・・・なんてことをよく聞きます。
今年の8月の統計を見ると、インフレ上昇率2.2%です。
以下の表を御覧下さい。
高くなったもの
安くなったもの
| 灯油 | +24.3% |
| ディーゼル | +15.2% |
| ガソリン | +12.3% |
| サラダ | +14% |
| ぶどう | +13.7% |
| もも | +9.1% |
| バター | +6.7% |
| タバコ | +6.0% |
| 家賃 | +3.6% |
| パン | +2.8% |
| ヨーロッパ都市間の飛行機 | -34.8% |
| レモン | -11.4% |
| 眼鏡レンズ | -10.0% |
| 砂糖 | -8.5% |
| デジタルカメラ | -6.1% |
| ガス | -5.7% |
| 携帯電話 | -5.2% |
| 旅行 | -4.6% |
| ピザ | -3.0% |
| ジャガイモ | -2.2% |
上の統計は今年8月のデータです。
燃料がかなり上昇しています。
実際に車に乗っているとガソリン代が結構高くなっていると思います。
ぶどうや桃も高くなっています。
個人的には両方好きなので痛いですね。
バターやパンも高くなっています。
家賃も上昇傾向ですから、オーストリアでの生活はお金がかかります。
逆にヨーロッパ都市間の飛行機がかなり安くなっていますが、日常生活にはあまり関係がないですね。
レモン、砂糖、ジャガイモが安くなっているのがちょっとした救いでしょうか。
去年と比較すると日常生活における通常の買い物では1日平均2.4%の上昇で、週末に車を利用して出かけたりする場合のガソリン代などを含めると5.5%も上昇しています。
オーストリアは一戸建てよりもWohnungen(アパート)が多く売れる傾向
オーストリアは年々物価が少しづつですが上昇しています。
買い物をする時、その都度はあまり意識しなくても、えっ、これってこんなに高かったっけ~、食費にこんなにかかっているの・・・ということがよくあります。
よく見たら値段は同じでも量が少なくなっているということもよくあります。
物価上昇に平行して、住居も高くなっていて、土地の値段や賃貸料も上昇しています。
住居の傾向としては、一戸建てよりもWohnung(ヴォーヌング)がよく売られているそうで、上半期の統計を見ると4%の上昇です。
Wohnungとは、いわゆるアパート、マンションで集合住宅の1室のことを指します。
ある大手不動産会社に統計によれば、2018年上半期だけで26.166のアパートが売られ、去年よりも1.006も多い数となっています。
特に中古アパートを購入する人が多いようです。
さて、今日はオーストリアそれぞれの州のEigentumswohnung(持ち家としてのアパート)の平均価格を見てみましょう。
右の表を見て下さい。
こちらは9月半ばに新聞に掲載された2018年上半期のWohnungの州別平均価格です。
オーストリア全体では1%の上昇に過ぎないのは、中古アパートを購入する人が多いからです。
一番高い所はVorarlbergで、次にSalzburg、Tirol、ウィーンと続いています。
一番安い所はBurgenlandですね。
ここの土地はオーストリア全体的に見て、群を抜いて安く、ウィーンの半額以下ですね。
一戸建てもそうですが、土地の価格が年々上昇していて、住居はかなり高くなっています。
| オーストリア平均 | +1.0% | € 192.475 |
| Vorarlberg | +14.8% | € 265.260 |
| Salzburg | -1.5% | € 224.623 |
| Tirol | +5.8% | € 224.604 |
| Wien | +1.1% | € 221.222 |
| Oberösterreich | +2.9% | € 178.966 |
| Niederösterreich | -3.3% | € 158.713 |
| Kärnten | -11.6% | € 153.807 |
| Steiermark | +2.0% | € 141.745 |
| Burgenland | +5.5% | € 107.811 |
ウィーンの街の郊外では至る所に住宅が建設されているのを毎日見ています。
多くは、一戸建てよりもマンションで、地上階には小さな庭があることが多いタイプです。
え~、ここも住居が建つんだ~・・ということがしょっちゅうあります。
賃貸は馬鹿らしいので、持ち家としてある程度手が届くWohnungを買う人が多い傾向です。
電動キックボードシェアリングの比較
こちらでは子供から大人まで日常生活の中では当たり前のようにキックボードが利用されています。
小さい子供は遊びで乗るでしょうが、社会人が通勤に利用している姿も多く見られます。
ウィーンは9月の終わり頃から電動キックボード(E-Scooter)のシェアリングが始まって、ウィーンの街の絵が少し変わったような気がします。
スマホやiPadのアプリ経由で利用します。
現在では"Bird", "Lime", "Tier"の3社が競合しながら電動キックボードのシェアリングを展開しています。
それぞれどんな違いがあるのでしょうか?
| Lime | Bird | Tier | |
| 完全に充電された状態での走行距離 | 50km | 20km | 15km |
| 最高速度 | 24km/h | 24km/h | 25km/h |
| 何歳から利用できるか | 16 | 18 | 18 |
| どこの区で利用できるか | 1~9 | 1,4,5,6,7,8,9 |
1~9,12,15*,20,22* * (一部の地域) |
| 料金 | 1回 €1、1分 €0.15 | 1回 €1、1分 €0.15 | 1回 €1、1分 €0.15 |
| 製造元 | Segway (USA) | Xiaomi (CHN) | Ninebot (CHN) |
| 利用時間 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~22:00 |
| シェアリング台数 | 300 | 100 | 250 |
| 会社 | San Mateo (CA) | Santa Monica(CA) | Berlin (D) |
| 創立 | 2017年 | 2017年 | 2018年 |
料金は3社共同じで、1回の利用につき1ユーロかかり,1分ごとに15セントです。
完全充電した状態での走行距離はLimeが抜きに出ています。
利用できる区は1~9区が基本ですが、Tierは外側の区でも利用できます。
これは指定された区だけしか走れないのではなく、返却する場所が問題となります。
利用時間もほとんど同じです。
Limeの製造元はSegwayですが、他は中国製ですね。
そういう意味ではLimeの方が安心感があります。
また、シェアリング台数でもLimeが現時点では一番多いです。
私は3つを試したわけではありませんが、この中ではLimeがお勧めです。
ウィーンの観光中にちょっと気分を変えて、電動キックボードで地元の空気を味わうのも悪くないと思います。











