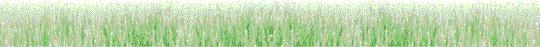2013年 6月
ウィーンによく見られるこの時期の花 22 (ハタザオキキョウ)

こちらはドイツ語でGlockenblume
(グロッケンブルーメ)、
ラテン語ではCampanula,
日本ではホタルブクロ属で
たぶんハタザオキキョウ (Campanula rapunculoides)でしょうか。
原産はヨーロッパで、日本には大正時代に園芸用として入って来たようです。
60~150cmぐらいの高さで、紫色をした釣鐘のような花をつけます。
草原、森、岩などがある地域など標高2000mぐらいまでに見られ、種類も300~500と非常に多いです。
ウィーンの通りの表示
ウィーンの街はぶらぶら歩きに堪える街ですが、通りの入口には必ず通りの名前が記されたプレートが掲げられています。
~straße シュトラーセ ~gasse ガッセ, ~Platz プラッツ ・・・
などがよく見られます。
Straßeはストリートで、Gasse は小道、Platzは広場といった意味でしょうか。
基本的に何かしら意味や言われがあって通りや広場の名称が付けられています。
夏にカロリー消費
先週は1週間ずっと30℃を超えた日が続き、今週月曜日の24日からは12℃に下がって
天気も不安定なウィーンでしたが昨日の木曜日からいい天気が続きそうです。
暑い、涼しいと極端な今年の夏ですが、健康の一貫で何をすればどのくらいのカロリーが30分で消費されるか・・・という記事を地元新聞で見ました。
以下その内容です。
ウィーンによく見られるこの時期の花 21 (モクゲンジ)

これはドイツ語でBlasenesche
(ブラーゼンエッシェ),
ラテン語では、Koelreuteria paniculata、
日本語ではモクゲンジです。
原産は中国で、ヨーロッパには1750年に入ってきました。
日本では日本海側に見られ、15mぐらいになりこの時期には黄色い花を咲かせます。
こちらでは中央ヨーロッパに多く見られ、たいてい公園や道路脇に植えられています。ウィーンにもシェーンブルン宮殿界隈、王宮庭園にも見られ、この時期は背丈が高い木で、黄色の花を咲かせるのはこれしかないので、かなり目立ちます。
写真はウィーンの王宮庭園(Burggarten) のモクゲンジです。
花を咲かせた後、袋のような実をたくさんつけます。
ウィーンの地下鉄(U-Bahn)
ウィーンはドイツ語ですから、地下鉄はU-Bahn(ウー・バーン)と呼ばれています。
U1、U2,U3,U4,U6 の5路線があります。
U5は現在は存在していません。
ウィーンによく見られるこの時期の花 20 (ラベンダー)

これは人気のあるラベンダーです。
ドイツ語でLavendel
(ラヴェンデル),ラテン語では
Lavandulaです。
原産は地中海沿岸とされていて、種類は非常に多く、1mぐらいまでの高さになるものもあります。
標高1700mぐらいまでの日当たりが良く、乾燥した場所が適していますので、こちらヨーロッパの西岸海洋性気候地域には多く見られます。
花の色は、紫、白、ピンクがあり、中でも紫は最もポピュラーです。
庭などにも観賞用として頻繁に見られます。
こちらはうちの庭のラベンダーです。
ラベンダーは鎮痛や精神安定などに効果があると言われています。
お勧め!ウィーンでおいしいスペアリブ!

これはあくまでも個人的にお勧めできるということでちょっとネタにしてみました。
地元で非常に有名な、スペアリブがおいしい店です。
その店の名前は「Zur Alten Kaisermühle」(ツア・アルテン・カイザーミューレ)です。
この店は1893年、Fischerwirt という名でオープンし、Alte Donau(旧ドナウ)沿いに位置し、目の前にはAlte Donauがあり、とてもいい雰囲気です。
ウィーンのパン 「ゼンメル」

地元ウィーンでおそらく
一番有名なパン・・・それは「Semmel (ゼンメル)」
でしょうか。正式にはKaisersemmel
(カイザーゼンメル)で
ここオーストリアのオリジナルです。18世紀の後半1760~1770年頃に描かれた、シェーンブルン宮殿にある絵の中に見られ、マリア・テレジアの頃にはすでにあったようです。
白パンのこのゼンメルは80gぐらいが最大で、小さいものもあり、オーストリアのホテルやペンションでの朝食や、地元レストラン、街中のソーセージスタンド、あらゆる所で見られます。
地元ではこのゼンメルがスープといっしょに出されれば、ちぎって食べるのが一般的ですが、バターやジャム、ハムなどをのせて食べる場合は、
横からナイフを入れて、ぐるりと回しながら半分に切って食べます。
この写真は、ANKER アンカーというオーストリアでは誰もが知っているパン屋さんの朝食です。この店はたいてい注文してからお店の人が半分に切って渡してくれます。
このゼンメルに限らずクロワッサンやその他のパンでも地元の人達はナイフを入れて半分に割って食べている光景をしょちゅう見かけます。
ゼンメルはおそらく一度見たら忘れることがないと思いますし、
焼き立てはとてもおいしいです。
ウィーンに何回も来られる方は懐かしさすら感じる・・・地元生活に密着したパンです。
ちなみにオーストリアのドイツ語は、"S"の後に母音が来た時には濁らない発音をするので、こちらではゼンメルではなくてセンメルです。
ウィーンによく見られるこの時期の花 19 (アメリカキササゲ)

こちらはドイツ語でTrompetenbaum
(トロンペーテンバウム),
ラテン語では
Catalpa bignonioides,
日本ではアメリカキササゲ
(アメリカ木大角豆)です。
日本には明治時代末期に入って来たそうです。
原産は北アメリカで、
高さは20mぐらいまで、30cmぐらいまでの細長いさやのようなものがぶら下がっているのが見えます。
中央ヨーロッパでは観賞用として、公園等に多く見られます。
ウィーン シティバイク (CITYBIKE)

ウィーンの街には何年も前から誰でも借りられる自転車「CITYBIKE WIEN」があります。
当初は登録もなくタダで誰でも乗れました。
しかし家に乗って帰る人や、ウィーンの自転車が何とベネチアにも出没したり、国境を越えて持って行く人がいたため、改良が重ねられ現在は登録制になってこれが定着しています。
登録は最初の一回だけで、ターミナルでもインターネットからでも行え、Citybike card,オーストリアの銀行カード(バンコマートカード)、クレジットカードのどれかひとつが必要です。
ウィーンによく見られるこの時期の花 18 (ウノハナ)

これはドイツ語でDeutzie
(ドイツィエ),ラテン語ではDeutzia,日本ではウツギ属で、ウノハナとも呼ばれています。
東アジアに多く分布し、1m~2.5mぐらいの高さで、世界には60種類程あるそうです。
6月9日に紹介した、Weigelien(ヤブウツギ)はタニウツギ属、スイカズラ科でしたが,こちらはウツギ属でアジサイ科です。
Zierpflanze で観賞用でこちらでは庭や公園に植えてあるのを多く見かけます。
ウィーンで人気のあるアイスの種類
ウィーンも30℃を超え、暑い日が続いています。
昨日の新聞で、WKO・・・Wirtschaftskammer Österreich(オーストリア商工会議所)が行った、現時点で「どのアイスクリームの種類がいいか?」というアンケートです。
ウィーンの自転車文化
ヨーロッパは自転車文化がとても根付いています。
ウィーンも陽気が暖かければ、自転車に乗っている人をとても多く見ます。
またこちらでは朝夕のラッシュ時を除いていくつかの規則を守れば地下鉄に自転車を持ち込んでもいいんですね。
ウィーン市内には自転車用の道が至る所にあります。自転車専用道路というのは中心には少ないですが、自転車専用ゾーンが多く作られています。
Einbahn は一方通行

ヨーロッパはどこの街も
たいていそうですが、一方通行が非常に多いです。
ウィーンでもあらゆる場所に見られます。
この写真のように矢印の中に「Einbahn」(アインバーン)と書かれています。
よくお客様からこの意味を聞かれます。ドイツ語を少し知っていると、Bahn は「鉄道」と
いう意味もあることから、この矢印の方向に駅がある・・・と最初に思われる方が意外と
多いんですね。でもあまりに色々な所に見られるし、駅というのも・・・
何て疑問がその内湧いて来るわけです。
こちらでは交通標識も補助標識との組み合わせも多く見られます。
この写真の例では、一方通行表示の下に「ausgen.」と自転車マーク・・・
これはausgenommen (~を除く)の略した表示で、一方通行だけど
自転車は除くということですね。
ウィーンによく見られるこの時期の花 17 (ベゴニア)

ウィーンの街中で色々な所に見られるベゴニアです。
ドイツ語ではBegonien,
ラテン語でBegoniaです。
原産は南アメリカだそうで、20~60cmの高さ、花の色は白、赤、ピンク、オレンジが多く、熱帯、亜熱帯地方の
原種を交配してとても多くの種類があり、約1500種類ぐらいにのぼるそうです。
「ウィーン」という読み方は日本語です
当たり前のようにこの街の名前は日本では「ウィーン」と呼ばれています。
でもこれは文字通り日本語読みです。
ウィーンは正式にドイツ語で、「Wien」・・・ヴィーンと発音します。
英語、イタリア語では「Vienna」・・・ヴィエンナです。
ドイツ語で「W」は「ヴェー」と発音します。
また「ie」は「イー」と伸ばして発音されますので、Wienはヴィーンと発音されるわけです。
ドイツ語オリジナルのWienから、「W」は英語発音ではWe(私達)のように「ウ」という音になるので、そこから日本語でウィーンと呼ばれているわけです。
ドイツ語圏ではどこでも「ヴィーン」と発音されます。
あの有名な自動車メーカーのVolkswagenもフォルクスヴァーゲンですし、BMWもベーエムヴェーです。
ウィーンによく見られるこの時期の花 16 (バイカウツギ)

6月も中旬に入り、暑い日が続くウィーンです。
春と比べると、花も限られたものが咲いていますが、逆にそれらが
よく目につきます。
これはドイツ語で、Pfeifenstrauch(プファイフェンシュトラウホ)、ラテン語でPhiladelphus coronarius,
日本ではおそらくバイカウツギやサツマウツギと呼ばれています。
南ヨーロッパが原産らしく、1m~3mぐらいの高さで、ほぼ観賞用として庭や公園に植えられています。野生のものはまれです。
大量の白い花を咲かせるため、とにかく目立ちます。
何といっても夕方に強い香りを出すのが特徴で、そこからこちらでは「ニセジャスミン」とも言われています。
ウィーンによく見られるこの時期の花 15 (ボダイジュ)

ウィーンの街のいたる所に見られるおなじみボダイジュです。
ドイツ語では、
Linde (リンデ),ラテン語でTilia です。
ボダイジュにも種類が多くありますが、Sommer Linde(夏ボダイジュ),
Winter Linde(冬ボダイジュ),
Silber Linde (銀ボダイジュ)などがよく見られます。
これらは日本ではセイヨウボダイジュと呼ばれているようです。
ボダイジュは中国原産ですが、ナツボダイジュはヨーロッパ原産です。
高さは40mぐらいになるものもあります。
ハート型の葉が特徴で、そこから更に薄い緑の細長い葉が出て、
そこから実のようなつぼみが出て、それが開いて黄色の細かい花が咲きます。
実際に細長い葉と書きましたが、細長い葉から実までの部分がボダイジュの「花」となっています。
この時期に遠くから見ると、ハート型の葉の緑と、花の部分の薄い緑の2色が混ざって見えます。
ウィーンの3大街路樹のひとつで、公園や庭園にとても多く見られます。
夏ボダイジュと冬ボダイジュの大きな違いのひとつは、花を咲かせる実の数が違います。
夏ボダイジュは、一枚から2~6個、冬ボダイジュは4~12個あります。
写真はプラター公園の夏ボダイジュです。
ウィーンの路面電車やバスの停留所
ウィーンの街は公共交通機関がとても発達しており、普通の生活では
車など必要がないぐらい街に張り巡らされています。
街の至る所に路面電車、路線バスの停留所を見ることができるわけですが、
そのわりに停留所名はまず最初に目に着かない所に表示されています。
バルコニーの花 (ペチュニア)

バルコニーや窓のすぐ外によく飾りとして見られ、大変人気がある花のひとつにペチュニアがあります。
ドイツ語ではPetunien
(ペトゥーニエン),
ラテン語でPetunia です。
原産は南アメリカで、ヨーロッパには18世紀中ごろに伝わったとされています。
雨でも傘をささない?!
こちらでは雨が降っていても傘をささない人が非常に多いです。
雪であればわかるんですけど、ザァーザァー降りになっても傘を持たない人が
とても多いです。日本からのお客様はちゃんと折りたたみ傘を持って観光していますので、傘を持ってない人はまずいません。
傘を持たない人達に話を聞いてみると、「歩く時に邪魔になる」、「どうせすぐ止む」、「地下鉄の駅、路面電車まで、オフィス、家まで歩く距離がそこまで長くない」、
「雨が止んだら傘を忘れる」、「ここまで本降りになるとは思わなかった」等々・・・
色々な答えが返ってきました。
こちらは天気が変わりやすい時期もあります。雲の動きが複雑で、晴れたり、
またすぐに雨が集中的に降ってきたりということはよくあります。
傘のかわりにカッパを持っている人が多いです。
ウィーンによく見られるこの時期の花 14 (ヤブウツギ)

これはドイツ語でWeigelien
(ヴァイゲリエン),ラテン語でWeigelia floribunda、
日本ではヤブウツギ
と言うそうです。
Weigelia はタニウツギ属です。
1m~2mぐらいの高さで、花は5cmぐらいで、白っぽい赤か
このように赤ピンクの色、
もしくはもっと赤に近い色です。
原産は東アジアで観賞用として植えられています。
こちらでは住宅地の中庭や、民家の庭に多く見られ、たくさんの花が咲き終わった中でもひときわ色的にも目立ちます。
こちらヨーロッパでは純粋なWeigelienではなく、観賞用にアレンジされたWeigelienが多く普及しています。
苦情の多い航空会社
昨日の新聞に苦情の多い航空会社ワースト10の統計が載っていました。
いわゆる格安航空会社も中にはあります。
遅れ、欠航、オーバーブッキングなどが多いということが一番の理由のようです。
以下そのリストです。
ウィーンによく見られるこの時期の花 13 (コルクウィッチア)

こちらはドイツ語でKolkwitzie
(コルクヴィッツィエ)、ラテン語でKolkwitzia amabilis,
日本ではショウキウツギとか
アケボノウツギ、そのまま学名で
コルクウィッチアと呼ばれます。
高さは2~3mほどで、原産は中国で、ピンク色が入った白い花を
たくさんつけます。
これはウィーン郊外の有名な温泉地バーデンの公園で咲いていたものです。
とにかく大量の花がまとまって咲くので遠くからでもすぐにわかります。
オーストリアとEU諸国25歳以下の失業率
6月3日付の新聞に載っていたオーストリアの青年失業率と
他のEU諸国の青年失業率の比較記事からです。
これはEU諸国内25歳までを対象としています。
以下EU27ヵ国の青年失業率です。
ユーロ通貨の1,2セントが廃止になる!?
今日の新聞にユーロ通貨の1、2セント廃止に地元オーストリアでは「74%が賛成」
だという記事が載っていました。
ユーロ導入の2002年から現在まで、1セント、2セント硬貨の製造による損失が、1.400,000,000ユーロ・・・だそうです。
日本円で約1820億円ということになります。
生活の中では実際にスーパーなどで買い物しない限り
あまり1,2,5セントは使われませんし、自分も1,2,5セントが財布の中に多くなるのは好きではありませんから、極力支払い時に減らそうとしています。
そういう意味では、1,2セントは廃止した方がスッキリしそうな気がします。
ウィーンの電気バス

3月15日にこのコーナーで「電気バスも走っています」と何気なく書きました。
こちらがその電気バスです。
去年2012年 9月10日に初めて街中で走り始め、リンク内路線の2A,3A に計12台
導入されることになっており、その路線は全て電気バスが活躍することになります。
ザルツブルクなどにあるトロリーバス(電車のように電線に接しながら走る)ではなく、
それ専用の電線は全くありません。
充電は、Schwarzenbergplatz と Schottenring の終点2箇所で行われ、
最長15分の充電時間で、最長走行距離は150kmです。
充電時はパンタグラフのようなもので充電します。
座席は44席、長さ 7,72 m、幅 2,20 m 高さ3,15 mです。
もちろん階段なしのローフロアーです。
ウィーンによく見られるこの時期の花 12 (スイカズラ属)

これはGeißblatt
(ガイスブラット)、ラテン語でLonicera x tellmanniana,
日本ではスイカズラ属です。
ラッパの形をした花が特徴です。
つる性とそうでないタイプ、
常緑タイプと葉を落とすタイプ
とあります。
スイカズラ属は180種類ほどあるそうで、こちらでは観賞用に好まれています。
つる性のものは庭の柵に這わせたり、家の壁に上方に成長させているパターンが多く見られます。
写真はうちの庭のGeißblatt です。このタイプは5月~6月終わりまでと、花が咲く時間がスイカズラ属の中では比較的短いのですが、とても強く、猛烈に多くの花を咲かせます。
全く香りがしません。
このタイプは常緑性ではなく、寒くなると葉を落とします。
こちらは常緑性と葉を落とすタイプと両方好まれています。
ウィーン市交通局からの記事
本日の新聞記事からです。
ウィーン交通局の中間発表によると、今年1月~5月までの間、路面電車、路線バスなどをブロックしてしまう違法駐車が780回あり、そのうち463台が路面電車領域や
バス路線領域に違法駐車されていたそうです。
計317回 消防車、レッカー移動車が出動して、違法駐車している車、バイクを
レッカー移動しました。
ウィーンは路面電車領域のわきギリギリに駐車スペースがある所もたくさんあります。
縦列駐車もピッタリ入れなければ、路面電車領域にはみだしてしまうわけです。
カフェ カプチーノとフランツィスカーナ―
日本からのお客様にウィーンのカフェを飲んで頂く時に、やはりメランジェ、
アインシュペンナーを最初にお勧めしています。
先日5月28日に「ウィーンナーコーヒーはありません」というタイトルでメランジェと
アインシュペンナーに触れました。
ここではもう少し突っ込んでメランジェを含めて
3つのカフェを比較してみたいと思います。
ウィーンによく見られるこの時期の花 11 (クレマチス)

特に一般家庭の庭に多く見られるのが、クレマチスです。
ドイツ語ではClematis
(クレマ―ティス)とか Waldrebe(ヴァルトレーベ)と呼ばれ、
ラテン語でClematis です。
北半球に多く分布し、
原種は約200種類、
現在2000を超える品種があるそうです。